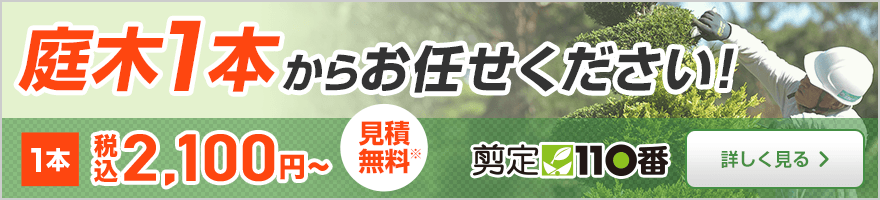ボケは、中国原産の美しい花木です。日本でも古くから大変人気のある種で、庭木や植木などとして広く愛されています。
そんなボケの木を自分でも育てたいといった場合、まずはその特徴から知っていかなければなりません。ボケの特徴から育て方、剪定のポイント、生育の注意点。この記事ではそれらをひとつひとつ、詳しく解説しているので、ぜひ生育の参考にしてください。
ボケの木の育て方をしっかり把握しておけば、きっと美しい花ki があなたの庭や鉢に咲いてくれるでしょう。
目次
ボケとは?その特徴を詳しく解説!
ボケはかわいらしい小さな花が特徴の落葉低木です。近年では庭木として親しまれているほか、盆栽などでも取り扱われており、より一層身近になってきました。そんなボケには、いったいどのような特徴があるのでしょうか。
ボケの季節
ボケは主に3月~5月の春の時期にかけて長く咲く、春の花木です。この開花時期は品種によって異なり、中には冬の12月に咲くものもあります。非常に長い期間楽しめるという点も、ボケの木の魅力ですね。
ボケの外観・色
ボケの外観は基本的に、小ぶりでかわいらしい見た目をしています。近年では美しい形を保ったままサイズを大きく品種改良したものも登場しており、非常に人気のある種となっています。
また、色は赤やピンク、白などシンプルなものが多く、庭木としてもよく映えるでしょう。
ボケのサイズ
ボケは低木と呼ばれていますが、大きいものだと3mほどの大きさまで成長することもあります。この高さは剪定によっても変えることができるため、自分にあったサイズにそろえるようにしましょう。
ボケは寒暖に強い
ボケは寒い環境のみならず、暑い環境もそれほど苦手としていません。この特徴から、ボケは比較的育てやすい植物として知られています。
ボケにはトゲがある!
ボケの木の枝部分には、多くのトゲがあります。このトゲはかなり鋭いため、剪定の際や木に触れる際は注意してあつかうようにしましょう。
ボケの木の植え付け・植え替えの手順とポイント
ボケの木は、基本的に苗を植えるパターンが多いのではないでしょうか。ここでは、ボケの木の植え付けについて詳しく解説していきます。
ボケの木”植え付け”の時期・手順
ボケの木の植え付けは、主に9~10月の秋ごろにおこないます。
手順
1.根の大きさに対して、約2倍の大きさの穴を掘る
2.ボケの木を穴に入れ、根を傷つけないよう注意しながら土を入れていく
※この際、入れる土には腐葉土やたい肥、化成肥料などを混ぜ込んでおく
3.根に水をたっぷり注ぎ、棒などを用いて土になじむように調整する
4.植えた直後は根が定着しておらず倒れやすいため、柱などを立て支えておく
ボケの木”植え付け”のポイント
日当たり・風通しのよい場所に配置しよう
ボケの木を庭に植える場合は、日当たりと風通しをとくに意識しましょう。基本的にボケは、ある程度環境が整っていればしっかり育つ強い木です。日当たりや風通しがそれほどよくない場所でも成長はしてくれますが、その場合虫や病気に侵害されやすくなってしまいます。
水はけのよい土壌が好ましい
日光同様、ボケの木は極度に乾燥するような土壌でなければ基本は大丈夫です。土にはあまり左右されませんが、水はけのよい土であればなおよいでしょう。
ボケの木”植え替え”の手順
ボケの木の植え替えは、植え付け同様9~10月ごろおこないましょう。2年または3年に一度が最適です。
手順
1.根を傷つけないように、丁寧に掘り起こす
2.周りの土を適度に落としつつ、根をほぐしていく
3.古い根に対してはさみなどを入れ、約3分の1を切り落とす
4.新しい鉢などに植え替える
ボケの木”植え替え”のポイント
植え替えの鉢は大きめのものにしよう
ボケの木の植え替えをする場合は、根よりも大きめの鉢を用意しましょう。深さや広さなどをみて、余裕を持った大きさの鉢があると便利です。具体的にいえば、根に対して一回りほど大きいサイズのものが望ましいといえます。
植え替え後は日陰で管理しよう
基本は日当たりのいい場所で育てる方がよいのですが、植え替え直後はその真逆です。植え替え後は木にかかるダメージも大きいため、しばらくは日の当たらない場所で丁寧に育てていきましょう。
ボケの木の育て方とコツを解説!
ボケの木を育てるにあたって、押さえておかなければならないポイントはたくさんあります。ひとつひとつ覚えることで、よりきれいなボケを咲かすことができるようになるでしょう。
水やりは土壌の乾燥度合いをみながら
ボケは乾燥に弱い木ですが、庭植えの場合は土壌に定着すればそれほどこまめに水やりをおこなわなくても大丈夫です。鉢の場合はこまめに水をあげた方がよいですが、庭であれば普段は雨水のみの水分でも十分成長してくれるでしょう。
しかし、暑い時期や土壌が乾燥しているタイミング、植え付け直後などは水分が不足しやすいため注意が必要です。定期的にチェックして、水を与えていくようにしましょう。
肥料のあげすぎに注意
肥料と聞くと土によいものというイメージがあるため、どんどんあげたくなってしまうかもしれません。しかし、これはNGです。肥料を与えるのは1年に2回、または3回程度で十分なのです。
この肥料をあげるタイミングは、植え方によっても変化します。
鉢に植えた場合は、花後の5~6月ごろに1回、油かすなどの有機肥料を与えましょう。また、9月ごろにもあげると効果的です。
庭に植えた場合は1月~2月の寒い時期が適切です。この場合も同様に、油かすなどの有機肥料を与えましょう。また、大規模な剪定をした後にも肥料をあげると効果的です。それ以外の期間は、とくに肥料を与える必要はありません。
挿し木をすればボケの木を増やせる
ボケの木を生育していく中で、ボケの木を増やしたいと思うこともあるかもしれません。そのような場合は、『挿し木』という方法を使えばボケを増やすことができます。
挿し木とは株や枝の一部を利用して、新たな木として生長させる方法です。
まずは、ボケの木の枝を数十cmほど切り落としましょう。この枝は、伸びすぎてしまった枝などを再利用しても大丈夫です。その切り落とした枝を、数時間水につけておきます。
2~3時間ほどたったら、枝を土に挿し込みましょう。この際、無理に挿し込むと枝が折れてしまう可能性があるため、挿し込みに無理がありそうなら、事前に土に小さな穴を開けておきましょう。
また、この土は主に挿し木用の土が望ましいとされています。挿し込みまで終わったら、日陰で丁寧に、水を絶やさず育てていきましょう。
植える場所とトゲの関係
前述したように、ボケの木にはトゲがあります。ボケの木は生垣などにも向いているため、防犯・防獣の面でも役にたつでしょう。
しかし、ボケは成長の速度が速いため、放っておくと道路などに飛び出してしまうこともあります。その場合、近隣の住民にもトゲの危険が迫ってしまうため、植え替える場所を決める際は、注意して決めるようにしましょう。

ボケの木をおそう『病気』と『害虫』
ボケの木を生育していくにおいて、注意しなければならないのは『病気』と『害虫』です。このふたつを甘くみていると、木が枯れてしまう事態におちいってしまうかもしれません。
ボケの木の病気
ボケの木は、以下のような病気にかかってしまう恐れがあります。特徴を知って、早めの対策を心がけましょう。
赤星病
赤星病はその名の通り、葉の表面に赤みがかった斑点模様が浮かび上がる病気です。主に春ごろのあたたかい時期に発症しやすく、病状が悪化すると斑点部分から白い毛のようなものが複数生えてきます。
この病にかかってしまうと、葉の部分から徐々にボケが枯れていってしまうでしょう。対策としては、専用の水和剤など薬剤を散布する方法や、発症した葉を摘み取って処分する方法があります。
根頭がん種病
根頭がん種病は、根が菌の影響により膨れてしまう病気です。土から感染する病気なので、植え替えなどの際には根に傷がついていないか、しっかり確認するようにしてください。
この病気は、一度かかってしまうとなかなか治りません。感染してしまった場合は、そのほかの木に影響を出さないためにも土ごと破棄してしまいましょう。
ボケの木の害虫
ボケの木を生育していく中で、害虫に住みつかれてしまうと生育に悪い影響を与えてしまいます。ボケの木につく代表的な害虫を知って、対策方法を確認しておきましょう。
アブラムシ・カイガラムシ
アブラムシは、主に黄緑をしていることの多い小さな虫です。また、カイガラムシは主に白に近い色で、かいがらのような見た目をしています。この2種の害虫は主に枝や葉の部分などに発生し、住み着かれると樹勢を弱める上、病気の原因となることもあります。
アブラムシは3~5月ごろ、カイガラムシは5~9月ごろが発生しやすいですが、基本的には年中警戒しなければなりません。ボケの木の風通しが悪いと発生しやすいため、剪定などの環境メンテナンスを欠かさないようにしましょう。
万が一発生してしまった場合は、害虫用の殺虫剤・薬剤などを使用してください。
グンバイムシ
グンバイムシは、葉裏に発生することの多い害虫です。この虫も葉から汁を吸うため、早急な対処が求められます。グンバイムシがついた葉には白色の斑点や黒色の排せつ物が残るため、その特徴を目安にしましょう。
予防方法も、基本的には風通しの良化が有効です。薬剤なども効果的なので、発生してしまった場合は速やかに駆除するようにしましょう。

ボケの木の最適な剪定時期&適切な剪定方法
ボケの木の美しさを維持するためには、剪定作業が必須です。また、正しく剪定をすれば害虫や病気の予防にもつながります。この剪定作業は少々難易度が高いため、ここで手順や時期を紹介しておきましょう。
ボケの木の剪定時期と方法
ボケの木の剪定は、主に花後の『5~6月ごろ』と落葉する『11~12月ごろ』の2回おこないます。
5~6月ごろの剪定
5~6月ごろになると、開花期を終える花も出てきます。この花がらは、放置していると実になります。実も観賞したいという方はそのままでよいですが、とくに必要ないという方はここで摘み取りましょう。
花がらの処理が終わったら、今度は枝を短く切っていきましょう。
この時期になるとボケの木は生長し、余分な枝や伸びすぎた枝などで木全体が混雑してきます。弱った枝や絡まった枝など、余分な枝は根元から切り取ってしまいましょう。また、伸びてしまった枝は3cmぐらいの長さに切り戻します。この際、花芽を2、3個残すように切り戻すと有効です。
11月ごろの剪定
冬ごろの剪定では、春同様枝を切り戻していきます。春から冬にかけて生長し、伸びてしまった枝を調節していきましょう。
この剪定でも、花芽のついた枝は芽を2、3個残します。その上で、しっかり切り戻していきましょう。また、花芽のついていない枝も1cm程度に切り戻しておくと、風通しがよくなり生育によい影響を与えます。この際、不要な枝は切り戻しではなく、根元からしっかり切り落とすようにしましょう。
ボケの木の剪定する際のポイント・注意点
ボケの木の剪定をする際には、押さえておくべきポイントがいくつかあります。
トゲに注意
前述しましたが、ボケの木にはトゲがついています。このトゲはかなり鋭く、不用意に触れるとケガのもととなってしまうでしょう。
剪定の際は軍手などで肌を隠すのはもちろん、極力トゲに触らないように気をつけて作業を進めるようにしましょう。
挿し木で増やしたボケは生長するまで数年待つ
挿し木で増やしたボケの木を剪定する場合は、数年間待ってからおこなうようにしましょう。生長しはじめのころは、木自体をどんどん大きくしていく方が先決です。
根が定着し、幹が太く生長するまでは、不要な枝の間引き程度にとどめておいた方がよいですね。
剪定に慣れていないなら業者に相談
剪定は、少々慣れが必要な作業です。剪定のできは木の生育や外観に大きな影響を与えることとなるため、かなり緊張する作業となるでしょう。また、トゲや高所作業など、初心者には不安な点も多くあります。剪定作業に悩みのある方は、業者に委託して代わりにやってもらいましょう。
業者に作業してもらえばきれいに木を整えてもらえる上、今後の相談などもできます。ボケのような小さな木であれば、相場は約1,000~3,000円と比較的安めです。興味のある方は一度見積もりと相談をしてみてはいかがでしょうか。
まとめ
ボケの木は幅広い環境で育つ、比較的育てやすい木です。しかし、植える場所や風通しなどに注意しておかなければ病気や害虫の被害にあうおそれもあるため、注意して生育するようにしましょう。
また、ボケの木の生育に欠かせない要素に『剪定』という作業がありました。この作業は木の外観を整えるだけでなく、風通しをよくして健全な木の生長を助ける効果もあります。時期をみて、毎年欠かさずおこなうようにしてください。
しかし、剪定は慣れていなければどうしても難しい作業になります。自分でできる場合はよいですが、剪定に不安のある方はプロの業者に依頼して代わりに剪定してもらうとよいでしょう。
剪定を依頼できる業者や料金
依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「剪定」をご覧ください。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!