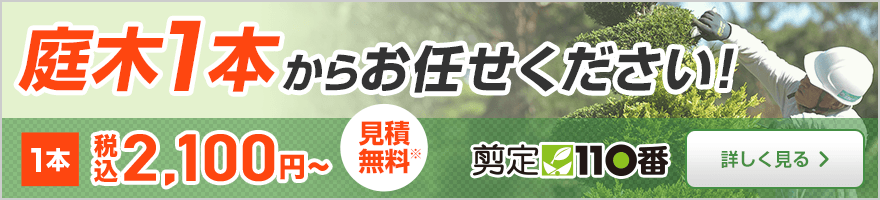道路から家の様子が見えないよう、目隠しに木を植えたい。近年では景観づくりの一環として補助金を出している地方自治体も多く、ブロック塀に変わって生垣が増えつつあります。その生垣として使える木のひとつが「レッドロビン」という樹種です。
ただ「レッドロビン」という名前を聞いてもイメージが湧きにくく、ましてや剪定などの手入れ方法はよくわからないという方は少なくないでしょう。今回はそんなレッドロビンの剪定方法を、そもそもどういう特徴の木なのかを含め細かく解説していきます。
目次
そもそもレッドロビンってどういう樹木?
レッドロビンはバラ科の植物で、ベニカナメモチやセイヨウカナメとも呼ばれることがあります。その正体はいったい何なのでしょうか。
生垣や庭木などの園芸品種として人気
レッドロビン自体はカナメモチのひとつの園芸品種として扱われることが多く、その正体は一般に自生するカナメモチと、それより大型の葉を持つオオカナメモチを掛け合わせたものです。
どちらも中国から日本にかけて分布する種ですが、レッドロビンは分布と異なり、アメリカにおいて開発されました。胸元が赤い鳥「コマツグミ」のアメリカでの愛称「ロビン」にちなみ、名づけられたのです。日本ではベニカナメモチと呼ぶことがあるものの、本来はレッドロビンのみを指すことばではないことに注意しましょう。
ちなみにカナメモチの「モチ」は葉の形が「モチノキ」に似ていることから、「カナメ」の部分は「赤のモチ」がなまったとも、木材として丈夫であり、扇の軸となる「要」に使ったからともいわれています。掛け合わせということもあり、葉自体も本来のカナメモチより大きなものに生長します。
鮮やかな葉色を楽しめる樹木
カナメモチの大きな特徴は「春の新芽が赤く色づく」こと。そして葉が生長するにつれ、緑へと変化していく点です。これは新芽に多くのアントシアニン(酸性状況で赤色になる色素)が含まれており、葉緑素(クロロフィル)が生成されるにつれ緑色素を増やしていくことに由来します。紅葉はクロロフィルの分解とアントシアニンの生成によって色づくことから、まるで逆のプロセスをたどっているかのようです。
この新芽部分を使い、剪定のついでに草木染めへ挑戦してみるのも面白いかもしれません。
病気や害虫に強い
レッドロビンが生垣に向いている理由のひとつとして、害虫や病気に比較的強いことがあげられます。生垣は道路に面した外部からのリスクが大きい位置に植えられるものであり、そのぶん病気の感染源に接する機会も多くなります。しかし簡単に枯れてしまうようでは役割を果たせないため、見た目もよいレッドロビンが選ばれやすいのです。
こうした特徴を持つレッドロビンは生垣作りに向いているといわれ、現在多くの住宅敷地内に植えられています。

レッドロビンを生垣として使うためのポイント
住宅を建てるときや塀の改修でレッドロビンを新たに植えるときのポイントを、ここでは解説します。
生垣の場合でも木の間隔は50cm空ける
生垣として使うには木同士の間隔を詰める必要がありそうに感じますが、レッドロビンは生長の早い木。あっという間に上へ横へと延びていきます。十分な栄養やスペースを確保できるよう、50cmは間隔をあけて植えるようにしましょう。
肥料や水やりなどの手入れを忘れずに
地面に定着するまでは植物にとって過酷な時期です。余裕を持って肥料や水やりをおこないましょう。一方一度根付けば、こうした水やり・肥料やり作業は不要になります。
日当たりがよく、水はけのよい土地に
ほとんどの植物にとって日光は、栄養を作り出し生命を支える大切な役割を果たします。 一方水分も植物にとって重要な一方、多すぎると根などを腐らせる原因となるのです。レッドロビンも日当たりのよい土地を好むため、植える場所に関しては一度よく条件を検討しましょう。
知っておきたいレッドロビンの特徴
ではレッドロビンを剪定する際に気を付けるポイントについて解説していきます。
レッドロビンは生長の早い樹木
レッドロビンは生長が早く、同時に多くの枝を伸ばしていきます。そのため目隠しとしても早くから使えるようになるでしょう。ただ形を整えても、すぐに生長した枝が飛び出してくる点には注意が必要です。
生垣として機能させるには剪定が必須!
レッドロビンは基本上へ、上へと生長していきます。そのため剪定をしないと横方向へ十分に枝を伸ばさず、目隠しの機能を果たさなくなってしまうのです。また上への生長を押さえなければ下の方が枝分かれせず、普通の木のようにスカスカとなってしまいます。すると下の部分は目隠しにならず、生垣としての機能を十分に果たすことができません。
強く刈り込む場合はこまめに手入れをしよう
庭木の中には刈り込みに弱く、太い枝を切ってしまうとそのまま枯れてしまいやすい種類も存在します。しかしレッドロビンは根元から切っていっても枯れにくく、その切り口から多くの枝を分岐させていきます。
ただし刈り込みに強いぶん、放置するとさまざまな方向から枝が伸び始めることには注意が必要です。そのため剪定を怠ればすぐに見た目の悪さに直結します。とくに上へと枝を伸ばしやすいことを意識し、年数回にわけて剪定の予定を組むようにしてください。

レッドロビンの剪定・刈り込みは適切な時期に年3回!
刈り込みに関しては定期的におこなっていくことが大切です。「春」「初夏」「秋」の年3回を基本として、随時作業をおこなっていきましょう。
春は大胆に刈り込む
春から夏にかけては生長も早い時期のため「大胆に刈り込む」ことも可能です。できれば希望する高さよりも少し低めに切り、葉や枝の生長を見守ってあげましょう。また枝を切ることでそこから枝分かれさせ、密度の濃い生垣へと育てていくことができます。その際は見た目も重視し、枝の根元から切るようにしてください。
初夏は全体を整える
レッドロビンは小さく白い花を咲かせます。花が終わった後、春から予想外に増えた枝などを切っていきましょう。少し切りすぎたと思っても意外と早く生長するため、大胆に切ってしまっても構いません。表面の枝を一通り切り新芽を出すことで、「赤み」をより長く味わうこともひとつの選択でしょう。
秋は細い枝だけを切る
木にとって寒い冬を乗り越えることは厳しく、余分な枝に対して栄養を与えたくないもの。その前にあらかじめ枝を切っておきたいことろです。ただレッドロビンの場合、10月くらいからは次の春に向けて養分を蓄えていく期間へ入っていきます。治癒も遅くなるため切りすぎは禁物。確実に樹形形成の妨げになる、細い枝だけを切っていくのが無難といえるかもしれません。
一度樹形が整ったら、細かく手入れをしよう!
植え始めて当初は枝分かれも少なく、できるだけ根元で切り取って枝分かれを増やしたいところです。しかしいったん生垣として整えば枝よりも形に意識を向け、形を維持することに焦点を向けていきましょう。
ただし枯れかけている・変色している枝葉は病気にもつながっていきます。こうしたところが見つかったときは優先的に取り除くようにしてください。
まとめ
レッドロビンが持つ特徴はより早く、より元気のよい生垣を作るのに適しているといえるでしょう。しかしそのぶん生長が早く、剪定よりコントロールしていく必要があります。生垣を作る際は定期的な剪定が必要であることを念頭に、管理しやすい場所を選ぶようにしましょう。
なおレッドロビンの剪定は木自体が刈り込みに強く自分でもおこないやすい部類に入りますが、最初数年はどうしても生垣の形が定まらず、失敗しがちな面も否定できません。自分での剪定に不安であればプロに依頼するなどして、安定した形を保つようにしたいところですね。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!