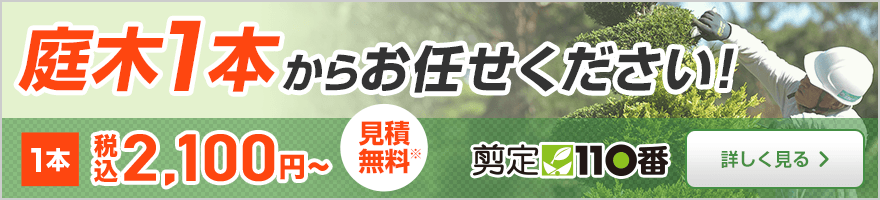くるみは栄養価が高く、ビタミンや葉酸を含んでいるので栄養補給として子供からご年配の人、特に妊婦さんにおすすめの食材です。近年では、そのまま食べるだけでなくパンやお菓子作りにも重宝するので、人気が高まっているそうです。
健康維持のために、少量でも毎日食べたい人はくるみを育ててみてはいかがでしょうか。くるみは、比較的手間がかからず、育てることができます。そこで、今回はくるみの育て方を初心者の人でもわかりやすく、重要ポイントをおさえてご紹介していきます。
目次
くるみの育て方
日本で栽培されているくるみの種類はいくつかありますが、すべてのくるみが食べられるとはかぎりません。じつは、食べられないくるみも存在するのです。
くるみを収穫して食用にしたいのであれば、「ペルシャグルミ」がおすすめです。この品種は、日本でよく販売されているくるみのひとつです。実を多く収穫したいときは、接ぎ木で増やす方法もあります。
くるみの栽培は、風通しがよくて、日当たりがよい場所が適しています。土は、赤玉土と腐植土を3:1の割合で混ぜると成長がよいといわれています。水やりは、庭植えでは植えた直後はしっかりとあげて、それ以外であれば雨水ぐらいでじゅうぶんです。
鉢植えは、表面が乾いてきたら多いと感じるぐらいあげましょう。くるみはほとんど肥料がいらないですが、実をたくさんつけたいのであれば、有機質の肥料を与えてみてはいかがでしょうか。
くるみの育て方は人によって異なります。食用以外にも、観賞用として育てている人もいます。くるみは放っておくと大きくなりますが、きちんと剪定してあげると屋内でも育てることができるので、自分のライフスタイルにあわせて育てていきましょう。

くるみの木を剪定する方法
くるみは育て方ひとつで、実のつき方が変わってきます。質のよい実をつけるに剪定は、大事な作業工程のため正しい方法を身につけていきましょう。
くるみの剪定は、葉が落ちはじめた冬が適しています。この時期は、くるみが休眠に入るタイミングで、剪定してもダメージが少ないといわれています。時期がずれると新しく生えた花芽を切ってしまうおそれがあり、花つきが悪くなる原因にもなるのです。
くるみの剪定は、若い木と古い木で切り方が異なります。実がまだついたことがない若い木は、徒長枝やからみ枝といった不要な枝が生えてくることが多いです。不要な枝が多いと幹に日が当たりづらくなり、木の成長を妨げる原因になります。枝と枝の間隔をあけてあげて、不要な枝を根元から切り落としてください。
古い木の剪定はほとんど必要ありません。枝が込みあってきたと感じたら、間隔をあけて不要な枝を切ってください。風通しがよくなることで、害虫予防にもつながります。しかし、初めて剪定を行う際は、どの枝を切ればいいか判断が難しいでしょう。間違った方法で剪定したら最悪の場合、実がつかなくなってしまうかもしれないため困ったら業者に相談してみてはいかがでしょうか。
くるみの木を植える場所は慎重に選ぼう
くるみの栽培には、気をつけてほしいポイントがいくつかあります。ポイントをおさえておけば、手間がかからずに育てることができるので覚えておきましょう。
くるみが育ちやすい環境
くるみの栽培は、年間を通して日当たりがよく、涼しい場所が育ちやすいです。観賞用として屋内で育てたい場合は、寒暖差が大きいと木の成長によいといわれているので朝・夜は屋外、昼は室内など環境を変えてみてはいかがでしょうか。
地植えの栽培では夏の直射日光を避けるのはもちろんのこと、冬は芽が霜焼けしないように気をつけましょう。寒さに強いからといって雪などがついたままほうっておくと、芽の成長を妨げる原因にもなりますので注意が必要です。
2種類の木を植える必要がある
くるみは1本の木に雄花・雌花が咲きますが、それぞれ開花のタイミングが違うので、1種類のみで育てても実がつきにくいのです。そのため、雄花が先に咲く品種と雌花が先に咲く品種を一緒に植えることで、実がつきやすくなるといわれています。
高いところから落ちる
くるみは、庭など広い場所で育てていると木が大きくなります。収穫時期になると実は自然と落ちはじめますが、高い木を揺らして落とす場合は気をつけてください。殻つきの実は固く、頭に落ちると危ないので、ヘルメットなどできちんと保護してから落とすようにしてください。
他感作用(アレロパシー)がある
くるみには他感作用といって、くるみの木から発する化学物質が他の植物の成長を妨げてしまうおそれがあるのです。これは昆虫にも影響があり、くるみの木には昆虫が寄りつかないともいわれているのです。他の植物と一緒にくるみを育てる方は、他感作用に注意しましょう。

くるみを育てる方は害虫・害獣に要注意!
くるみは、虫が寄りつかないといっても害虫被害がまったくないとはいいきれません。剪定せずに放置して、虫の住処になってしまった人も多いのではないでしょうか。害虫を予防するためにも剪定は大切です。では、くるみにはどんな害虫・害獣に気をつければよいか見ていきましょう。
くるみはコウモリガがつきやすいのです。この害虫は、くるみの幹や枝の内部に入って、食い荒らして空洞にしてしまいます。空洞になった幹は折れやすく、木の成長を妨げてしまうおそれがあるので、見つけたら早めに対処しましょう。ワイヤーなどの先がとがったものでとりだして駆除してください。
くるみは栄養が豊富なので、人間以外にも動物も好んで食べてしまいます。山や森などの自然が多い場所だと、リスやカラス、ネズミなどの小動物が食べてしまうことがありますのでくるみを育てる方は気をつけましょう。
まとめ
くるみの実を収穫したいのであれば、食用の品種を選んで栽培してみてはいかがでしょうか。栽培環境が整っていると育ちのよい実が収穫できるかもしれません。くるみを育てる方は他感作用に気をつけましょう。
くるみの実がならないときは、2種類の木を植えてください。それでも実がならないときは害虫被害や、剪定方法が間違っているおそれがあります。くるみを収穫するには正しい剪定が必要です。
くるみの木は高さがあるので、自分で剪定をおこなうのが不安な人も多いでしょう。そのときは業者にお任せするのもひとつの方法です。
剪定を依頼できる業者や料金
依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「剪定」をご覧ください。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!