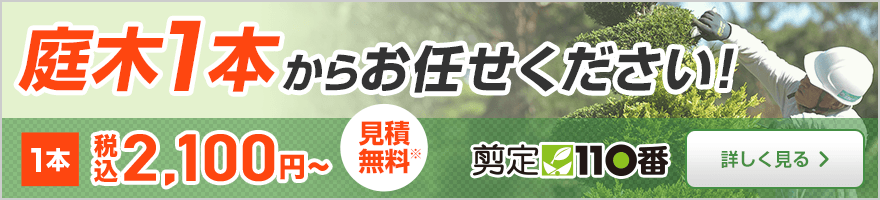モチノキは、枝や葉が多い植物です。高さもあるため、手入れが大変だと感じてしまうかもしれません。しかしそのまま放置すると、知らないうちに病気にかかったり腐らせてしまったり、最悪の場合枯らしてしまうことになります。
そうならないためにも必要な知識を取り入れて、しっかりと手入れをしてモチノキを長生きさせてあげましょう。どのように手入れをするかによって、育成に変化が出てしまうかもしれないので正しい方法を知っておくことは大切です。
そこで今回は、モチノキの剪定についてご紹介します。また、剪定するにあたって、正しいやり方や剪定時期などもご紹介します。
目次
庭木の剪定は病害虫を対策する効果もある!
モチノキも生き物なので、病気にかかってしまうことがあります。その中でも「すす病」という病気はかかりやすいので、注意が必要です。
注意が必要な病気
すす病とはカビの仲間で、黒いシミのような模様があらわれます。この病気は、植物自体に増殖し発症します。さまざまな植物でも発症してしまう恐れがあるもので、野菜や果物はもちろんのこと、観葉植物にも起こる危険性のある病気です。
すす病にかかってしまった場合、光合成ができなくなり、成長の妨げになってしまいます。植物の内側にも侵食してくるので、できるだけ早めに対処が必要となってきます。すす病を引き起こす要因は、アブラムシやカイガラムシなどの害虫です。どのような被害があるのかご紹介します。
注意が必要な害虫
・アブラムシ
葉などに寄生して汁を吸い、栄養を奪います。また、アブラムシが出す排泄物はすす病を引き起こす原因となってしまいます。群れでいる場合は影響力が非常に大きくなるため、見つけたら早期に駆除したほうがよいでしょう。アブラムシは春から秋のはじめにかけて発生するため、要注意です。
・カイガラムシ
木の枝や幹に寄生して栄養を奪い、その影響で発育が悪くなってしまうことがあります。また、アブラムシと同様に、排泄物によってすす病を引き起こす原因となってしまうので注意が必要です。年中発生する可能性があるので、日頃から気にかけてあげるとよいかもしれません。
すす病を発症してしまったときの対処法は、発症していると思われる部分を拭き取るだけでも効果があります。また、定期的に害虫がついていないかの確認をおこなうことや枝同士の風通しをよくするために、モチノキの剪定は害虫から守るための大切なこととなります。
モチノキの特徴を知って適した時期に剪定を
モチノキの剪定時期は、開花が終わったあとに新芽が丈夫になり葉が伸びてくる、6月から7月頃が最適といわれています。秋ごろに枝が少し伸びてきたときは、整える程度に剪定してもよいでしょう。
大きくなりすぎてしまったモチノキを剪定する時期は、2月ごろが目安となります。花が咲くのが4月なので、花が出てくるまえに強めの剪定をしておけば、比較的早めにモチノキが回復します。
また、数年に1回程度で、枝透かし剪定と呼ばれる剪定をおこなうのもよいでしょう。枝透かし剪定は、通気性をよくするためにおこなうものです。枝が多いと風通しが悪くなってしまうので、害虫などの被害や病気の原因になることもあります。
モチノキの剪定の適期に病害虫の活動が目立ってきますので、剪定中に被害を受けていないかしっかりと確認することは大切です。病害虫が増える時期の剪定は重要なので、おろそかにはしないほうがよいでしょう。
モチノキの剪定方法
モチノキは剪定に強く、刈り込みしても頑丈な植物なので心配はいりません。刈り込みとは、高さや全体の大きさを整える手法です。剪定とは違い、枝や葉を多く残すので、見た目を重視する方はよい手法かと思います。また、強めの刈り込みをしても耐えることができるので、すっきりとさせたい方はバッサリと切ってしまうことも可能です。
しかし、強く刈り込みをすると、数年の間は花や実のつき方が悪くなってしまうこともあります。何度も強い剪定を繰り返すと、モチノキ自体の栄養のたくわえがなくなってしまい、弱ってしまったり枯れてしまったりすることがあるということです。そのため、ほどよい剪定をすることを心がけるのも大切といえます。
ほかには、風通しや日当たりを重視する方は、剪定をするのもよいでしょう。風通しがよいと、病害虫の発生をおさえることができます。成長のコントロールをすることもできるので、大きさが気になる方は、剪定するのもよいかもしれません。

モチノキを剪定するときのコツ
モチノキは大きな木なので、どう剪定したらよいのか分からない方もいると思います。そこで、モチノキを剪定する際に大事なことをご紹介します。
剪定をする際、下部よりも上部をていねいに切り込みましょう。上部がきれいに剪定されているほうが、美しく仕上がったように見えるからです。そのため、上部に時間をかけるとよいでしょう。
上部の剪定は、交差している枝や、一直線に真上に伸びてしまっている枝を切ります。この枝は必要な栄養を吸収してしまうため、ほかの枝に栄養がいかなくなってしまいます。見栄えをよくすることもできるので、これらの枝は切ってしまいましょう。
モチノキの全体を剪定をするときは、Yの字を意識して剪定しましょう。まず、枝を見たときに、余分に生えている部分を切ります。枝と枝の間に伸びている部分を切るとよいでしょう。切ったあと、余分な葉も軽くとって形を整えます。これらをするだけで見た目も非常によくなります。
しかし、どの部分を剪定すればいいか分かりにくかったり、どう切ってもYの字にならなかったりする場合もあるでしょう。そんなときは無理にYの字にせず、あえて1本にしてしまったほうが、自然な見た目になります。
また、枝の上側の葉を少なめにし、下側の葉を多めに残す剪定を意識するとよいでしょう。バランスよく見え、遠くから見た形もきれいに映ります。切ることに意識しすぎると、枝や葉が残らずさみしい印象になってしまうので、ほどほどのところできりをつけるとよいでしょう。
庭木の剪定は無理をしないことが大切
モチノキは、高さが5メートルや6メートルあるものが比較的多いです。そのため、自分で剪定しようと思ってもなかなか手が出ません。
また、剪定方法をご紹介しましたが、モチノキの剪定はセンスがとわれるそうなので、思ったような剪定ができないかもしれません。失敗してしまうのが怖いと思う方は、無理をしないで業者に頼むことがよいでしょう。
モチノキを剪定してくれる業者はさまざまにありますが、どのように剪定してくれるかはどうしても違いが出てきます。業者の特徴やサービス、作業内容なども事前に調べておくとよいでしょう。
たとえば、地域に密着した業者に依頼すると、土地や気候にあった剪定を心がけてくれることがあります。地元に生息している植物を把握していたら、安心して依頼できるのではないでしょうか。また、庭木1本からでも請け負ってくれたり、休日でも対応してくれる業者もいるそうです。
このように、自分の生活環境や庭にあった剪定をしてくれる業者を見つけて、依頼してみてはいかがでしょうか。
まとめ
モチノキを剪定するにあたり、時期や方法など気をつけておくとよいことが多くありました。病害虫の被害にあうと、対処するのは大変です。病気になってしまうまえに害虫を駆除できるよう、日頃から観察をするとよいでしょう。
モチノキは樹高が伸びてくると、個人で剪定することが難しくなります。失敗したり高所作業が危険だなと感じたら、業者に依頼することをおすすめします。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!