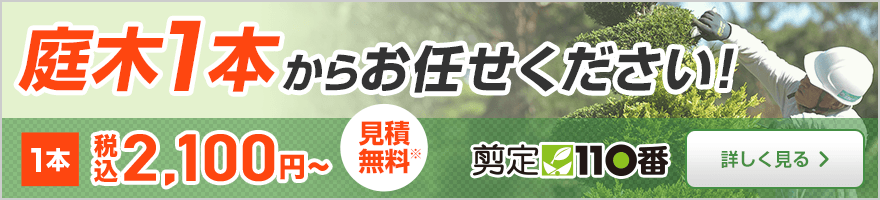黒竹は放置しているとどんどんと伸びていき、手がつかなくなるほどになってしまいます。そうならないためにも、黒竹の剪定をしっかりとおこなうことが大切です。
なぜなら、黒竹を剪定して短く切ることによって、黒竹の高さを調整することができるからです。また、黒竹の見た目を整えることができるので、より黒竹の魅力を楽しめることにもつながるでしょう。
当記事では、黒竹を剪定するときに知っておきたい剪定時期や方法について解説。さらに、鉢植えの植え付け手順や枯れる原因についても紹介しています。これから黒竹を育ててみたいという方も参考にしてみてください。
目次
黒竹の剪定で棹を整えよう!
棹(さお)とは、樹木でいう「幹」にあたる部分のことをいいます。黒竹の伸びすぎを防ぐためにも、棹の高さを調整しておきましょう。ここでは、黒竹の剪定で必要な事柄について解説します。
黒竹の剪定時期と必要な道具

黒竹の棹は始めから黒いわけではなく、最初はほかの竹の種類に近い緑色をしていて、年齢が上がるとともに黒みをおびていきます。それにともない、黒竹の剪定時期が異なってくるので注意しましょう。具体的には、棹の色によって以下のタイミングで黒竹の剪定をしていきます。
【棹の色と剪定時期】
緑色: 3~4月
黒色: 6~7月
また、黒竹の剪定で使う道具は「剪定バサミ」です。ただし、切る必要のある棹や枝が太い場合は、太い枝でも切れるハサミやノコギリが必要になるでしょう。切り口を傷つけないために切れ味がよいものを選び、除菌をして清潔な状態で使用するようにしてください。
黒竹の剪定方法
黒竹の剪定方法は1つだけでなく、目的に合わせておこなういくつかの方法があります。その方法の詳細について項目別でご紹介しましょう。
・芯止め
黒竹の「芯」の部分となる棹の先端を切ることで、それ以上伸びないように生長を止める剪定方法です。方法はとても単純で、調節したい長さの位置で棹にハサミを入れて切るだけでおこなえます。
また、黒竹の葉を増やしたくない場合は、枝に対しても芯止めをおこないます。伸ばしたくない枝の先端部分を狙って剪定バサミで切り取りましょう。そうすることで、枝と葉が少なくなるので、黒竹の棹がよく見えやすくなります。
・切り戻し
切り戻しとは、枝を短く切り落としていく剪定のことをいいます。黒竹の剪定では、生えてから1年目の枝に対して3~4節を残すように、節の位置を狙って剪定バサミで枝を切り落としていきます。2年目以降は、前回切った節から1節ずつ切り詰めていくようにしましょう。
・間引き
黒竹が生えすぎて密集している状態の場合は、良い状態のものを残してそれ以外を取り除く「間引き」をおこないましょう。4~5年以上経って古くなってきたものや細いものを優先して間引いておくことで、若々しい黒竹を長く楽しむことができます。
作業がむずかしいなら業者に相談しよう
もし、数が多すぎて黒竹の剪定作業が大変、黒竹が高く生長しすぎて手に負えない状態の場合は、無理をせず剪定のプロに依頼しておくのがよいでしょう。剪定のプロに依頼をすることで、手間をかけずに黒竹の剪定をしてもらえます。
ちなみに、庭木の剪定をおこなう費用相場は、業者にもよりますが7m以内の範囲であれば、5,000~20,000円の範囲内で済むことが多いです。ただ、状況によって料金が左右する場合があるので、気になる方は料金の見積りを取ってもらうとよいでしょう。
また、弊社では黒竹の剪定が得意な業者を紹介することが可能です。もちろんお見積りを取ってもらうことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
黒竹の特徴と植え付け方法
黒竹にあこがれて育ててみたいという人もいらっしゃるでしょう。黒竹の栽培はしやすいほうですが、栽培を始めるまえに知っておきたいことがあります。ここで、黒竹の特徴と植え付け手順を紹介します。
栽培する前に知りたい黒竹の特徴

黒竹は炭のように真っ黒な棹が美しい植物で、生えたてのうちは緑色をしていますが時期が経つことに黒くなっていき、2年ほどを目安に真っ黒の棹になります。さらに、比較的丈夫な植物であり、初心者でも手入れがしやすい部類に入るでしょう。ただし、黒竹の注意点としては「生育旺盛すぎる」という点が挙げられます。
黒竹をはじめとした竹の種類は、「地下茎」とよばれる構造をしており、地面の下の根がぐんぐんと延びていき、個体数を増やしていきます。とくに地植えの場合は、根が広範囲に広がってしまうので、対策をせずに植え付けをすると手に負えなくなるほど増える可能性があるのです。そのため、基本的には鉢植えで黒竹を栽培するほうが無難でしょう。
鉢植えでの植え付け手順
それでは続いて、黒竹を鉢植えで栽培する場合の植え付け方法について解説していきます。ほかの植物と植え付け手順はあまり変わらないため、そこまでむずかしい作業ではないでしょう。
【黒竹を鉢植えで植え付ける手順】
1.大きめの鉢に鉢底ネットを敷いて、鉢底石をある程度入れる
2.「赤玉土8:腐葉土2」で混ぜた土を鉢に入れる
3.苗を新しい鉢に入れて、土をかぶせる
4.支柱を立てる
5.たっぷりと水を与えておく
植え付けをする際のポイントとしては、まっすぐに伸ばすために工夫すること。新しい鉢に苗を入れるときに、しっかりと直立するように調整しておきます。さらに支柱を立ててヒモで棹を軽く固定することで、黒竹の生長方向を誘導しておくと伸びたときに見栄えがよくなるでしょう。
庭植えならプロにお願いしてみよう
先ほども伝えたとおり、庭植えの場合は地下茎が広く延びるため、繁殖のしすぎで庭が竹で埋め尽くされてしまうおそれがあります。そのため、黒竹を庭植えで栽培する際は、根の広がりを遮断するための「防竹シート(防根シート)」を用いた植え付けが基本です。
しかし、防竹シートの設置は大掛かりな作業となり、丁寧に施工をしないと十分な効果を得ることができません。そのため、業者に依頼して防竹シートの施工と黒竹の庭植えを代行してもらうほうが安心できるでしょう。
注意したい黒竹の栽培管理
きれいな黒竹を楽しむためには、黒竹の剪定のほかにも普段の栽培管理方法に気を使うことも大切です。そこで、黒竹を栽培するための基本や注意点について解説していきます。
美しい棹を活かすなら日当たりにこだわろう

黒竹ならではのきれいな黒色の棹を活かすためには、日当たりのよい環境が必要になります。一応、半日程度の日の光が当たる「半日陰」でも栽培することが可能ですが、日光が当たらない時間が増えると、黒竹が枯れる原因を作りやすくなるので注意が必要です。
また、日当たりとともに「風通し」にも十分に気をつけましょう。黒竹同士が密集している状態の場合は風通しと日当たりが悪くなるので、間引きによる黒竹の剪定で黒竹の数を減らしておくと風通しを改善できます。
鉢植えの場合は水やりが必要
黒竹は比較的丈夫な植物ですので、庭植えの場合なら自然に降る雨水だけで育てることができます。そのため、極端な環境のときを除いて基本的に水やりは必要ありません。しかし、鉢植えの場合は土が乾燥しやすいので定期的な水やりをすることが大切です。
鉢植えでの水やりは、鉢の土が乾いたタイミングで根元にたっぷりと与えるのが基本。とくに夏は土が乾燥しやすい季節なので、それに合わせて水やり頻度や量を上げておくのを忘れないようにしてください。
また、普段の水やりとは別で「葉水」もおこなうことをおすすめします。葉水とは名前のとおり葉の表面に水を与えることです。霧吹きに水を入れて、葉の表面を掃除するように吹きかけていきましょう。これにより、葉にうるおいを与えるだけでなく水を苦手とする害虫の対策にもなります。なお、梅雨などの湿度が高い時期には葉水を控えたほうがよいです。
用土があれば追肥はなくてもOK
先ほどご紹介した植え付け手順のとおり、「赤玉土8:腐葉土2」の割合で混ぜた用土が黒竹の栽培に最適です。また、植え付け時には緩効性の化成肥料を入れておくと、しっかりと生長できるようにサポートしてあげられるでしょう。なお、黒竹に適した用土と元肥を用意していれば、それ以降は追加の肥料(追肥)の必要はありません。
黒竹が枯れる原因3つ
生育旺盛で丈夫な植物である黒竹でも、何らかの原因が起こることにより枯れてしまうことがあります。黒竹を長く楽しむためにも、黒竹が枯れる原因を3つご紹介しましょう。
1.栽培環境に不備があった

もし高齢でもない黒竹が枯れているのが見られたら、今までの栽培環境に不備がなかったか確認をしてみてください。たとえば、以下のような状況で黒竹は枯れてしまうことがあります。
【黒竹が枯れる栽培環境の例】
・鉢植えが小さすぎて根詰まりをしている
・水のやりすぎや水不足
・日当たりが悪い環境である
・密集しすぎて風通しが悪い
また、今の鉢植えに不釣り合いなほど大きく生長したという場合は、黒竹の鉢をひと回り大きなものに植え替えをしていく必要があるでしょう。
2.病気・害虫による被害
黒竹を栽培するときは、病気や害虫被害の対策も十分におこなったほうがよいでしょう。たとえば、黒竹には以下のような病気・害虫が発生する可能性があり、対処が遅れると枯れてしまうおそれがあります。
| 黒竹で気をつけたい病気・害虫例 | |
| 病名 | 害虫名 |
| ・テングス病 ・すす病 ・黒穂病 |
・タケホソクロバ(幼虫) ・ベニカミキリ ・ハダニ |
多くの病気・病害虫は栽培環境が悪い状態、弱っている状態のときに発生することが多いです。黒竹の剪定や水やりなどのタイミングでもよいので、黒竹の葉や棹を見て、病気・害虫が発生していないか定期的に確認するようにしてみてください。また、この中でとくに気をつけたい「テングス病」「タケホソクロバ」についてもう少し詳しく解説します。
・テングス病
テングス病は菌が原因で起こる病気で、細い枝が多く伸びていくのが特徴です。この病気の原因となる菌は、胞子によりほかの枝へ伝染させるため早めの対処をしなければなりません。テングス病が発生した枝を見つけたら、すぐにその部分を取り除くようにしましょう。
・タケホソクロバ(幼虫)
黒い体に羽を持つ蛾の仲間で、幼虫はおもに5~9月ごろに発生し、オレンジ色に近い毛虫のような外見をしています。見つけたら駆除をしておきましょう。ただし、毒針を持っているため手で触らずに道具を使って捕獲するようにしてください。
3.黒竹の寿命が来てしまった
とくにこれといった問題がないにも関わらず、黒竹が枯れてしまったときは寿命が原因で枯れてしまったのかもしれません。一般的な竹の寿命は10年ほどとされています。寿命が来て枯れた黒竹は剪定により間引きして、ほかの若い竹を育てていくとよいでしょう。
また、黒竹の株分けをおこなうことで、新しい黒竹を育てることも可能です。3月ごろの時期を目安に、新芽(タケノコ)から根の部分までを切り取って植え付け、根付くまでしっかりと水やり管理をします。
まとめ
黒竹のきれいな棹や葉を十分に楽しむためには、黒竹の剪定が必要です。黒竹の剪定時期や方法など注意したい点は多いので、この記事の内容をよく確認して慎重に作業をおこなうようにしましょう。なお、黒竹の剪定がむずかしい、黒竹が生育しすぎて自力で剪定ができないといった場合は無理をせずプロの剪定業者に依頼することをおすすめします。
また、黒竹の剪定を代行してもらう業者選びにお困りでしたら、ぜひ弊社にお任せください。弊社ではお客様のご希望に合った、黒竹の剪定業者をご紹介するサービスをしています。24時間365日受付可能なので、必要だと感じたときにすぐ連絡することができます。
【記載情報はコンテンツ作成時の情報です】
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!