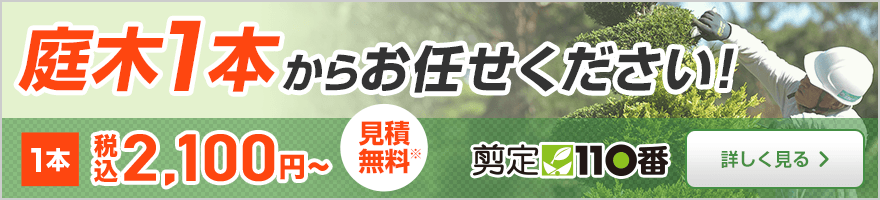クレマチスはツル性の、美しい植物です。とくにその花が見どころですが、剪定方法や時期を間違いやすいため、「花が咲かない!」という事態に陥りやすいです。
じつはクレマチスの剪定は、種類によって方法を変えなければなりません。クレマチスは種類が豊富であるため、種類に合った剪定をおこなわず、失敗をしてしまうケースが多いのです。
このコラムでは、新枝咲き・旧枝咲き・新旧咲きの3タイプの剪定方法をご紹介していきます。またクレマチスの花をたくさん咲かせるために大切な育て方の説明もおこないます。ぜひコラムを参考に、美しい花を咲かせてみてください。
目次
クレマチスの剪定時期は?
クレマチスは品種が多く、その数は100種類にものぼるといわれています。それぞれ花のつき方などに違いがあるため、適切な時期に正しい方法で剪定をおこなわなくてはなりません。そんなクレマチスの剪定時期について確認をしていきましょう。
花後の剪定|春先の剪定
クレマチスの剪定は、年に2回ほどおこないます。その時期は、「花後」と「春先」であることが多いです。花後とは、花が咲き終わった後の時期のことです。花後の時期に剪定をおこなわないと、クレマチスがそのまま種を作ってしまいます。
種を作るには、たくさんの栄養が必要です。そのため貴重な栄養が種にとられて、クレマチス本体が弱ってしまうでしょう。必要なところに栄養をいきわたらせるためにも、花後に花を剪定することが大切になるのです。
また、クレマチスが休眠している春先の剪定も大事です。このときに剪定するツルは、既に枯れてしまっているような不要なものです。これらを残しておくと、ほかのツルの健康と生長を妨害してしまうため、剪定をおこなわなければなりません。

クレマチスの花が咲かない?剪定の注意点
クレマチスは、強剪定をおこなうと、花つきが悪くなってしまうことがあります。強剪定とは、太いツルを根元から切り取ってしまうような、強い剪定のことです。強剪定は花に与えるダメージが大きいため、むやみにおこなうと、クレマチスを傷めつけてしまうでしょう。とくに夏以降の強剪定には注意してください。
またクレマチスが花をつける場所には、法則があります。しかしこの法則は種類によって異なります。そのため、花をつける予定のツルを間違って剪定してしまうと、「いつまで経っても花がつかない……」というトラブルが起きてしまうのです。
次の章で紹介する剪定時期と方法をもとに、クレマチスの種類に合った剪定をおこなうようにしましょう。
クレマチスの剪定方法をタイプ別に解説
クレマチスは、「新枝咲き」「旧枝咲き」「新旧咲き」に分けることができます。新枝咲きは新しく生えたツルに花が咲くタイプ、旧枝咲きは昨年生えたツルに花が咲くタイプ、新旧枝咲きは去年に枯れたツルから新しく伸びたツルと剪定によって新しく伸びたツルの両方に花が咲くタイプです。
育てているクレマチスがどれに当たるのかによって、剪定方法は変わってきます。それぞれについて見ていきましょう。
新枝咲きの剪定|バッサリ切ってOK
新枝咲きは時期を間違えなければ、大きく剪定してしまっても大丈夫です。春先の剪定は2~3月に、生え際から3節程度をカットしましょう。春先に剪定をすることで、新しいツルが伸びるようになります。伸びたツルから、美しい花を咲かせてくれるでしょう。花後の剪定は4~5月に、ツルを半分ほど切り落とすようにおこなってください。

旧枝咲きの剪定|つるの残し方がポイント
旧枝咲きは、モンタナやシルホサによく見られます。昨年に伸びた枝に花を咲かせるため、昨年の枝は残すように剪定をしていきましょう。とくに冬になると枯れたような見た目になるため、たくさん剪定をしたくなってしまいますが、じつは生きているということがあります。枯れたと勘違いをしてクレマチスを剪定をすると、翌年の花が咲かなくなるため、気をつけましょう。
剪定は4~5月頃に、ツルを切り戻すようにしておこないます。切り戻す位置は、花から1~2節ほど下にするとよいでしょう。
新旧枝咲きの剪定|花後の剪定を忘れずに!
フロリダやアトラゲネに多いのが、こちらの新旧枝咲きです。春先の2~3月と花後の5~8月に1回ずつ剪定をおこないましょう。5~8月の剪定は、花が8割ほど咲き終わったころに、新芽の出ていないツルを剪定します。春先と花後の剪定は、花から1節ほど下のところをカットするようにおこないます。
また、花後の剪定は忘れずおこなうようにしましょう。もし忘れてしまえば、翌年花が咲かなくなってしまうことがあります。花を咲かせたい方は、とくに注意をしておきましょう。
クレマチスの育て方とつるの誘引方法
適切にクレマチスの剪定をおこなうことで、美しい花を観賞することができるようになります。
しかし、適切な育て方をおこなわなくては、花が咲く前に枯れてしまうことも考えられます。美しい花を咲かせるためにも、育て方についても知っていきましょう。
水やり、肥料、日当たりの管理
クレマチスは水やりをしっかりとおこなう必要があります。しかし、この水やりは多すぎても少なすぎても枯れさせてしまいます。適切な水やりの頻度を心がけるようにしましょう。水やりの頻度は、「庭植えか鉢植えか」という点と、「季節はいつか」という点が大切です。
まず、ご自宅のクレマチスが庭植えであれば、基本的に水やりをおこなう必要はありません。自然に降る雨が水やりを代わりにおこなってくれるからです。ただし、クレマチスが根付いていないような時期や、夏で水分が足りなくなりやすい日は、水やりをおこなう必要があります。
また鉢植えで育てている場合は、夏は基本的に1日に2回、それ以外の季節は頃合いを見ておこなうようにしましょう。水やりをおこなう頃合いは、「土の表面が乾燥しているとき」です。鉢植えの底から水が漏れてくるまで、たっぷりあげるようにしましょう。
また肥料は、真夏を除く春から秋にかけて定期的にあげると、クレマチスが元気に育ちます。月に2回ほど液体肥料をさし、隔月ごとに、緩効性の化学肥料をあげるとよいでしょう。

病気と害虫対策
クレマチスは残念ながら、いろんな病害虫の被害にあってしまいます。かかる病気は、たとえばうどん粉病があげられます。
この病気はクレマチスだけでなく、ほかの植物も被害にあうことが多いため、非常に有名な病気でしょう。うどん粉病とは、葉の表面がうどん粉のように白っぽくなってしまう病気です。
白っぽくなる原因はカビによるもので、放っておくと木が枯れてしまいます。残念ながら、白っぽくなってしまった葉を治すことはできません。病気にかかってしまった部分は剪定してしまいましょう。
また、さび病にかかることもあります。さび病は、クレマチスの葉や茎を変形させる病気です。この病気にかかると、最初に斑点が表れて見えるので、定期的に確認するとよいでしょう。もしさび病を放置してしまえば、クレマチスが枯れてしまうこともあります。さび病にかかっている部分はちぎって取り除くようにしましょう。
ほかにも、白絹病という病気にかかることもあります。クレマチスに白い糸が覆うような形で発症します。この白い糸は、白絹病を引き起こす病原菌が出す糸でできています。こちらも残念ながら、治すことはできません。白絹病にかかってしまった部分は取り除くようにしましょう。
害虫であれば、アブラムシによる被害が多いです。アブラムシは緑色の小さな虫で、放置しておくと葉の栄養を吸い取り、枯らしてしまいます。繁殖力も強く、排せつ物は病気を引き起こす原因になるため、殺虫スプレーや木酢液を散布して駆除しましょう。
またモンシロチョウの幼虫であるアオムシも、クレマチスに棲みつくことがあります。こちらは食害をおよぼすので、クレマチスの景観を楽しみたい方には対策をするべきでしょう。捕獲することで、被害を防ぐことができます。
こうした病害虫は、剪定をおこなうことで、予防ができます。剪定は風通しがよくなるため、枝葉の間が蒸れにくくなります。病害虫は蒸れが原因で繁殖を起こすので、剪定をすることは病気の予防にもつながるのです。
鉢植えは定期的に植え替えを
クレマチスは育てていると、鉢が根でいっぱいになってしまいます。その状態のまま置いておくと、根が詰まって不健康になってしまいます。そのため、根が詰まってきたと感じたら植え替えをおこないましょう。
植え替えをするには、新しい鉢と土、軽石と赤玉土を用意しましょう。まずは新しい鉢の底に軽石と赤玉土を詰め、その上を土で満たしていきます。半分ほど土で埋めたら、クレマチスをかぶせて、再び土を盛っていきます。クレマチスは根が傷つきやすいため、極力ダメージを与えないようにおこなうようにしましょう。
クレマチスのつるの誘引方法
クレマチスはツル性の植物なので、放っておくと、つるがさまざまな方向へ伸びていってしまいます。そのためつるが育ってきたら、誘引をしてあげましょう。
誘引をするには、支柱やフェンス、ロープなどを用意しましょう。用意をしたらつるを支柱やフェンスにまきつけていきます。このときにロープで固定をすることで、思い通りの形に誘引することができます。またどのように誘引をしていくかは、自由です。お好みの形に結び付けていきましょう。
誘引をおこなうことで、見栄えがよくなることはもちろん、風通しがよくなるため病害虫にかかることも防ぐ効果があります。クレマチスの健康のためにも、誘引はおこなうようにしましょう。
繊細なクレマチスで切り花を楽しむコツ
クレマチスを剪定して、美しい花を咲かせることができたのであれば、活用したいものですよね。クレマチスの花は、切り花にして楽しむことができます。
クレマチスを切り花にしようと考えている方は、コツをおさえておきましょう。コツをおさえずに切り花にしてしまうと、美しい見た目を長期間保つどころか、切り花にすることも難しくなってしまいます。そのため、クレマチスを切り花として活用したい方は、コツを知っていきましょう。
丁重に扱う
クレマチスの茎は非常に細いため、丁重に扱わなければ折れてしまうことがあります。しかし茎ではなく花付近を持つと、花がこぼれてしまうため、注意が必要です。クレマチスは茎を折らないよう、丁寧に持つようにしましょう。
切り口は毎日作る
切り花にした花は、水分が非常に大切です。水分が花に行き渡るような工夫をおこなわなければ、水不足で花は枯れてしまいます。しかし、切り花にした花は、切り口が古くなると水を吸収する力が弱まるため、葉から多くの水分が蒸発してしまい、水不足で枯れてしまうことが多いのです。
そのため、毎日クレマチスの茎をカットして、切り口を新しくするように心がけましょう。切り口を新しくすることでたくさんの水分を吸収するようになり、水不足になりにくくなるのです。
切り口は水中で作る
切り口を作るときは、水中で作業をするようにしましょう。水中で作業をせずに切り口を作ると、カットをしたときに空気が導管へ入ってしまいます。
空気が入ることで、水が上手に葉や花へ届かなくなることがあるのです。水不足になってしまえばクレマチスは枯れてしまうので、切り口は水中で作るようにしましょう。
不要な葉を取り除いておく
もし不要な葉を残した状態で活用すると、水分が不要な葉にまでわたってしまいます。そうすると、目立たせたい花や葉に水分がいきわたりません。そのため少々もったいないですが、不要な部分はカットしてしまいましょう。

まとめ
クレマチスは、「新枝咲き」「旧枝咲き」「新旧枝咲き」の3つに分けることができます。それぞれ剪定時期や方法が異なるため、間違えてしまわないように注意をしましょう。
またせっかく適切な剪定をおこなっても、育て方が正しくないと枯らしてしまうことがあります。クレマチスは剪定も育て方にも気を配らなければならないことを覚えておきましょう。
もし不安がある方は、業者へ剪定を依頼するのもよいかもしれません。業者であれば、これまで培ったノウハウを生かして、剪定をしてくれることでしょう。
「業者を利用したいけど、どの業者を利用すればよいのか分からない」というときは、弊社をご利用ください。ぴったりの業者をご紹介いたします。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!