
鮮やかでかわいらしい金柑は昔からのどによいとされていて、のど飴でもおなじみのビタミンが豊富な果物です。
そして、金柑を庭木として育てるのを楽しみながら、新鮮な自家製の金柑を収穫して食卓でも楽しみたい方も多いのではないでしょうか。頑張って育てていても、実が付かなかったり、付いた実が落ちてしまったりすると、残念な気持ちになってしまいますね。
せっかく金柑を育てるなら、甘くて大きな実を育ててたくさん収穫したいものです。金柑は日光を好む植物なので、適切な剪定をおこなうことで日当たりがよくなり元気に育ちます。栄養たっぷりで元気に育てば、収穫も期待できます。
これから、自分で金柑を剪定するときのコツや上手に栽培する肥料の選び方・与え方をご説明します。適切な金柑の剪定方法を習得して、おいしい金柑をたくさん収穫しましょう。
- 樹齢や季節に合わせて、肥料を与えたりや定期的な剪定をする時間がない
- 実を付けるようになるまで3~5年かかるので、それまでの手入れが面倒
- 肥料の与え方や剪定方法を試行錯誤したけれど、毎年あまり実がならない
このようなときは、プロに依頼して金柑の剪定をしてもらうのもひとつの選択肢です。金柑の剪定は、最初が肝心なので丈夫に育てば軽く剪定するのみで済みます。
また、今まで試行錯誤しても金柑の実がなりにくい場合は、プロなら原因を見つけて改善策を提案してくれるはずです。
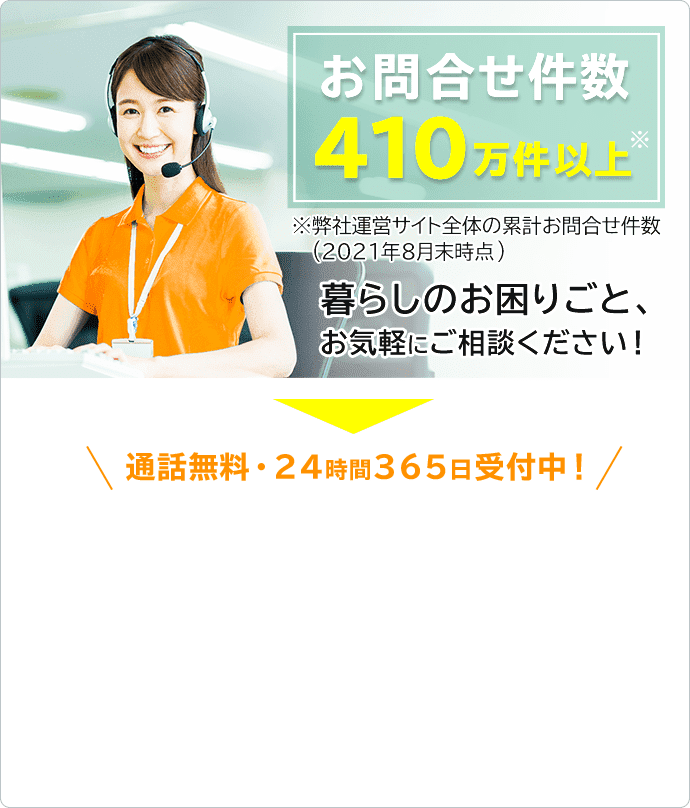
目次
病気・害虫予防にもなる金柑の剪定時期と方法
金柑を上手に育てるためには、適度な剪定が必要です。また、植えてから実をつけるまでに3年から5年ほどかかるようです。育てる段階によって金柑の剪定方法が変化していくので、参考にしてみてください。
植え付け時

金柑の植え付けは、3月下旬から4月半ばごろにおこなうのがよいそうです。あまり大きくならない品種なので、地面に直接植えるほか、鉢植えでも育てることが出来ます。水はけがよく、日当たりのよい場所に植えるようにしましょう。
植え付けるときには50cmくらいの穴を掘り、しっかりと根をほぐしておきましょう。また、植え付けの際、金柑の剪定は40cmから50cmの高さで切るようにします。
翌年の春ごろ
金柑を植えた翌年の春ごろになると、植え付けたときに切り戻した箇所から新しい枝がのびているはずです。新しい枝は3分の2くらいの長さになるよう、剪定しておきましょう。このように切り戻しをおこなうことで、枝の成長を促します。
2年目の春ごろ
前回の剪定からの1年間で、さらに枝がのびている時期です。前年と同様に、新しくのびた枝を3分の2程度の長さに切り詰めます。
また、細い枝や木の内側に向かって生えてきた枝があれば、根元から切っておくとよいでしょう。育てたい枝に日光と栄養がいきわたるよう、不要な枝は切っておくのがポイントです。
3年目以降の春ごろ
今回も1年間でのびた枝を3分の2くらい残して剪定します。また、2年目と同じように、不要な細い枝も切っておきましょう。特に、混みあって成長している箇所は、根元からしっかり剪定することで、木の内側までたっぷり日光が届くようになります。金柑は日当たりがよい環境を好むので、剪定をするときの参考にしてくださいね。
成長の早い金柑は、植えてから3年目までに実をつける場合もあります。しかし、この段階では樹形を作るためにしっかりと剪定をおこなう時期なので、実がついたら早めに切るほうがよいとされています。せっかくついた実を切ってしまうのはもったいない気がしますが、翌年以降においしい実をたくさん収穫するために覚えておきたいポイントです。
手入れの剪定で注意するべきポイント
金柑は夏ごろに開花したあと実が育ち、2月ごろに収穫時期を迎えます。剪定は2月ごろの実がなっているタイミングでおこないましょう。金柑の剪定は、混みあっている枝を切る程度で十分です。
先にも紹介したように、金柑は日光を好む植物です。そのため、剪定を適度におこない日当たりをよく保つことが大切です。しかし、剪定を強くやりすぎると育ちが悪くなったり、実が十分に収穫できなかったりするので注意が必要です。

金柑は3年目までに強めの剪定をおこない、樹形を整えます。そのため、実が収穫できるようになった後は、あまり強い剪定はおこなわずに形を整えたり、混みあう枝を間引いたりする程度にとどめましょう。
また、太い枝を剪定した場合は、切り口から病気の原因となる害虫やウイルスなどがついてしまうおそれがあります。金柑を病気から守るため、剪定した箇所に殺菌剤などを塗るようにしてください。
枝を切る場所がわからなかったり、切りすぎたりする不安がある場合は、業者に頼んで金柑を剪定してもらうのもよいかもしれません。上手に業者を活用してみてくださいね。
庭木や鉢植えの金柑を元気に栽培するポイント
金柑をたくさん収穫するためには、普段から手入れをする必要があります。元気な金柑を育てる方法をまとめて紹介します。金柑の剪定とあわせて、栽培する際の参考にしてみてください。
金柑の水やり
金柑は水はけのよい場所に植えるとよい植物です。庭に直接植えた場合は、基本的には水やりは必要ありません。もし夏場に雨が少なく日照りが続くような場合は、水をあげるとよいでしょう。鉢植えで育てている場合は、土の表面が乾いてきたらしっかり水をあげましょう。

金柑の肥料
金柑は木の大きさに対して多くの実をつける植物なので、栄養がたくさん必要になってきます。庭植えの場合は2月と10月の2回、鉢植えの場合は2月、5月、10月の3回肥料を与えましょう。
2月~3月ごろは、金柑が休眠から目覚める時期なので、養分を必要としています。新しい芽や動き始めた根に栄養を与えるのが目的です。
5月~6月ごろは金柑が花をつける時期にさしかかり、さらに栄養が必要になってきます。庭植えの場合、夏肥は与えないことが多いようですが、鉢植えの金柑にはあげたほうがよさそうです。
秋は開花時期が終わり、収穫期の2月に向けて実が育っていく時期になります。この時期にあたる10月ごろには、実や来年咲く花芽の成長を助ける目的で肥料を与えます。
しかし、金柑を元気に育てたいからといって、肥料を与えすぎてはいけません。肥料をあげすぎると、かえって実がつきにくくなったり、木が枯れてしまったりすることもあるそうです。ちょうどいい量の肥料の与え方がわからない人は、金柑の栽培について業者に相談してみてはいかがでしょうか。
金柑の病気や害虫
金柑は比較的丈夫な植物です。しかし、病気になったり、虫が寄ってきたりして枯れてしまうこともあります。
特に気をつけなければならないのが、アゲハチョウの幼虫です。アゲハチョウの幼虫は金柑の葉が大好きなので、食い荒らされてしまうことも珍しくありません。もし見かけたら、早めに取り除くようにしましょう。ほかにも、アブラムシやカミキリムシ、カイガラムシなども金柑を好んで寄ってくるようです。
また、枝の切り口から菌が入って潰瘍病という病気にかかるケースもあります。切り口から菌やウイルスが入らないように薬を塗っておくと安心です。
美味しい金柑の実の収穫の仕方
金柑はたくさん実をつけるので、必要に応じて間引きをおこなうとよいでしょう。小さな実は9月から10月ごろの色づき始める前の段階で摘んでおくとよいそうです。目安として1本の枝に1つか2つ程度の実がつくようにします。

1月から2月にかけて金柑は、収穫の時期を迎えます。黄色から鮮やかな山吹色に変わってきたころが食べごろです。金柑の剪定は実の収穫と同じ時期におこなうため、間違えて収穫前の実を落としてしまわないように気をつけましょう。
金柑の収穫シーズンは、1年で最も寒い時期になります。金柑の木は寒さには強いほうですが、霜がおりる場合などは実がいたみやすくなるので注意が必要です。また、ほかの果実が少ない季節でもあるため、鳥が実を食べにくることもあります。霜よけの袋やネットなどをかけて収穫前の金柑を守るようにしましょう。
まとめ
金柑は一度にたくさんの実が取れるので、食べる楽しみがあります。コツをつかめば家でも栽培することが十分可能なので、この機会に自宅で金柑を育ててみてはいかがでしょうか。また、自宅に金柑の木がある方にも参考になれば幸いです。
はじめのうちは樹形を作るために剪定が必要なので、実をつけるようになるまでには少し時間がかかってしまいます。金柑の剪定に不安がある場合は、業者に相談すると解決するかもしれません。業者を上手に活用して、より多くの金柑を収穫してみてくださいね。
\ 完全無料 /
厳選した全国の剪定業者を探せます!
×
関連記事カテゴリ一覧
剪定の記事アクセスランキング
剪定の最新記事
カテゴリ別記事⼀覧
- お庭の手入れ
- 害虫駆除
- 害獣駆除
- 電気工事
- 鍵開け・交換・修理
- 窓ガラス修理・ドアノブ修理
- 家の修理
- バッテリー上がり
- ハウスクリーニング
- ペット火葬・葬儀
- 家電修理
- パソコン修理・ネット回線
- 家具・雑貨の修理
- 外壁・屋根工事
- リフォーム
- 防犯カメラ設置
- 盗聴器・その他調査診断
- 便利屋・代行サービス
- 引越し・配送サービス
- オフィス・店舗向けサービス
- その他










