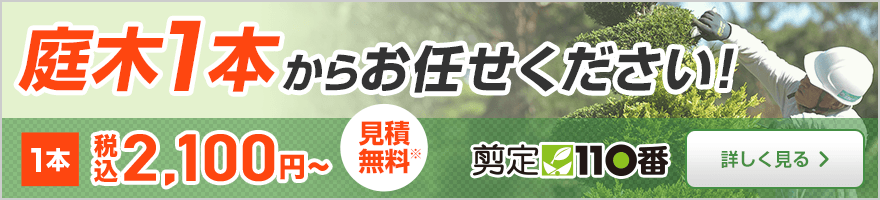紫陽花は、初夏になると立体的でとてもきれいな花を咲かせます。色もピンクに近い紫色や水色などがあり、たくさん育てているときれいなグラデーションが目を楽しませてくれます。
そんな紫陽花は、じつは育て方にはコツが必要です。とくに日当たりや水やりなどに気をつけていないと弱ってしまうので、知らずに枯らしてしまったという方も多いことでしょう。
このコラムでは、紫陽花が枯れる原因を紹介するとともに、元気がない紫陽花を復活させる方法についても解説していきます。もしかしたら、一度は枯れた紫陽花を、復活させられるかもしれません。
目次
紫陽花が枯れるおもな原因4つ
紫陽花が枯れる場合、いくつかの原因が考えられます。それでは、早速その原因と対策方法について確認していきましょう。
原因①水の量が合っていない
紫陽花は乾燥を苦手とする植物なので、水やりが適切でないと枯れてしまうことが多いです。庭植えの紫陽花は、降雨だけでも育てることができるといわれていますが、乾燥が激しい真夏などには追加で水やりをしてあげましょう。

一方、紫陽花を鉢で育てる場合は、より一層注意が必要です。鉢植えの場合は、春から夏にかけては土が乾いたタイミングで水やりをします。7月から9月ごろにかけてはとくに暑く、乾燥も進みやすいので1日2回、たっぷりと水をあげましょう。
乾燥しやすい時期には、腰水(こしみず)という方法で水不足を防ぐことも可能です。腰水とは、朝の水やりのときに鉢の受け皿に2cm程度の水をためておき、夕方に捨てるというものです。ただし、水が入ったまま放置していると根腐れしてしまうことがあるので、昼間だけ腰水を設置するように管理しましょう。
原因②日当たりがよすぎる
紫陽花は、日が当たりすぎると弱ってしまうことがあります。成長するために適度な日の光は必要となりますが、真夏の直射日光のような強い日差しにさらされると、乾燥の原因ともなり葉が焼けてしまうのです。
とくに紫陽花は西日が苦手なので、庭植えの場合は植え替えをするか、すだれなどで西日を遮るとよいでしょう。鉢植えで育てている場合は、半日陰で西日が当たりにくい場所に移動することをおすすめします。
原因③鉢が小さすぎる
花に対して鉢が小さすぎると、土の保水力が足らず、根に十分な水分が行き渡りません。また、紫陽花が大きくなるにつれて地中にある根も成長するため、根詰まりもしやすくなってしまいます。
そこで、紫陽花が大きくなってきたら、1回り大きな鉢に植え替えをおこなうことがポイントです。大きな鉢にすると土が増えるので、保水力も高くなり、水不足になりにくいでしょう。
原因④植え替える時期を間違えた
紫陽花の植え替えは、開花後の7月終わりごろから9月ごろまで、もしくは、11月~2月ごろの休眠しているタイミングがよいとされています。咲き始めは、株の栄養が花に集中しているため、植え替えには適していないのです。
落葉期を「枯れた」と勘違いしている場合も
紫陽花は冬になると葉を落とし、休眠シーズンに入ります。そのため、晩秋から春にかけての紫陽花は茶色く変色して、枯れたような見た目になるのです。
このような状態になると枯れたのではないかと心配になるかもしれませんが、春にきれいな緑色の葉が出てきたらきちんと育っているので、安心して栽培していきましょう。
枯れた紫陽花が復活することもある
水やりに関していくら気をつけて育てていても、天候や乾燥などによっては、紫陽花が枯れることがないとはいいきれません。すでにご家庭の紫陽花が枯れてしまっているという方も、たくさんいることでしょう。
しかし、その枯れた紫陽花を復活させられる場合があります。鉢植えの紫陽花が水不足でしおれてしまった場合や元気がないときには、以下の方法をぜひ試してみてください。
①鉢が入る大きさのたらいや桶などに水を入れる
②紫陽花の鉢を水の中に漬け込む
③日陰で涼しい場所に数時間~半日くらい置いておく
水不足が原因で紫陽花が枯れかけている場合には、普通に水やりをするだけでは足りません。そのため、鉢ごと水につけてしっかりと根に水を吸収させます。そうすることで、弱った紫陽花でも復活することがあるのです。

ただし、根腐れや病害虫など、別の原因で紫陽花が枯れてしまっていることもあります。弱っている原因が水不足以外にある場合は、この方法をもってしても復活しないため注意が必要です。
紫陽花を枯らさないために病気や害虫にも注意
紫陽花を育てるうえでも、ほかの植物と同様に病気や害虫に気をつけなければなりません。それでは、紫陽花を枯らせる原因には、主にどのようなものがあるのでしょうか。

たんそ病
黒っぽい褐色の斑点が葉に広がります。進行すると葉に穴があいて、紫陽花が枯れる原因になります。症状が出ている葉はすぐに取り除き、薬剤をまいておきましょう。
うどんこ病
うどんこ病の見た目は、白い粉がかかったようになります。この病気になると光合成がしづらくなるため、紫陽花の成長の妨げにもつながります。うどんこ病を防ぐためには、事前に薬剤を使用したり剪定で風通しをよくしたりといった対策が必要です。
ハダニ
ハダニがつくと葉の汁を吸われ、植物は枯れてしまいます。この害虫は葉の裏側に発生しやすく水が苦手なため、葉の裏にしっかりと水をかけると予防につながるようです。
ほかにも、黒点病やカミキリムシの幼虫などの被害もあります。日ごろからこまめに観察して、異変がないかチェックしましょう。原因がなんなのかわからない、もしくは病気なのかどうかもわからないといった場合は、業者に相談するのもよいかもしれません。
枯れていないはずなのに花が咲かないなら剪定の見直しを
剪定は紫陽花の樹形を整えるだけでなく、翌年の花付きや風通しをよくするためにも大切な作業です。しかし、やり方を間違えると花が咲きにくくなってしまうこともあります。
夏の剪定のやり方
紫陽花は8月から10月ごろにかけて、新しい花芽をつけます。そのため、7月中に夏の剪定を終わらせることがポイントです。剪定する際は、花の下で切り戻しをおこないます。切る長さは上から2節くらいが目安です。
7月だとまだ花が残っていて、剪定するのがもったいないと感じるかもしれません。しかし、剪定が遅くなると花芽を切ることになってしまい、翌年の花つきが悪くなってしまいます。紫陽花は花が散らない品種が多いので、まだ鑑賞できる花を剪定したときは切り花として活用してみてはいかがでしょうか。
また、古い枝については思い切って3分の1程度の長さに切りつめます。古い枝を切ることで新しい枝が生えてくるので、若い枝に更新することができます。古い枝は次第に花付きが悪くなっていくので、定期的にチェックすることをおすすめします。

冬の剪定のやり方
冬は、紫陽花が休眠する時期です。このとき、枯れた枝や密集している枝を整理するために剪定をおこなうとよいでしょう。
基本的には、白っぽくなって枯れている枝をカットします。ただし、紫陽花の見た目は冬になると枯れているようにも見えるので、生きている枝についている花芽を切らないように注意が必要です。
ほかには、混みあっている枝を間引き剪定していきます。枝が密集していると通気性が悪くなり、病害虫が発生しやすくなってしまいます。古い枝や細い枝などを切って、すっきりさせておくと、紫陽花が枯れるリスクを防ぐことにもつながります。
まとめ
紫陽花が枯れる原因には、さまざまなものが考えられます。そのため、水分量や日当たり、鉢のサイズなどを工夫することで、枯らさずに育てることができます。

紫陽花には病気や害虫がついて枯れてしまうこともありますが、よく観察して異変に対処すれば長く育てていくことも可能です。定期的に剪定をして風通しのよい環境を作り、事前にトラブルを回避していきましょう。
紫陽花の手入れに不安がある場合や紫陽花の元気がなくて心配なときには、業者に相談してみてはいかがでしょうか。自宅の紫陽花にぴったりの対処法を見つけて、適切な処置が施せるかもしれませんよ。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!