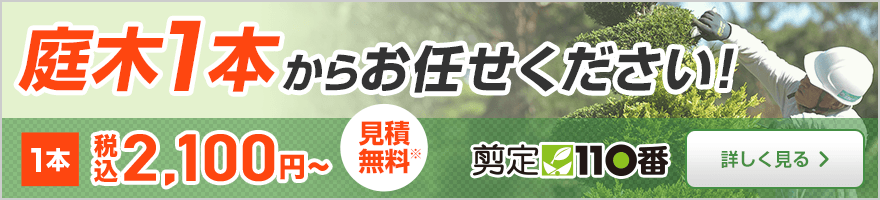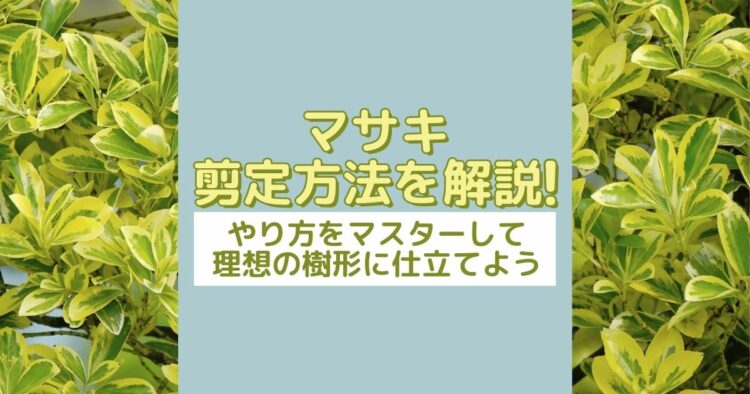
マサキの剪定は年に2回おこなうのが理想です。なぜならマサキは生長スピードが早いので、定期的に剪定しないと樹形を大きく乱したり、風通しが悪くなって病気にかかりやすくなったりするからです。また、マサキをどんな樹形に仕立てたいかによっても、剪定方法はちがってきます。
この記事で紹介する剪定のやり方を参考にマサキを剪定し、理想のイメージに育てあげましょう。
目次
マサキの剪定時期
マサキの剪定時期を、生垣の場合と、1本で育てる場合とにわけてご紹介していきます。

生垣の場合
生垣としてマサキ育てている場合、1回目は初夏(梅雨前となる5月~6月)に行い、2回目は秋口(9月~10月)におこなうとよいとされています。
梅雨前に剪定をおこなう大きな目的は、病害虫を予防するためです。梅雨の時期は枝や葉が重なり合いすぎてしまうと病害虫が発生する確率が高くなるため、剪定がとくに重要となります。そのため、梅雨前に余分な枝を切って枝や葉の隙間を確保し、病害虫の発生しにくい環境にしておくのです。
さらに、秋口に2回目の剪定をおこなうことによって、やがて小枝が枝わかれをしていきます。剪定直後は生垣の内側がスカスカした印象となっているかもしれませんが、枝わかれによって内側の枝葉が充実していくでしょう。
1本で育てる場合
生垣ではなく1本の自然樹形に育てる場合は、真夏以外の季節ならいつでも剪定しても大きな影響はないといわれています。夏を避ける理由は、マサキは夏に剪定すると葉が日焼けしてしまうおそれがあるためです。マサキを剪定する際には、真夏を避けておこないましょう。
マサキの剪定方法・注意点
つぎは、マサキの剪定方法を解説していきます。今回はおもな剪定方法を3種類ご紹介するので、マサキをどう仕立てたいかを考えながら方法を選択してください。

剪定に向けて用意する道具
マサキを剪定するにはまず、道具をそろえます。剪定するときに便利なハサミとしてあげられるのは、植木バサミ、剪定バサミ、刈り込みバサミなどです。また、太く硬い枝を切るときには、剪定ノコギリを使用することもあります。
さらに、マサキの高さによっては脚立を使用することがあり、剪定をおこなうときは、園芸用手袋や軍手を着用するとより安全に作業ができるといわれています。
・植木バサミ……細い枝を切るハサミ
・剪定バサミ……植木バサミで切るのが難しい、太めの枝を切るハサミ
・太枝切りバサミ……剪定バサミで切るのが難しい、さらに太い枝を切るハサミ
・刈り込みバサミ……生垣などの刈り込みに使うハサミ
・電動バリカン……生垣の体積が広い場合にあると便利
・脚立またはハシゴ……手が届かない高い部分を剪定する際に使う
・軍手……枝や葉から手を守るため
・掃除道具……竹ぼうき、熊手、ビニール袋など、切った枝葉を掃除する際に使う
このような剪定に使う道具は、基本的にはホームセンターや園芸の通販サイトなどで購入することができます。
剪定方法1:透かし剪定
透かし剪定は、マサキを1本の自然樹形に育てる場合の基本的な剪定方法です。透かし剪定では、込み合っている枝や成長のさまたげとなる不要な枝を切り、風通しや日当たりを改善することがおもな目的となります。
剪定のやり方としては、まず枝が混み入っている部分を切っていくいことからはじめます。枝を切る際には、根元から切ってください。すっきりと風通しをよくさせることで、衛生的な形づくりがおこなえるでしょう。
混み入っている部分の剪定ができたら、つぎは下記のような不要な枝を根本から切っていきます。
・上に向かってまっすぐ伸びている枝
・真上にいきおいよく伸びる枝
・ほかの枝と交差したり、からみあったりしている枝
・幹に向かって伸びる枝
これらの枝は、栄養を奪ってしまう要因になるため、一緒に切ってしまいましょう。そして、長くのびすぎた枝を切ってマサキ全体の形を整えて、完成です。
剪定方法2:刈り込み剪定
刈り込み剪定は、生垣やトピアリー(動物や図形の形に仕立てること)の樹形をつくるために枝葉を切りそろえる剪定方法です。
刈り込み剪定は、下から上の順番に剪定していくと失敗しにくいです。その理由は、木は上のほうと下のほうでは生長する力に差があるからです。
そのため、刈り込み剪定では剪定後の生長を考えると、下のほうはあまり刈り込みすぎないよう注意する必要があります。刈り込み剪定は、側面、上面の順番でおこないましょう。
そして、刈り込み剪定ができたら、内部の枝を透いて日当たりや風通しをよくしていきます。枯れている枝や交差している枝などを適度に切って完了です。
剪定方法3:切り戻し剪定
切り戻し剪定は、1本の自然樹形に育てる場合でも、生垣として育てる場合でもおこなわれることがある剪定方法です。
大きな樹形を小さくしたり、樹形を小さくたもち続けたりすることが切り戻し剪定のおもな目的です。また、切り戻しをしたあとには新しい枝が生長しやすいことから、生長促進の目的でおこなわれることもあります。
切り戻し剪定では、樹形が小さくなるよう全体的に枝を短く切っていきます。枝を切る際には、枝の中央あたり、または枝の根本から3分の1あたりの場所で切ってください。
また、切り戻し剪定の際には、さらに剪定方法1:透かし剪定でご紹介したような不要な枝があれば根本から切っておくとよいでしょう。
マサキを剪定するときの注意点
マサキを剪定する際に気をつけていただきたいポイントを4つお伝えします。

【ポイント1:病気や害虫を確認しながら剪定する】
マサキを剪定する際には、病気や害虫が発生していないか確認しながらおこないましょう。のちほど注意すべき病害虫で詳しくご紹介しますが、マサキが被害にあいやすい病気や害虫は何種類か存在します。
病害虫の発生を見逃してしまうと、適切に対応できず被害が周囲に広がり、最終的に木全体を枯らしてしまうことも考えられます。もし、マサキ全体が枯れてしまった場合には木を伐採することも考えらえるため、病害虫はできるだけ範囲が小さいときに見つけましょう。
【ポイント2:清潔な剪定道具を使う】
剪定をおこなうときは、使う道具に気を配ることが大切です。ハサミは、清潔なハサミを使用することがよいとされています。ハサミの刃に細菌がついたまま剪定をおこなうと枝や葉に細菌がついてしまうこともあるため、剪定終了後はハサミの手入れを必ずおこないましょう。
使用しているハサミの種類により手入れ方法が異なるため、取り扱い説明書をしっかりと読むことが大切です。たとえば、ハサミを購入するときに店舗において、自分で手入れが可能であるかを確認するとよいでしょう。
【ポイント3:剪定後の樹形をイメージする】
剪定の際には、自然体な樹形や理想とする樹形になるようにイメージしながらおこなうことをおすすめします。もし具体的なイメージを持たずに剪定をしてしまえば、形が悪くなってしまうかもしれません。
イメージがわかない場合は、学校などの人の手が加わっている木を参考にすることも方法の1つです。しかし、どの枝をどのようにして切ってよいのか、自身では判断が難しいことがある場合、業者に依頼されることをおすすめします。
【ポイント4:剪定時の安全を確保する】
マサキは、大きいもので樹高が6mほどにもなる庭木です。そのような樹高の高いマサキを剪定する際には、高所作業となるため危険がともないます。しっかりと安全対策をとったうえで剪定してください。
樹高が高い木を剪定するのが不安な方は、剪定業者に依頼するという選択肢もあるので、検討してみるのもよいでしょう。
マサキの育てかた
剪定のつぎは、マサキの育て方についてご紹介してきます。何年もマサキを育ててきた方も、ぜひ参考にしてみてください。
また、「マサキが枯れる」「葉っぱが落ちる」などのトラブルが発生した場合も、育て方を見直すことでその原因を見つけるヒントとなるかもしれません。
基本情報
マサキは日本や東アジア原産の樹木であるため、日本の環境で育てやすいといわれています。萌芽力が強く、乾燥や塩害にも強いので、お手入れが比較的簡単な庭木だといえるでしょう。また、マサキは常緑樹といって1年中緑の葉をつけるため、生垣としてよく採用されることが多いです。
そんな庭木として人気の高いマサキですが、じつは、常緑の葉をつける「マサキ」以外にもいくつか種類があるのです。人気の高い種類を4つご紹介します。
・キンマサキ
深い緑色の葉に、金色のように鮮やかな黄色の模様があらわれます。
・ギンマサキ
葉の内側は落ち着いた印象を持つ緑色で、葉の外側は白色で縁どられています。
・ベッコウマサキ
葉の内側は落ち着いた印象を持つ緑色で、葉の外側は黄色で縁どられています。
・オウゴンマサキ
新芽は黄金のように鮮やかな黄色で、だんだんと緑色になっていきます。
育てる環境
半日陰でも育つことはできますが、日当たりがよい場所のほうが育ちやすいです。土壌については、乾燥にも湿度にもある程度対応できますが、基本的には水はけのよい土壌を好みます。
水・肥料やり
庭植えの場合、植え付けから1年以内は土が乾燥しないよう水やりをします。植え付けから1年たったら、基本的には自然に降る雨で生長します。鉢植えの場合は、土が乾燥しないよう水やりを続けてください。
肥料については、植え付けや植え替えの際には下のほうに有機質肥料まぜた土を敷いておくとよいです。その後は、2月ごろに有機質肥料を株本に与えるだけで育つでしょう。
注意すべき病害虫
マサキは剪定を怠ると、病気や害虫の被害にあいやすくなってしまいます。剪定は、木の見栄えをよくするほかにも、健康がよくなるという役割があるのです。
剪定によって密になっている葉や枝を切ることで風通しがよくなり、衛生的にすることができます。そのため、剪定は植物の健康には欠かせない作業だといえるのです。マサキを育てるうえで注意したほうがよい病気や害虫をご紹介します。
【病気】うどんこ病
もしマサキの剪定をおこなってしまったときは、うどんこ病という病気にかかってしまうことが考えられます。
うどんこ病の原因は糸状菌というカビの一種とされ、乾燥しているときに発生しやすいといわれています。マサキの葉が白色になっているときが発生しているサインといえるでしょう。うどんこ病は、初夏や秋口といった気温がやや高いときに発生することが多いとされています。
うどんこ病をそのままにしておくとほかの葉に広がっていくこともあるため、周囲に落ちている葉っぱも拾いましょう。予防策として葉や枝が重なり合わないようにすることや患部の葉っぱをすぐに切ることなどがあります。
うどんこ病にかかった場合、樹木用の殺菌剤をまきます。薬剤によっては、発生初期段階に効果を大いに発揮するものや範囲が広いとき用のものがあるため、状況にあった殺菌剤を選びましょう。
【害虫】ミノウスバ、ツノロウムシ、ユウマダラエダシャク
ミノウスバの幼虫は、マサキの葉を好んで食べるので、ほうっておくとどんどん葉が食いつくされてしまいます。ミノウスバの幼虫は体に縦のラインがはいっているのが特徴です。
ユウマダラエダシャクの幼虫も、マサキの葉を食べつくしてしまう害虫です。ユウマダラエダシャクの幼虫は、全体は黒色で、ところどころ黄色の斑点がはいっています。
ツノロウムシについてはは体を白い貝殻のようなものでおおっているのが特徴です。マサキの樹液を吸って育つため、発生すると枝葉が枯れてしまったり、さらに被害が拡大するとその排泄物によってすす病になってしまったりすることもあります。
このような害虫を見つけたら、早めに害虫を取り除いて殺虫剤を散布するようにしてください。そして、このような害虫が発生する前に予防として薬剤を散布しておくとよいです。
また、病気や害虫の被害をあわないようにするためには、定期的な剪定も効果が期待できます。忙しくて剪定できないときは、業者に依頼してみるのもよいでしょう。
マサキの増やし方

マサキは挿し木という方法で木を増やすことができます。「マサキをもう1本育ててみたい」「生垣を広げたい」とい方は、挿し木にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
1.6月ごろ、その年に伸びた新しい枝を10cm~20cmほど切ります。
2.切った枝を1時間ほど水につけます。
3.小さい鉢に湿った縁を入れ、枝を植えます。直射日光があたらない半日陰で管理し、根が生えてくるのを待ちます。1か月~2か月ほどで発根するでしょう。
4. 発根したら植え付けをおこないます。植え付ける地面や鉢の底に有機質肥料を敷いて植え付けましょう。植え付け後は土が乾燥しないよう水やりをおこないます。
まとめ
マサキは基本的に水やりの回数も少なく、暑さや寒さにも強いため、育てやすい庭木として人気があります。マサキを育てるうえで大切なことは、定期的に剪定をおこない、葉同士が重なりすぎていないかを観察することです。
日ごろからマサキに気を配ることで、病害虫の被害を未然に防ぐことができるかもしれません。剪定には時間や体力も必要としますが、マサキを元気に育ててきれいな見栄えを維持するためにも、定期的におこないましょう。
マサキの剪定は、準備も必要で作業にも時間がかかるため、少々骨が折れてしまいます。剪定に不安を覚える方や、作業が面倒に感じる方は業者に作業を依頼してみてはいかがでしょうか。弊社のサービスではお近くの剪定業者をご紹介しているので、ぜひご相談ください。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!