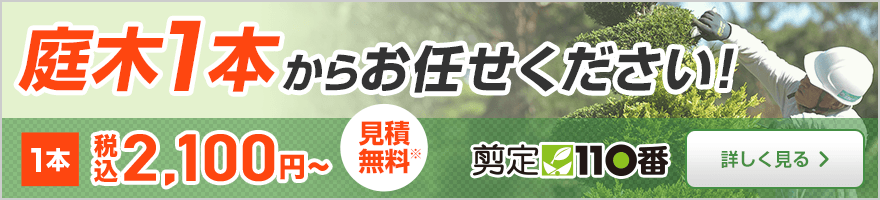大切に育てている桜が、病気にかかって元気をなくしてしまったら心配ですよね。中には株ごと処分しなければ感染を防げない病気もあるため、桜を育てるうえで病気への警戒は欠かせないでしょう。
桜の健康が心配な方は、一度根や枝葉を確認してみてください。病気がみつかっても、はやめに対処すれば枯れることもなくすむかもしれません。
ここでは桜から確認されやすい、代表的な病気の症状をご紹介していきます。予防できるものも多いので、ぜひ参考にしてみてください。
葉っぱに異常が起こる桜の病気
ときには桜の葉が病気のサインを出していることがあります。葉に小さな模様ができている場合は、「せん孔褐斑病(せんこうかっぱんびょう)」の症状かもしれません。
せん孔褐斑病
病原となる糸状菌が葉の表面につくと、次第に小さな斑点が現れるのが特徴です。斑点は大きくなっていき、中心には穴ができます。
菌が付着した葉と健全な葉のちがいはひと目で判断できるほど明らかです。また、発病した葉は落葉がはやく、その表面で病原菌は増殖します。
葉に小さな斑点や穴が確認できたら取り除き、ほかの植物への感染を防ぐために焼却処分しましょう。その年地面に落ちた葉も同じように処分することで、翌年の発病を予防できます。焼却が難しい場合は、地中1mほどにまで埋めることでも対処できます。

幹に異常が起こる桜の病気
幹や枝から桜の病気を引き起こす原因がみつかるかもしれません。この章では、幹や枝に症状がみられる病気を説明してきます。
こうやく病
枝葉に膏薬(こうやく)をつけたようなものが確認された場合は、「こうやく病」という病気にかかっているかもしれません。こうやく病は菌が繁殖してできるカビの一種で、症状が進行した枝は枯れてしまうこともあります。
対策には発病した部分を削り落として感染拡大を防ぐ方法などが有効です。ただし削り口から新たな菌が繁殖することもあるため、薬剤などで保護しましょう。
また、日ごろから桜を育てる環境に気をつかうことも大切になります。風通しや日当たりが悪いとこうやく病に限らず病原菌が繁殖しやすいので注意してください。
こうやく病の病原菌は、カイガラムシという害虫に寄生していることが多いという特徴も覚えておきましょう。カイガラムシ自体が植物に食害などの被害を与えるため、はやめに駆除することが大切です。
てんぐ巣病
たくさんの小さな枝が、ふくらみをもつ枝から生えている場合は、「てんぐ巣病」を疑いましょう。てんぐ巣病の特徴として増える小さな枝には花が咲きません。また本来の開花時期に緑の葉をつけて栄養を使うため、花や樹勢が弱まってしまいます。
発病した枝をこぶ状になった部分から切り取り、焼却処分して対策しましょう。切り落とした部分をそのままにしていると、病原菌が雨風にはこばれて被害が拡大するかもしれません。また、切り口には必ず薬剤などを塗って保護することが大切です。
根っこや地際に起こる桜の病気
地中に隠れている根から、桜が病気にかかってしまうこともあります。なかには株ごと処分しなければいけない「根頭がんしゅ病」などもあるため、しっかり予防して桜の健康を保つようにしましょう。
根頭がんしゅ病
根っこのや地面に近い場所、あるいは接ぎ木したときの接合部分にいくつものこぶが現れるのが、「根頭がんしゅ病(こんとうがんしゅびょう)」の症状です。こぶの大きさはさまざまですが、いずれも木を枯らす原因になるおそれがあります。
残念ながら、根頭がんしゅ病を完全に治療する方法はありません。こぶを削り取った部分に薬剤を散布して保護すれば、ある程度の効果は期待できます。しかしほかの植物への感染を避けるためには、発病した木を根元から抜き取って焼却処分するのが最善です。
また病原菌は発病した木の手入れに使ったスコップや剪定ばさみなどを伝って感染するため注意しましょう。発病した木を抜き取り、新しく苗木を植えたい場合は、土を入れ替えると予防になります。
きのこ
桜の根元から生えてくるきのこ類は、桜が植えられた場所の日当たりが悪いことや剪定方法が悪く枯れて落ちた枝などが原因です。
きのこをそのままにしておくと、桜の成長に必要な栄養が奪われてしまいます。樹勢が弱まれば、枯れる原因にもなりかねません。
もとから手入れや植えつける環境に気をつかっていれば、発生することはないでしょう。きのこが生えてきた場合は、日当たりのよい場所に植え替えたり、土壌を改善したりして対処してみてください。

桜は剪定に弱い
桜が病気にかかったり、樹勢が弱まってしまったりする原因のひとつには、剪定が関わってくるケースが多くあります。桜はほかの植物よりも剪定に弱く、切り口から菌が繁殖しやすい特性をもっているからです。
そのため剪定したあとは必ず薬剤などを用いて切り口を保護することが大切になります。また、剪定時期を見極めることも欠かせません。
桜を剪定するのに適した時期は、葉が落ちきった11月ごろです。気温が高すぎても低すぎても切り口が傷み、菌が繁殖しやすくなってしまうため注意してください。
一度にたくさんの枝を切り落とすことも、樹勢を弱める原因になることがあります。かたちを整える剪定をするときも同じように、切り落としたほうがよい枝なのか、しっかり見極めてから作業しましょう。
まとめ
根や幹、枝葉など、桜から病気が確認される部分はさまざまです。いずれもはやめに対処すればほかの木や植物へ感染するおそれを減らせますが、なかには株ごと処分しなければいけない病気もあります。そのため病気には十分注意しましょう。
また、桜は剪定に弱い植物であるということも覚えておきましょう。ほかの植物でも、発病した部分を切り落として対処する方法をとることがありますが、桜の剪定はとくに注意が必要です。
剪定で枯らしてしまうおそれがあったり、病気の対処方法がわからなかったりするときは、いちど業者に相談してみましょう。病気を予防する方法を教えてもらえることもあるかもしれません。
剪定を依頼できる業者や料金
依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「剪定」をご覧ください。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!