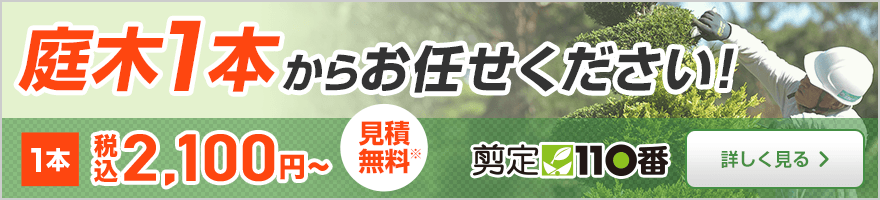オオデマリは水やりや肥料などこまめな手入れを必要としないので、園芸初心者の人でも安心して育てることができるといわれています。日当たりがよい場所で育てれば、毎年きれいな花を咲かせてくれるのです。
しかし、オオデマリを元気に育てるには、正しく剪定をすることが重要です。そこで、今回はオオデマリの剪定方法についてご説明します。剪定のコツを知ることで、オオデマリを長く楽しむことができるかもしれません。
オオデマリの栽培は自然に育てよう
オオデマリは花付きがよく、剪定によって花の数を増やす必要がありません。成長速度もゆるやかなので、できるだけ自然に任せたほうがよいといわれています。
しかし、オオデマリは年月がたつごとに花数が減る傾向があります。花付きの悪い枝が増えてきた場合、剪定して若い枝を育てることで、花を多くつけられるでしょう。
また、枝が長く伸びすぎていたり、枝が込み入ったりしていると全体的な形のバランスが悪くなってしまうのです。さらに、日当たりが悪くなって光合成がうまくできないおそれもあります。
このような問題を解消するには、オオデマリの剪定が必要なのです。ただし、あまり剪定をしすぎるとオオデマリの木に負担がかかるので、枝を切るのは最低限にとどめておきましょう。

美しい花を咲かせるための剪定方法と剪定時期
オオデマリは夏ごろになると来年にむけて花芽をつけるので、剪定は春から初夏にかけて行います。もし、剪定が夏以降になってしまった場合は、花芽がつきにくい長い枝を切り落としましょう。
オオデマリが花芽を付けるより前に剪定をすることで、翌年にたくさん花を咲かせることができるのです。夏以降の剪定になってしまっても、花芽が少ない枝だけ剪定することで、花が減るのを最小限に抑えられるでしょう。
寒さに強いうえ、冬の間は剪定にかかるダメージが少ない休眠期に入ります。休眠期であるうちは、不自然に伸びた枝を剪定したり、樹木が高くなりすぎないよう調節したりできるのです。さらに、ほかの枝の邪魔になる枯れ枝も取り除けます。
枝を剪定する際には、付け根から切り落としましょう。中途半端に枝を残してしまうと、木が不格好になるおそれもあります。根元から枝を切り落としておくことで、切り口から新しく枝が生えるのを防ぎ、整った樹形に仕上がるのです。
全体的な樹形を整えるには、大幅に枝を減らす必要があります。しかしこれを春に行うと剪定による負担からオオデマリが弱ってしまいます。そのため、冬のうちにオオデマリを剪定をしておくことが大切なのです。
より花を楽しむオオデマリの増やし方
オオデマリは剪定で小さくするだけでなく、枝を切り取って株数を増やすこともできます。オオデマリは根を生やす力も強く、繁殖が手軽にできるのです。株数の増やし方は、大きく分けて2通りあります。
挿し木
さし木とは、木の中でも若く実りの多い枝を切り取って、鉢に入れた土へ植えるという方法です。切り取った枝の上部だけ葉を残し、下のほうについている葉は取りのぞきます。枝の切り口を30分から60分前後まで水につけてから、土を入れた鉢に植えましょう。
使用する土はさし木用の細かい土がよいとされています。土に枝を植えたら、こまめに水分を与えて育てていきましょう。
取り木
取り木とは、増やしたい枝の樹皮をはぎ取り、木がむきでたところに水苔をまいて根を生やすというものです。水苔をまいたら、そこをポリ袋で包み、外れないように上下をひもで固定します。
定期的に水分を与え、根が生えてきたら、枝を切り取って土に植えます。皮をむく枝は、さし木と同じく、若くて強い枝を選ぶのがおすすめです。

オオデマリを栽培するときは病害虫に注意!
オオデマリは簡単に増やせますが、増やしたまま放置していると、害虫や病気が発生するおそれがあるのです。害虫や病気が発生したら、早めに対象をしないとオオデマリが枯れてしまうおそれがあります。そうならないためにも、どんな病害虫になりやすいのかを知っておくことも重要です。
害虫
オオデマリに寄生する害虫は、おもにサンゴジュハムシとカイガラムシがいます。2種類とも個体は小さいですが、オオデマリに大きな被害を出すこともあるのです。
サンゴジュハムシ:幼虫のうちは土の中で越冬し、樹木に寄生してからは葉を食べて育ちます。成虫になっても葉を食べ続けるので、葉が穴だらけになってしまうのです。幼虫は殺虫剤をまくことで駆除できますが、成虫は薬剤が効きにくいので、見つけたら駆除しましょう。
カイガラムシ:毛が生えた豆のような虫で、群れになって樹木にびっしりとはりつきます。枝や葉から汁を吸い取るため、栄養を奪ってしまうのです。栄養が不足してくると花や葉が育ちにくくなり、最悪の場合は枯れるかもしれません。カイガラムシは薬剤での駆除が難しいので、歯ブラシや爪楊枝で落としていくのが効果的だとされています。
病気
オオデマリを剪定しないと枝が混み入ってくるため、暗く湿った場所を好む病気の温床にもなります。オオデマリがかかる病気には、おもにうどんこ病と褐斑病の2種類があり、どちらも放っておくと株を枯らしてしまうおそれがあるのです。
うどん粉病:うどんこ病にかかると、葉の表面に粉のような白い斑点がつきます。葉のうえに白い汚れがつき、それが光合成をさまたげる原因になります。ひどくなると木が弱り、枯れてしまうかもしれません。
また、うどんこ病の菌は、いちど発病した植物と同じ種類のものに感染しやすい性質を持っています。そのため、症状のでた葉や落ち葉を取り除き、薬剤を散布する必要があるのです。予防するには、剪定によって通気性と日当たりを改善する必要があります。
褐斑病(かっぱんびょう):葉の表面が茶色に変色する病気で、おもに湿った木や土が感染源とされています。変色した部分は枯れてしまうので、病気が広範囲に広がるとオオデマリ自体が弱ってしまうのです。
褐斑病を予防するには、土の下に軽石を入れるなどして排水性を高めておきましょう。また、剪定をして通気性を高めるのも大切な予防策のひとつです。
まとめ
オオデマリは剪定をあまり必要とせず、自然のままに育てるのがよいとされます。花付きが悪かったり、枝が伸びすぎたりしている場合には剪定をするのがおすすめです。
もしも剪定をせずに放っておくと、害虫や病気にかかるおそれがあります。害虫や病気は通気性のいい場所を嫌うので、剪定して予防する必要があるのです。
しかし、病害虫を予防するために、工夫して剪定するのは難しいかもしれません。そんなときは、剪定を業者に任せてみてはいかがでしょうか。業者に依頼することで、オオデマリを長く楽しめるのではないでしょか。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!