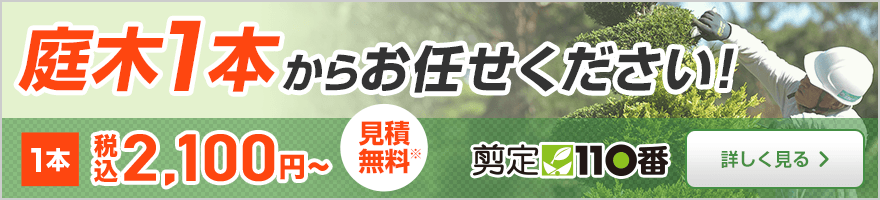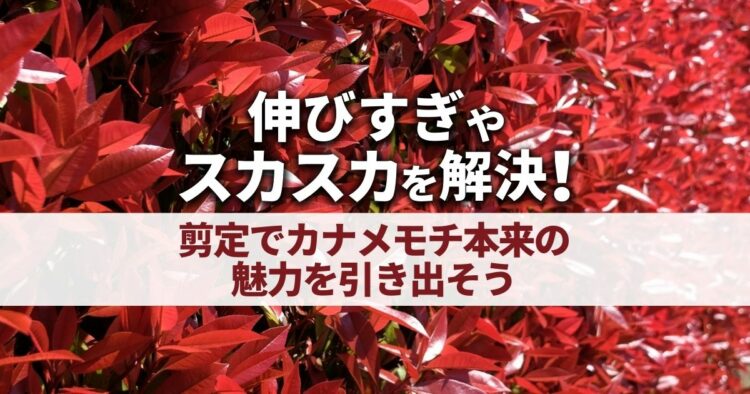
季節によって違った表情を見せてくれるカナメモチ。春は赤い新芽、初夏には白い花、秋はたくさんの実をつけ、冬も葉を落とさず庭を彩ってくれます。
このように、本来は一年を通して美しい姿を楽しめるはずのカナメモチですが、「高くなりすぎた」「うまく形がまとまらない」など、思うように剪定できずお悩みの方も多いのではないでしょうか?
そこで当記事では、カナメモチの剪定時期と方法について詳しくご紹介します。カナメモチは上へぐんぐん育っていく傾向があるので、高くなりすぎると下のほうが枯れ、スカスカになってしまいます。1年に2回~3回ほど剪定して、育ちすぎや枯れを防ぎましょう。
こまめな剪定が大切だとわかっていても、実際に毎年欠かさず続けていくのは大変ですよね。
- 剪定のための時間をとれない
- 体力的に厳しい
- 下のほうがスカスカになってきた
こんなときは、無理せずプロの手を借りましょう。初心者には大変な広範囲の剪定、暑い時期の剪定、枯れかけている木の剪定なども、プロにとっては慣れたもの。あっという間にきれいに仕立ててもらえます。
目次
カナメモチの剪定のコツ
カナメモチはよく芽吹く特性を生かして、生垣に利用されることが多い植物です。美しい生垣を仕立てるために必要な、カナメモチの剪定のコツを見てみましょう。
生垣に向いている剪定方法
カナメモチを生垣に仕立てるときは、刈り込み剪定という方法が適しています。刈り込み剪定とは、長くのびすぎた枝を切って、木の形を整える方法です。
カナメモチの場合は、芽吹く力が強く新しい枝がつんつんとのびてくるので、切りそろえておかないと見栄えが悪くなってしまいます。また、剪定後に新しく出た葉が綺麗な赤色になるので、こまめに整えておく方がよいですね。
カナメモチの剪定をおこなうのは基本的に年2~3回です。5~6月に赤い葉が緑色になったころに、1回目の剪定をしましょう。
このときは、春にのびて長くなりすぎた枝を切り戻して、形を整えることが目的です。夏になると花芽が育ちはじめるので、翌年に花を楽しみたい場合は早めに終わらせるようにしてください。
2回目の剪定は9月ごろにおこないます。10月以降に刈り込むと、寒さに負けて新葉が枯れてしまうおそれがあるので、なるべく9月中に済ませるようにしましょう。
またその剪定では、枯れた枝や、内側に向かってのびている枝など、不要な部分を切り落とします。適度に風通しをよくしておくことも、病気や害虫を防ぐために大切です。
一度に強く刈り込みすぎてしまうと、枝が枯れてしまう場合もあります。枯れるリスクを減らし、生垣としての見栄えのよさを保つためにも、こまめに少しずつ刈り込みする方がよいでしょう。
もしも枝の成長がさかんな場合は、刈り込み剪定の回数を増やすとよいそうです。年に3回剪定する場合は3~4月ごろを目安におこないます。剪定の回数や方法がわからないときは、業者に相談してみるとよいでしょう。
高くしすぎると足元がスカスカに!
カナメモチは上に向かってよくのびる特徴があります。そのため、放っておくと5m以上の高さに育つでしょう。
しかし、育ちすぎたカナメモチは、下の方が枯れてスカスカになってしまいます。足元がスカスカになってしまうと、目隠しとしての生垣の役割を十分に果たすことができません。
大きくなりすぎると手が届きにくく管理もしにくいので、一定の大きさになったら刈り込み剪定をしながら高さをキープしましょう。刈り込みをおこなうと新しい葉が出やすくなり、赤い葉を楽しむこともできます。
カナメモチの種類とその剪定時期について
カナメモチにはさまざまな品種があります。ここでは、代表的な3種類のカナメモチの仲間について紹介します。
カナメモチ
カナメモチは日本に広く分布する植物です。とくに西日本や四国、九州のような温暖な地域を好み、風土に合うので庭木としても育てやすい品種です。4月~5月ごろに赤く色づいた新葉を楽しむことができ、別名アカメモチとも呼ばれます。
先述でも紹介したように、カナメモチの剪定は5~6月ごろ、9月ごろに加え、必要であれば3月ごろの年2~3回程度おこないます。刈り込んでから時間が経つと葉が緑色に変わってしまうので、葉を長く楽しみたい場合は、こまめな剪定をするとよいでしょう。
ベニカナメモチ
もともと日本にある在来種で、昔から生垣や庭木としてなじみのある品種です。新葉の赤色と、株の内側にある緑色のコントラストが美しく、和風・洋風どちらの家にもマッチしやすいので、かつては人気を博しました。
カナメモチよりも鮮やかな赤色とやや小さめの葉が特徴です。新葉以外にも赤い葉が残ることもあるそうです。そのため、剪定から時間が経っても長く赤い葉を楽しむことができます。剪定はカナメモチと同じく、開花後の5~6月ごろと9月ごろにおこなうとよいでしょう。
生垣として広く使われていましたが、病気などで枯れやすいこともあり、以前より流通は下火になっているそうです。
セイヨウカナメ
日本固有種のカナメモチとオオカナメモチをアメリカで改良して作った品種です。レッドロビンという名前でも広く知られています。
セイヨウカナメはベニカナメモチのように鮮やかな赤い葉を持ちつつ、病気にも強い品種に改良されていて、生垣に使われることが多いようです。カナメモチよりも大きな葉が特徴で枝の成長も早く、しっかり刈り込んでも枝が枯れにくいのが特徴です。
セイヨウカナメはとくに枝がよくのびるため、年に2度の剪定では生垣の形が荒れてしまうかもしれません。必要に応じて3月にも形を整えるようにしてください。
成長が早いので、背がのびすぎると下の方が枯れてスカスカになってしまうこともあります。剪定が追い付かない場合は、業者に相談してみてはいかがでしょうか。
花も綺麗なカナメモチは剪定でゴージャスに
カナメモチは生垣として仕立てる場合が多く、主に葉が鑑賞される機会が多いです。葉に比べてあまり着目されることは少ないですが、カナメモチは5月から6月ごろにかけて開花を迎えます。
カナメモチの花は、小さな白い花がまとまってたくさん咲きます。開花時期にはふんわりとした花のかわいらしさや、赤、白、緑の3色のコントラストが楽しめます。
カナメモチは一般的には生垣として仕立てるために、のびてきた枝葉をこまめに刈り込む場合が多いです。しかし、強く剪定しすぎると花芽ごと切り落としてしまうため、しっかりと手入れされているカナメモチには花がつかない場合もあります。
生垣としての見栄えも大切ですが、5月ごろに白い花を楽しみたい場合はカナメモチの剪定を軽めにしたほうがよさそうです。夏になると花芽をつけ始めるので、もし見つけたらなるべく切らないようにすると、翌年の開花が楽しめるかもしれません。

カナメモチを剪定しないとどうなる?
カナメモチは形を整える刈り込み剪定をおこなうので、あまり複雑な手入れは必要ありません。しかし、先述したように、生垣としての美しさを保つためには、枝がのび放題にならないようにこまめに剪定をおこなう必要があります。
カナメモチを剪定して低めに仕立てておくことは可能ですが、放置しておくとどんどん上へのびて、手が届かない高さになってしまうこともあります。また、大きくなりすぎたカナメモチは、下の枝が枯れやすくなるため、本来の目隠しとしての役割を果たさなくなってしまう場合もあります。
忙しくてあまりこまめに剪定できない場合や、外から目に付くカナメモチを綺麗に仕立てたい場合もあるのではないでしょうか。そのように、自分でカナメモチを剪定するのが難しかったり、不安があったりするときは、業者を活用すると安心です。
まとめ
カナメモチは日本でも生垣によく使われているので、自宅で剪定する機会があるかもしれません。日本の風土にも合っていて比較的育てやすい庭木ですが、綺麗な生垣に仕立てるためにはこまめな剪定が必要です。
綺麗な赤い葉の生垣を作るためにも、まずはカナメモチの剪定の時期やコツを知ることは大切です。せっかく植えたカナメモチがのび放題になって、足元が枯れてしまわないように定期的にメンテナンスしてください。
生垣は剪定する箇所が広い場合もあるので、自分で手入れするのが大変な場合は、ぜひ業者を活用してみてください。家のアクセントになる美しい生垣を仕立てられるのではないでしょうか。
剪定を依頼できる業者や料金
依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「剪定」をご覧ください。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!