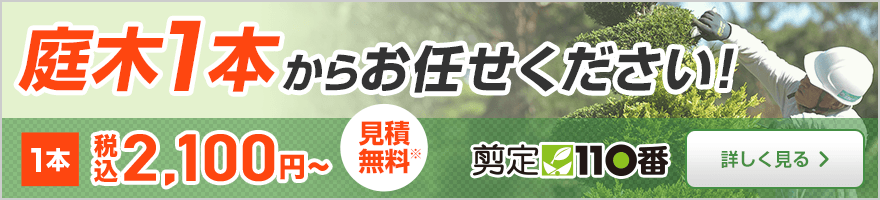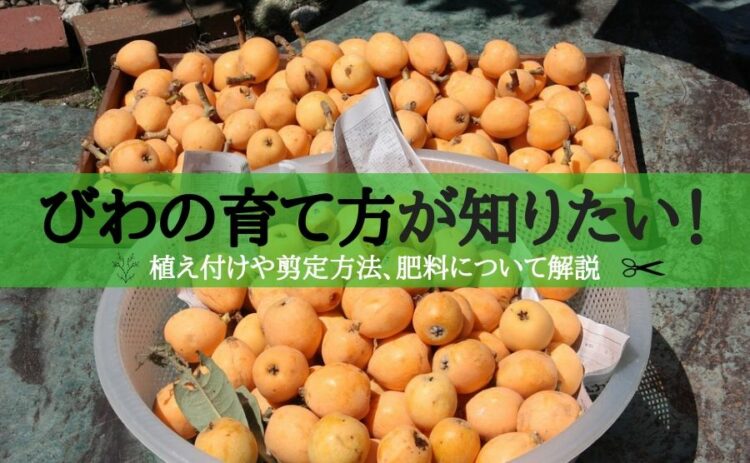
「びわを育てたい!」というときは、育て方の基本をまず知りたいですよね。びわを育てると、最終的にびわの実をご自宅で楽しめるようになります。美味しい実を育てるのも、楽しみのひとつになりそうですよね。
今回は、びわの育て方を中心にまとめます。まずは、一からびわを育てたい!という方に向けて、びわの植え付け時期をご紹介します。また、美味しい実をつくるにあたってかかせない肥料や剪定方法にも触れるので、ぜひ参考にしてみてください!
目次
冬季でも可能?苗木の植え付けや種まきの時期と方法
びわを植え付ける時期は、冬でも可能です。ただし、冬に植え付け可能なのは、苗木から育てる場合です。種から育てる場合は時期が違ってくるので、注意しましょう。
ここでは、苗木の植え付け時期と種まきの時期をご紹介します。
苗木の植え付け時期と方法

苗木は、冬から春にかけて植え付けます。具体的な時期は2月下旬から4月の間です。日当たりがいい、かつ水はけのいい場所を選ぶようにしましょう。植え付けは地植えでも鉢植えでも可能ですが、水はけが悪い場所ではびわが弱ってしまうため注意が必要です。
地面に植える場合は、深さと幅50cm四方に掘り土を掘り起こします。そして土をそのまま戻すのではなく腐葉土を2~3割ほど混ぜ優しく戻し、苗を植えていきます。
苗木は小さく、土が硬いと根を張ることができないので、最初に深めに掘り土を柔らかくしてあげることが重大です。びわの育て方として虫がつきやすいので気をつけてあげることも重要です。
種まきの時期と方法
種から育てる場合は、5~6月が種まきの適期になります。一番簡単な植え付け方法は、種を土に埋める方法です。3cmほど穴を掘ってそこに埋めましょう。
まずはスポンジを使って種を育てていく、という方法もあります。種をよく洗って、スポンジの上に種を置き、種が浸かるくらいの水をいれて育てるというものです。根が出てきたら、鉢に植え替えます。
植え付けは、びわの育て方ではじめにおこなうことです。苗木から育てるか種まきをして種から育てるかで、時期が異なります。種から育てる場合は育つまでに時間がかかりますが、じっくりと育てたいという方におすすめです。
鉢植えでびわを育てるときの注意点
コンパクトに育てたい方には「鉢植え」がおすすめです。鉢植えの場合、根詰まりを起こさないように2年に1度一回り大きな鉢植えに植え替えをおこなうようにしましょう。植え替え作業中に根を切ってしまったり、千切れてしまったりすると根っこから雑菌が侵入し病気になってしまうことがあります。十分気をつけて作業をおこないましょう。
手入れなどは地植えよりも手間になってしまいますが、小さくひっそりと育てるのには鉢植えはぴったりです。愛情を込めることができて楽しいですよ。
土つくりや肥料について

びわに最適な土と肥料について確認してきましょう。びわの育て方の基本としておさえておきたいですね。
びわに最適な土
びわに向いている土には特徴があります。それが、「水はけがいいこと」「弱酸性であること」です。
水はけのよさは先ほどもお伝えしたように、びわを育てるにあたって重要なポイントになります。「植える場所の水はけが悪くどうしても改善しない・・・・・・」という場合は、腐葉土を混ぜることで水はけをよくしておくといいでしょう。
肥料は年に3回
肥料は年に3回おこないます。まずは2~3月の寒い時期に肥料を与えます。実をつけ始める時期になるため、肥料が必要です。次におこなうのが6月ごろの収穫を終えたころに与えます。
また、11~12月も肥料を与える時期となります。牛や鳥の糞などの肥料を土に混ぜて与えてください。この時期の肥料は寒肥といわれています。寒い時期に肥料を与えることで、暖かくなってきたときに成長を促してくれます。
最初にご紹介した、二つの肥料時期には、化成肥料が最適です。化成肥料とは、生長をよくする肥料です。即効性があり、かつ安価で手に入るのが特徴でびわにも向いています。
びわの剪定時期はいつ?
美味しいびわを育てるためには、剪定が大切です。びわは木の育ち方で剪定時期が変わります。剪定時期を間違えてしまうと、実をつけなくなってしまったり、芽をつけなくなったりしてしまうので気をつけましょう。
まだ実をつけたことのない木の場合は2月頃に剪定をします。この時期にはびわの花が開花しているため、花に気をつけて剪定することができるのです。花になる芽を誤って切ってしまうと、実の付きに影響してしまいます。
剪定方法を間違えたばかりに、「びわの実が収穫できなかった……」という事態にもなりかねません。実の付きを重視するのであれば、2月中旬ごろに剪定すると安心できそうですね。
実をつけるようになった木の場合は8月下旬~9月頃に剪定をするとよいでしょう。びわの実がたくさんつき過ぎてしまうと栄養が分散し、味の劣化につながります。稀に、実の重さに耐えられず木が折れてしまうこともあるようです。ただし、のちに花になる花芽をすべて切ってしまうことで、実が付かなくなってしまうため注意が必要です。
また、3月中旬以降の強剪定は避けたほうがよいでしょう。強剪定とは、大きな枝を切るなど、大掛かりな剪定のことです。この時期に強剪定をすると、びわが弱ってしまうことがあります。

びわの剪定方法やポイント
びわの剪定方法は大きく2種類あります。ご自宅のびわの状況に合わせて剪定しましょう。
びわの剪定で一番覚えたいのが「間引き剪定」です。間引き剪定とは、枝を元の部分から切り落とすことをいいます。
主幹と呼ばれる枝(基礎となる部分)から細かい枝がいくつか生えているのがわかりますか?切る対象はその枝です。細々している枝を切ることで、びわの成長にかかせない日当たりを改善します。
もうひとつ、状況に応じておこないたいのが「切り戻し剪定」です。この方法は、枝の途中でバサッと枝を切る方法です。これをすることで、びわを小さくすることができます。例えば、お庭に対してびわが大きくなりすぎてしまったり、お隣の方に迷惑がかかるくらい大きくなってしまったりというときは使える剪定方法です。
摘蕾(てきらい)・摘花(てっか)の方法

冬に咲いた花すべてが実をつけてしまうと、栄養が分散してしまい、酸っぱいか味のしない果実になってしまいます。美味しいびわを食べるためには半分くらいにしたほうが甘い果実を食べることができます。
花の蕾はかたまって付いているので、大体それぞれ4.5個残して摘んでしまいましょう。
実ができてきて、多いかなとおもったら早めにもいでしまうのがいいでしょう。
びわは絶対に剪定しなくてはいけないというものではありません。間違った剪定で「実が付かなくなってしまった……」という事態になることも考えられるので、無理のない範囲でおこなうことが大切かもしれません。
剪定方法やびわの育て方に不安がある場合や、お隣に迷惑がかかっているから剪定したいといったときは、業者に依頼するのもひとつの手です。まずは剪定の見積りをとってみて、価格を見てから検討するのもいいですね。
まとめ
びわの育て方のなかでも重要なのは剪定で、大きくわけてふたつあります。おもにおこないたいのが切り戻し剪定です。日当たりをよくするために、様子を見ながら剪定をしていくといいでしょう。剪定時期は適期があるので注意が必要です。「自分でやるのは不安……」という場合は、業者に依頼するのもひとつの方法になります。
はじめてびわを育てるという方は、植え付けからおこないましょう。植え付けは種まきからおこなう方法と、苗木からおこなう方法のふたつがあります。実が付くまでにかかる時間ややり方が異なるので、自分に合った方法を選択していきましょう。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!