
松の木は庭木としても盆栽としても人気の高い樹木です。しかし、庭木と盆栽とでは、育て方や剪定方法が異なるので、お手入れの方法を間違えてしまう方も多いです。
そこで今回は、赤松や黒松の剪定方法を、盆栽の場合と庭木の場合にわけてご紹介します。松のお手入れで悩みがちな芽摘みや芽切り、見栄えよく仕上げるコツなども、イラストを使いながら解説します。松のお手入れにお困りの方はぜひご一読ください。
松の剪定は難易度が高いため、年月をかけて徐々にコツをつかんでいきましょう。枝を切りすぎると松にダメージを与えてしまうので、仕上がりに納得がいかないときも、ある程度のところで見切りをつけてください。
とはいえ、せっかく松を育てているのなら、お庭を美しく保ちたい方や、自分で理想の形に仕立てられるようになりたい方も多いでしょう。そんなときはプロの出番です。
プロに依頼すれば、松をきれいに剪定してもらえるうえ、作業の手順を見たりアドバイスをもらったりすれば、自分で剪定する際のコツも身につきます。自分で剪定するのが大変なときや練習してもうまく剪定できないときは、遠慮なくプロに相談してみましょう。
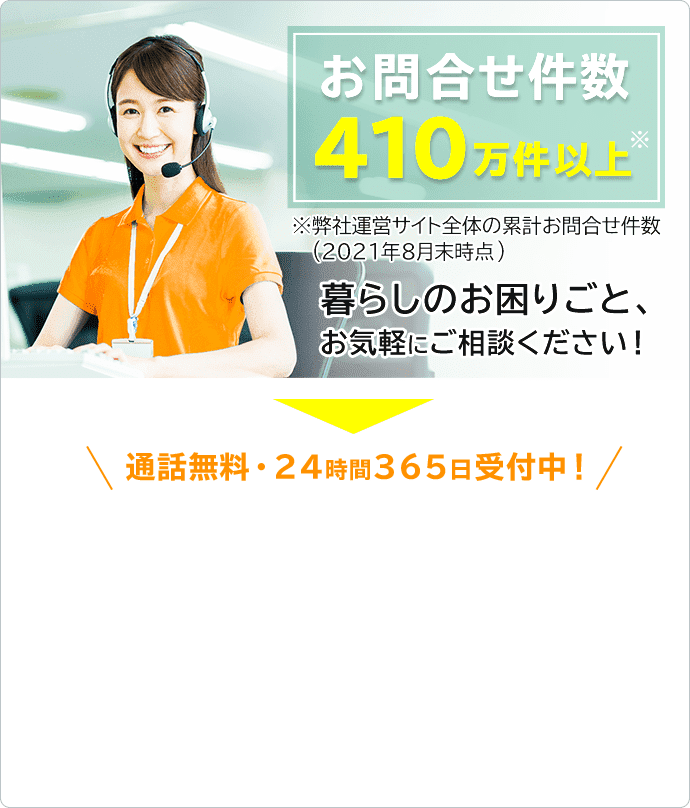
目次
松は盆栽の種類のひとつ
盆栽を見て、「鉢植えで育てる庭木と何が違うの?」と思う方がいるかもしれませんが、実は盆栽には意味があり、鉢植え栽培とは異なるものなのです。
盆栽は、盆が鉢、栽が樹木を意味します。植えられている樹木だけが主役になるのではなく、鉢まで含めたすべてを観賞するものなのです。
そして盆栽には、松の盆栽を意味する「松柏盆栽」や、葉の色や落葉などで四季を楽しむ「雑木盆栽」などさまざまな種類があります。
雑木盆栽は、選ぶ樹木によって紅葉する葉や色鮮やかな花、実が楽しめるものがありますので、気になった方は、松と一緒に育ててみてもよいかもしれません。
代表的な3つの品種

盆栽にはさまざまな植物があるとご紹介しましたが、なかでももっともポピュラーなものが松の盆栽です。松だけでも複数種類があるので、ここでは代表的な3種類について解説します。
・黒松
日本全国に存在しているマツ科マツ属の常緑高木です。庭木として育てると、樹高は35mになるものもあり、樹皮が黒いことが名前の由来です。潮風に強いため風や砂を防ぐために植えられることもあり、海岸地域に多く見られます。
・赤松
日本に広く分布しているマツ科マツ属の常緑高木です。庭木として育てると、樹高は30mほどまで生長する場合があり、赤みを帯びた樹皮が特徴的です。比較的寒さに強いですが、北海道では寒害にあうこともあります。
・五葉松
日本では南部のほうに自生しているマツ科マツ属の常緑高木で、樹高は20mくらいまで生長します。先の2種類に比べて短めの銀色がかった葉が特徴的です。和風の雰囲気に合うので、神社仏閣や庭園などに植えられていることが多くあります。
上記の3種類のうち、今回は黒松と赤松を盆栽にした場合の育て方や剪定方法について解説します。五葉松の場合は、ほかの2種類と葉の長さが違うという特徴があり、おこなう必要のない作業があるので注意してください。
松の盆栽の育て方
松の盆栽を楽しむためには、正しい方法でお手入れをおこなって健康に松が育つことが大前提です。まずは苗選びから樹形をつくる針金かけまで、基本的な育て方を確認していきましょう。
苗を厳選する
松の苗は幹や枝が太く、根のしっかりしたものを選びましょう。現在の樹形や状態はもちろん、ある程度将来を見すえて選ぶことも大切です。
幹模様や生え方などに注目してみて、自分の思い描く樹形になりそうな松を選ぶことができれば、そのあとの剪定や生育のイメージもしやすいでしょう。生育をはじめる前から松をよく観察しておくことが、美しい樹形の松を育てるコツです。

植え付け
植え付けは、黒松なら2月~4月ごろ、赤松なら3月~4月ごろが適した時期です。ただし、苗を購入してすぐに盆栽用に選んだ鉢に植えてよいとは限りません。
植え付け時期を過ぎた秋以降に購入した苗は、ひとまず屋外に置いて翌年の植え付け時期まで待ちましょう。その間、土の湿度を保つことが重要になります。土が乾ききってしまうことがないように、水やりをおこなって管理しておきましょう。
盆栽の置き場所
盆栽の置き場所は、“ここでなくてはならない”と細かく決まっているわけではありません。しかし、地面に直接置いてしまうと、害虫がつきやすく風通しが悪くなりやすいため、屋外で少し高さのある棚の上に置いておくのがよいでしょう。
四季それぞれの水やり
水やりの頻度は季節によって異なります。基本的には以下のようなタイミングでおこなうのがよいとされているので、覚えておきましょう。
| 季節 | 回数 | タイミング | やり方 |
| 春 | 1日1回 | 土が乾いていたら | 根元に回すように水をかける |
| 夏 | 1日2~3回 | 朝と夕方、日照りのときは昼間にも | 根元に回すように水をかけるのと、葉に直接水をかける |
| 秋 | 1日1~2回 | 土が乾いていたら | 根元に回すように水をかける |
| 冬 | 2日に1回程度 | 暖かい昼の時間帯 | 根元に回すように水をかける |
基本的に盆栽への水やりはジョウロを使っておこないます。上記のタイミングややり方を守って、鉢底にあいている穴から水が流れてくるくらいたっぷり水やりをしてください。
肥料
盆栽は、鉢のなかにある土から栄養を取り入れるしかありません。そのため、盆栽の生長には肥料がとても重要になります。肥料を与えるのは4月~12月の間月に1回です。油かすが主成分の有機肥料を与えて生長を促しましょう。
ただし、肥料を与えることを控えなくてはならないタイミングもあります。それが、梅雨の時期と植え替え後です。
・梅雨の時期
土に肥料が溜まっている可能性があります。人間に薬の過剰摂取がよくないように、樹木も肥料を過剰に吸収してしまうのはよくないことなので、控えたほうがよいのです。
・植え替え後
植え替え時に根を切っているため、根が弱っている状態です。体調を崩したときに食欲がなくなるような感覚に近いかもしれません。肥料を控えて、松の木を労わってあげましょう。
植え替え
松の盆栽は、2~3年に1度、2月~4月に植え替え作業をする必要があります。ずっと同じ鉢のなかで動かさずに育てていると、生長した根がつまるなどして水や栄養をうまく吸収できなくなってしまうのです。
タイミングに迷うときは、水やりをしたときの土の様子を見れば植え替えが必要かどうかわかります。水がなかなかしみ込まず、表から溢れてしまうようであればすでに根がつまってきている状態です。早めに植え替えをしてあげましょう。
植え替えはただ鉢を変えるだけではありません。樹木を取り出したら丁寧に土を落とし、下のほうで絡まる古い根を切ってから新しい鉢に植え替えましょう。
針金かけ
盆栽のお手入れで忘れてはいけないのが、針金かけです。針金かけとは、名前の通り枝に針金を巻き付けて樹形を整える作業のことをいいます。
美しい樹形をつくりたいときは、冬場の少し葉が少ない時期におこなうと、枝全体のバランスが見やすいのでおすすめです。
松の盆栽剪定に必要な道具
松の剪定に使用するおもな道具は、盆栽バサミとピンセットの2点です。少し太めの枝を切る必要がある場合もあるので、ハサミは切れ味のよいものを用意しておくようにしましょう。
ピンセットは、これからご紹介する芽摘みという剪定で使用するほか、雑草やゴミを取り除くためにも使用します。繊細な作業に使うものなので、盆栽の大きさにあわせて使いやすいサイズを購入しましょう。
黒松・赤松特有の剪定1:『芽摘み(ミドリ摘み)』
芽摘みは別名ミドリ摘みともいい、黒松や赤松の枝から伸びる葉の芽を摘む作業になります。おもに枝の数を減らしたり、樹形が広がりすぎたりしないようにするためにおこなう作業です。放置しておくと樹形が乱れてしまうため、しっかり摘み取っておきましょう
芽摘みの時期
時期としては4月~5月あたりが最適です。芽摘みをしておくとのちに説明する『芽切り』などの作業が楽になります。
芽摘みの方法
黒松や赤松の芽は薄黄緑色で細長く、ひとつの枝に3つほど付いていることが多いです。なかには芽が1つのものもありますが、基本的には多くは両脇が小さく中央のひとつだけ長い、漢字の『山』のような形で伸びています。
芽が3つの場合は、真ん中の長い芽を根元から摘み取ってあまった2つの芽を残し、芽が1つの場合は、芽を2~3cm残す程度の部分でちぎって長さを調整しておきましょう。ただし、芽の色が茶になっているようなものは、芽の数に関わらずすべて摘み取ってかまいません。
この芽摘みではハサミは使いません。芽を見つけたら素手でちぎるようにしましょう。素手でちぎればハサミの刃で葉を傷つけることがありませんし、作業効率もよく自然な樹形に仕上がりやすくなります。
また、この作業は枝を減らす作業となるため、枝が少なく増やしたい場合は芽摘みをしない、または少量の芽摘みだけでも大丈夫です。

黒松・赤松特有の剪定2:『芽切り』『中芽切り』
『芽切り』と『中芽切り』は、新芽を切ることで葉の長さや全体のバランスを調整する作業です。ここからは、松に盆栽バサミを入れるような作業になっていきます。難易度も少々上がるので、しっかり確認しておきましょう。
芽切り
芽摘み(ミドリ摘み)をしていない場合には、このタイミングで芽の長さを調節する必要があります。ある程度伸びた新芽を剪定バサミで落とし、二番芽とよばれる芽を付けるための作業です。
芽切りの時期は6月~7月で、剪定のタイミングはその木の樹勢によって少々異なります。回復の早い元気な木であれば遅め、回復の遅い元気のない木であれば早めに芽切りをしていきましょう。
元気な木を芽切りしていく際も、一気にすべての芽を切ってはいけません。芽のなかでも弱いものから剪定していくことが大切です。
数日~数週間かけて芽切りしていくことで、全体のバランスが整います。芽の根元が残らないように、まっすぐ根元からカットしましょう。

中芽切り
枝を増やすための芽摘みや芽切りをあまりしなかった場合などは、『中芽切り』という作業をする必要があります。時期としては、8月~9月の作業が最適です。
中芽切りでは、その年に生長し伸び過ぎた枝を切り落とします。この場合も、芽摘み同様3方向に枝が伸びていたら中央の枝を中心に切り落としていきましょう。そのほかの枝もバランスよく切り戻したら、込み合った葉を抜いて調節しておきます。
基本的には枝が伸び過ぎてしまったときにする作業なので、中芽切りをするとその年の黒松はあまり楽しめなくなる可能性があります。秋~翌年の春に付く芽に期待しましょう。
黒松・赤松特有の剪定3:『葉むしり』『もみあげ剪定』
枝が弱る冬場には、『葉むしり・もみあげ剪定』をしておく必要があります。黒松や赤松は、この剪定をしておくと外観・樹勢ともによい影響があるため、毎年欠かさず取りかかりましょう。
葉むしり・もみあげ剪定の時期
葉むしり・もみあげ剪定は、10月ごろから年明け辺りまでの時期におこなう作業です。1~2月でももみあげ剪定はできますが、早い時期にしておくと葉がやわらかい状態で楽に剪定できます。
葉むしり・もみあげ剪定の方法

この剪定は古い葉を除去することが中心となります。ある程度元気のある松の場合は、毎年しっかり古い葉をむしっておくことが大切です。
同時に、弱った枝や込み合った枝、夏に伸びた不要な枝などは、このタイミングで付け根から切り落としておきましょう。
古い葉や枝は、残しておいてもあまりメリットがありません。逆に変色して外観を乱してしまったり、樹木全体の通風性や日当たりを落としてしまったりと、デメリットが多いのです。
黒松や赤松が健康に美しく育つようにするためには、整った生育環境が必須です。上記のような作業を忘れずにおこなうことで、生育環境を改善することはできますので、毎年丁寧な作業を心がけましょう。
樹形をうまく仕上げるコツ
ここまでにご紹介したように、正しく丁寧な剪定をおこなえば、盆栽は健康的で美しく育ちます。しかし、より樹形をうまく仕上げようとした場合は、ほかにも2つのコツを知る必要があるのです。
強剪定と針金かけ
強剪定とは、太く生長した枝を切り戻して、樹形を大きく変えるような剪定のことです。強剪定後には、針金をかけて樹形を整えることもあります。
あまり寒い時期にこの剪定をしてしまうと、木が弱ってしまうおそれがあるため、強剪定をする場合は3月ごろが適期です。強剪定は樹形を整える効果も大きいですが、木へのダメージも比例して大きくなります。木が弱っている場合は強剪定をしないようにしましょう。
『上から下に』『奥から手前に』『Y字に』を意識する

剪定で大切なのは枝葉を傷つけることなく樹形を整えることです。そのために気を付けることが『上から下に』『奥から手前に』向かって剪定することになります。
下から上もしくは手前から奥の順で剪定してしまうと、先に仕上げた部分に後から剪定する枝が落ちてきてしまうのです。
盆栽は剪定する枝葉が小さいのであまり問題ないと思いますが、切れた枝が尖っていた場合などは残したい枝葉を傷つけてしまうおそれがあります。そのようなリスクを回避するために、剪定をする流れを意識しておくとよいでしょう。
また、黒松や赤松の枝の外観を整えるときは『Y字』のシルエットになるようにカットすると全体の見栄えがよくなります。まっすぐな枝が多いと外観が崩れて見えるおそれがあるので、注意してください。

庭木の松との違い
鉢植え栽培と盆栽が異なるものだということはご紹介しました。では、盆栽だけではなく庭木として松を育てたいと思った場合は、どのようにお手入れをしたらよいのでしょうか。
じつは基本的なお手入れ内容はほとんど変わらないのです。異なるのは植え付け時の注意点くらいです。
庭木として育てる場合は庭木の場合は、盆栽のように植え替えをすることがありません。とくに庭に直植えする場合は、植え付けてから樹木を移動させることが困難になります。そのため、日当たりがよく風通しのよい場所を慎重に選んで植え付けることが大切です。
庭木の松を剪定する道具
基本的なお手入れは変わらないとご紹介しましたが、庭木の松は盆栽と違って大きく生長しますので、剪定に使用する道具は変わります。必要なものは以下の通りです。
・剪定バサミ、枝切バサミ
・剪定のこぎり
・軍手、安全靴、作業着
・脚立
ハサミは、切ることができる枝の太さや柄の長さなどが異なるいくつかの種類があります。松の生長具合や自分の手の大きさなどを考慮して、使いやすいと思うものを準備するようにしましょう。そして、ハサミでは対応できないほど太い枝がある場合は、のこぎりを使います。
軍手や作業着、安全靴などは、作業中のケガを防止するためのものです。剪定は刃物を使う作業ですし、切ったあとの枝を踏んだり足に引っ掛けたりするおそれもあります。
このような危険から身を守るために、軽装ではなくしっかりと肌を出さない服装を用意する必要があるのです。
また、松は非常に高く生長することがあります。すると剪定も高所作業となるため、脚立を使用する必要があるのです。作業中に落下などの事故がないように細心の注意を払って作業しましょう。
庭木の剪定が難しい場合はプロに相談
松の剪定は作業の種類が多く、難易度も少々高いものが多くなっています。また、松は庭植えの場合だと人の身長をゆうに超えるほど大きく生長するため、上部の剪定が大変です。
やり直しがききにくいということもあるので、自分で剪定をおこなうことに不安のある方は、業者に剪定してもらうことをおすすめします。
自分で剪定するのも松生育の醍醐味ですが、大きくなりすぎてしまった黒松を剪定するには時間も手間もかかります。面倒な手間をかけずに美しく剪定したいという方は、プロの技術に頼りましょう。
松の木の剪定料金は、木の高さや業者の設定金額の方式などによって大きく変動します。地域などによっても差が出ることがあるため、まずは気になる業者に見積りを取ってもらいましょう。

まとめ
松の盆栽は、常緑の葉と美しい樹形を観賞することができるものです。黒松や赤松、五葉松などさまざまな種類がありますが、どれも庭木としても栽培できるものを使用して盆栽をつくります。
そして、盆栽を美しい状態に保つためには適切な剪定をおこなう必要がります。ご紹介した道具を揃えて、適期に作業をおこないましょう。
松の盆栽の剪定は、芽摘み・芽切り・もみあげなど複数の方法があります。それぞれ時期も手順も異なるため、間違いのないように注意しておこなうことが大切です。
さらに、庭木としても松を育てたいと思った場合は、庭木剪定用の道具も準備して、盆栽と同じ時期に剪定をおこなう必要があります。剪定内容は同じでも、庭木の場合は木の大きさによっては高所での作業になるでしょう。
作業自体も難しくなりますし、脚立から落下するなどの事故のリスクもあります。安全に美しい樹形をつくりたいという方は、庭木の剪定はプロに相談しましょう。
\ 完全無料 /
厳選した全国の剪定業者を探せます!
×
関連記事カテゴリ一覧
剪定の記事アクセスランキング
剪定の最新記事
カテゴリ別記事⼀覧
- お庭の手入れ
- 害虫駆除
- 害獣駆除
- 電気工事
- 鍵開け・交換・修理
- 窓ガラス修理・ドアノブ修理
- 家の修理
- バッテリー上がり
- ハウスクリーニング
- ペット火葬・葬儀
- 家電修理
- パソコン修理・ネット回線
- 家具・雑貨の修理
- 外壁・屋根工事
- リフォーム
- 防犯カメラ設置
- 盗聴器・その他調査診断
- 便利屋・代行サービス
- 引越し・配送サービス
- オフィス・店舗向けサービス
- その他










