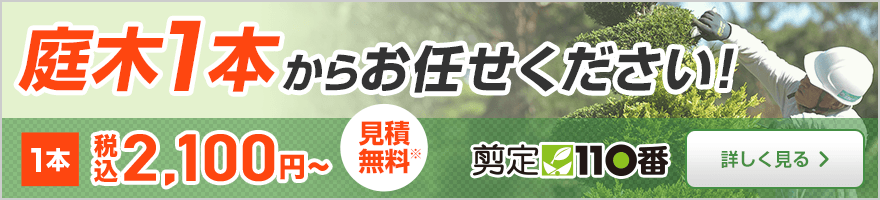ちょっとした垣根から本格的な日本庭園まで、幅広く活躍してくれる杉。少々日当たりが悪くても育つため、園芸初心者の方にもおすすめの木です。
そんな杉の木ですが、大きくなりすぎて剪定にお困りの方も多いのではないでしょうか?神社などには、樹高が数十メートル以上にもなる立派な杉の木がありますよね。このことからもわかるように、杉は剪定をしないとどんどん大きく育っていきます。
そこで当記事では、杉の基本的な剪定方法をご紹介します。定期的に剪定をして適切な大きさに保ちながら、より美しく仕立ててあげましょう。
杉のような大きな木の剪定では、脚立からの転落事故のほか、高枝切りばさみをぶつけて家の屋根を壊してしまったり、切った枝が通行人の上に落ちてしまったりなどの事故が発生しています。
もしご自身で剪定するなら、思わぬ事故が起きないよう、とくに安全に注意して慎重に進めましょう。
自分でうまく剪定できるか不安なときは、プロに依頼するのもおすすめです。とくに、はさみや脚立などの道具を揃える必要があるなら、場合によってはプロに依頼したほうがかえって費用が安くなることもあります。一度見積りを取って比較してみてはいかがでしょうか?
目次
杉の剪定はやり方に応じて季節を選ぶ必要がある
杉は、京都や奈良などの由緒ある寺社にも使われており、日本文化にとって欠かせない木です。その大きな姿は美しくて気高く、信仰の対象にもなるほどです。そのため、寺社では大きな杉の木を大切に剪定しています。杉の剪定の仕方は季節ごとに変わるので、注意が必要です。

基本剪定(3~4月)
木の骨格を整えるため、全体の枝を切っていきます。木への負担が大きいため、木が休眠している冬におこなうのが通常です。しかし杉の場合、5月に新芽が育つため、3~4月に基本剪定をします。そのほうが枝葉をバランスよく育てることができます。
軽剪定(夏や秋)
混みいった枝や弱々しい枝などを切る軽剪定は、日当たりや風通しをよくすることが目的です。日当たりをよくすることで、木全体の葉に日光を当て養分を増やして木を丈夫にすることができます。さらに、風通しをよくすることで木の湿気が減少し、病気や害虫による被害を予防するのです。
台杉仕立ての杉の詳しい剪定方法①枝打ちなどをする
杉はもともと寺社や住居などを建築するため、材木として育てられてきました。しかし、防火やコストなどの面から建築様式が変わり、杉が材木として使われる機会は少なくなっていったのです。
しかし近年では、杉は材木としてよりも観賞用として庭で育てられるようになりました。とくに京都北山の北山杉は、「台杉仕立て」という方法で剪定すると北山台杉と呼ばれる観賞用の杉となり、とても高価です。一般的に台杉とも呼ばれており、穂先、立ち木、取り木、幹で構成されます。そのうち、剪定するのは立ち木と取り木にある枝です。
実は台杉は、実がならない品種であるシロスギを用いるため、花粉がでません。そのため、観賞用として庭に植えても花粉症の心配をする必要がないのです。
では、台杉に仕立てるためにはどのように杉を剪定するとよいのでしょうか?まずは、台杉の立ち木を剪定する方法である、「枝打ち」・「払い枝」・「抜き枝」の3つについて順に見ていきましょう。
枝打ち
立ち木に生えているすべての枝のうち半分から2/3程度を切ります。立ち木の長さに応じて切る枝の数は変わり、長ければ長いほど切る枝の数は多くなります。切るときは、全体のバランスにも注意をします。
払い枝
枝払いともいいます。払い枝のポイントは、切る枝の付け根を残さないことです。残しておくと新しい枝が生え、その枝に養分が吸い取られ、立ち木の成長の勢いが弱くなってしまいます。
抜き枝
抜き枝をするときは、新しい立ち木の成長の邪魔にならないように、古い立ち木の枝を切ります。切るときは枝が生えてこないように、枝の根元から切るとよいでしょう。
台杉仕立ての杉の詳しい剪定方法②取り木を剪定する
先ほども述べましたが、台杉は、穂先・立ち木・取り木・幹で構成されます。そして、幹から取り木が伸び、取り木から立ち木が伸びています。取り木を剪定するときに使う道具は、「剪定バサミ」と「枝打ち鎌」です。剪定バサミで木の芽を切り落とし、枝打ち鎌で枝を切り落とすというように使い分けるのです。
取り木の剪定ポイント
①取り木の中心に近い枝の芽だけを残し、それ以外の芽は切り落とす
取り木の先端の芽を残すと取り木の先から立ち木が生え、その重みで取り木の枝が下がって木全体のバランスが悪くなってしまいます。
②枝を薄く平べったく剪定する
日当たりと風通しがよくなります。日当たりがよくなることにより、木全体の葉に日光があたります。その結果、光合成が活発になって、栄養が木にいきわたり、木が丈夫になるのです。また、風通しをよくすると湿気が減少し、病気や虫もつきにくくなり、木が枯れることを防ぐ効果があります。
台杉の剪定は自分でもできますが、剪定の仕方を間違えると木が弱ってしまうおそれがあります。
杉を育てるうえで剪定以外にも気をつけたいこと
杉は剪定だけでなく、水や肥料のやり方・病気や害虫の対策にも気をつけなければ丈夫に育ちません。気をつけるポイントについて見ていきましょう。
水や肥料のやり方
肥料は、杉が休眠期に入る1~2月に年に1回おこないましょう。栄養を吸収しない休眠期のときに杉に肥料を与えると、吸収されなかった肥料は土のバクテリアなどによって杉に吸収されやすい形に分解されます。分解された肥料は、杉が芽吹くときの3月ごろに杉に吸収されるのです。葉の色をよくするために、使う肥料は有機質のものを使うとよいでしょう。
台杉は根が腐らないように、水はけのよい土に植えます。そして、台杉をしっかり根付かせるために、植えた最初の年だけ土が乾きすぎないように毎日水をたっぷりあげましょう。あげる水の量はバケツ1杯が目安です。
病気や害虫の対策
杉の病気には赤枯れ病などがありますが、病気を予防するために殺菌剤をまきます。殺菌剤をまく回数は年に1,2回程度で十分です。使う殺菌剤の種類は地域によってちがうので、どの殺菌剤を使ってよいかわからないときは専門の業者に相談してみるとよいでしょう。
注意すべき害虫に、スギドクガとスギノハダニがいます。スギノハダニは湿気を嫌いますので、見つけたら水を枝葉にかけましょう。スギドクガは、薬剤で1匹残らず駆除しましょう。1匹でも残すと耐性をもってしまい、薬剤が効かなくなるおそれがあります。
まとめ
かつては、材木用として本州の広い範囲にわたって植えられた杉ですが、近年は台杉を鑑賞用として庭に植える人も増えています。花粉症がひどくなるおそれがあるということで、庭に植えることをためらう人もいるかもしれません。しかし、観賞用の台杉に用いられるシロスギは実をつけないので花粉を心配しなくても大丈夫です。
庭に植えて育てるときに剪定が必要になりますが、台杉の剪定は立ち木と取り木で異なりますし、季節ごとに剪定の仕方もちがってきます。また、植え初めは、たっぷりの水が必要ですし、病害虫対策のために使う薬剤の種類も地域によってちがいます。
大切に育てた高価な台杉を枯らせないようにするためには、剪定・水やり・病害虫対策を正しくおこなうことが必要です。自分で剪定などの管理をするのが難しいかたは、専門の業者に相談してみるとよいのではないでしょうか。
剪定を依頼できる業者や料金
依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「剪定」をご覧ください。
迅速・丁寧に受付対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
庭木が健康に成長するためにかかせないのが剪定です。剪定のプロがお庭や植木の状態を詳しくお調べし、プロの目から見て一番効率の良い最高の剪定方法をご提案します。
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - お庭・樹園、どんな木でも対応。落ち葉、枝、雑草など剪定後の処理もいたします!
-
- 剪定
- 4,000円~/本(税込)
剪定業者を検索
厳選した全国の剪定業者を探せます!