
庭木を育てるなかでの楽しみといえば、その庭木が美しい花を咲かせたり、実をつけるときなのではないでしょうか。庭木を選ぶ際に、ご自身が魅力的に感じる花を咲かせる庭木を選んだというケースも多いでしょう。
そんな、庭木で育てられるなかでも、美しい花を咲かせる植物のひとつが、トサミズキです。トサミズキは、春に薄い黄色の花を咲かせます。
そんなトサミズキを長く元気に育てるには、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。トサミズキの育て方や剪定について、さらには増やし方についてもご紹介します。
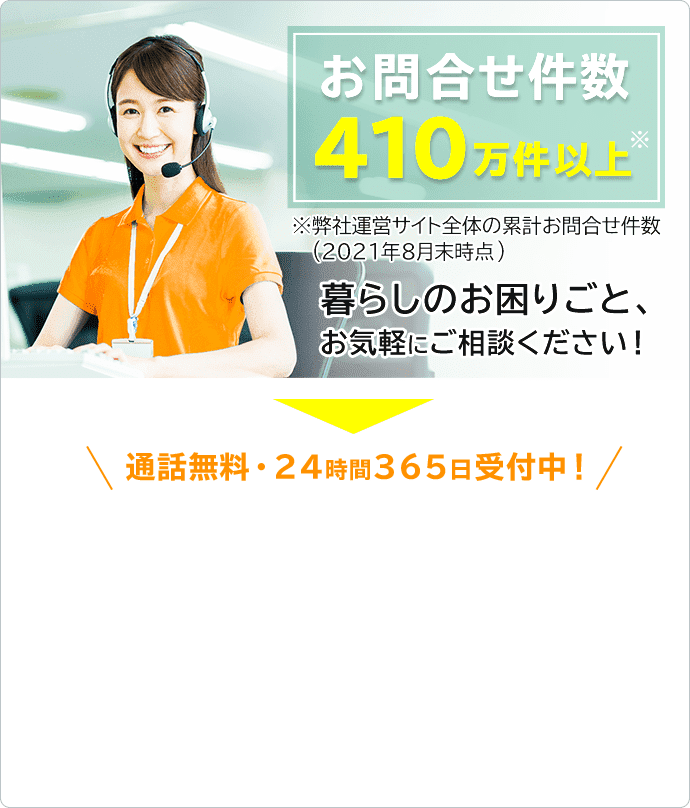
目次
トサミズキは日本が原産の木
トサミズキは、日本の四国地方が原産であるといわれています。3月下旬から4月にかけて、春の陽気が続くようになったとき、薄い黄色の小花を咲かせます。小花が5つほど連なって下に向かって垂れている姿はなんともいとおしく、その魅力に魅せられる方も多いものです。
花が非常に小さいぶん、あまり主張しない質素な庭木ですが、ほかの庭木とのバランスを調和してくれる役割も果たします。その素朴な姿から、生け花や盆栽などにも人気があるようです。
また、トサミズキは寒さには弱い庭木です。寒さが厳しい地域では育ちにくく、雪などが降らない地域でも、冬には室内に入れてあげるのがよいとされています。
若木であれば、特に剪定はいりません。しかし、生長するとその高さは2メートルから高いものだと4メートルにもなります。そのため、剪定をする際には場合によっては業者に依頼する必要もあります。
とはいえ、ほかの多くの庭木とは異なり、大胆な剪定の必要があまりない点も、トサミズキの特徴のひとつです。庭木として育てて盆栽に活かすのもよいでしょう。初心者でも比較的育てやすく、あまり手間がかからないため、庭木を育て始める方にも好まれています。
トサミズキを育てるときに知っておきたいこと
どのような植物にも、その特徴にあった育て方をすることが大切です。トサミズキは、どのような点に留意して育てるのがよいのでしょうか。
まずは、育成環境です。トサミズキは、日当たりのよい場所を好む一方、乾燥を嫌う植物です。西日が当たる場所は乾燥しやすいため、場所には気をつける必要があります。トサミズキは、乾燥にさえ気をつければ初心者でも育てることができます。
土は、できるだけ湿り気のあるものを使用するとよいでしょう。しかし、必ずしも乾燥しやすい土で育たないということもありません。トサミズキを育てるうえで最も注意すべき点は、水やりだといわれています。
土が乾燥している状態で放置してしまうと、枯れてしまいます。そのため、水やりは小まめにたっぷりと行うことがポイントです。土が乾いていると思ったら、すぐに水をあげましょう。
肥料はあまり必要ありませんが、春先に開花した後は少量の油かすなどを施すと安心です。トサミズキは、害虫が付きにくいですが、剪定をしっかり行っていないと、うどんこ病という病気にかかってしまいます。
うどんこ病とは、剪定を行わないことによる風通しの悪化や日当たりが悪いことが原因で起こる病気です。葉に白いカビが生えることが、うどんこ病にかかっているサインとなります。トサミズキが病気にかからないためには、適切な時期に剪定を行うことが大切なのです。
トサミズキにはある程度の剪定が必要
トサミズキは、ほかの庭木のように、ばっさり切り落とすような剪定は必要ありません。しかし、枝や葉が混みあっている部分はしっかりとケアをしてあげる必要があります。
剪定しなかった場合に起こる問題
トサミズキを剪定せずに育て続けた場合、必要以上に大きくなりすぎてしまいます。トサミズキの樹高は、おおよそ2メートルほどが適切です。それ以上大きくならないように剪定します。
また、不必要な部分にまで栄養を取られてしまうため、肝心な部分に養分が十分にいきわたらなくなります。養分が木全体に足りなくなると、枯れるのが早くなってしまったり、寿命を縮めてしまうことにもつながるのです。
せっかくのきれいな花が魅力なトサミズキも、5年ほど放っておいてしまうと、花があまりつかなくなります。庭木を育てるうえで、花をつけなくなってしまうのは、非常に悲しいことですよね。
また、先述したように、剪定を十分に行わないと、うどんこ病という病気にかかり、白いカビが発生します。これは、風の通しが悪くなったことや、日当たりが十分にいきわたらないことが原因で起こります。
うどんこ病は、トサミズキの寿命を縮めてしまうだけでなく、美しさまで奪ってしまいます。多くの植物にとって、風通しのよさと全体に均等に日光が当たるようにすることは、とても重要な条件です。
このように、トサミズキが健康に育つためには、剪定は不可欠なのです。大幅な剪定が必要ないからこそ、ご自身で剪定が可能です。定期的に様子を見て、剪定を行いましょう。
具体的な剪定のやり方
トサミズキには、剪定を行うべき時期があります。多くの植物には、剪定に適した時期というものがあり、これはそれぞれの植物の特徴に沿って決められています。トサミズキは、花が完全に咲き終えた5月から6月までと、葉が落ちている間の11月から2月ごろまでに行います。
トサミズキは、基本的に大幅な剪定は必要ありませんが、しっかりと剪定したい場合は、落葉中である11月から2月に行うようにしましょう。この時期に、枯れている枝や枝が混みあっている部分、不要な太い枝を切り落とします。
混みあっている部分を剪定する際は、できるだけ古い枝を切り落とすようにしましょう。そうすることで、新しい枝がどんどんと生長してくれます。冬の時期に剪定することで、枯れる心配もなく、さらには葉が落ちているため、剪定がしやすいというメリットがあります。
剪定の方法は、まずは不要な古い枝や養分をとってしまう太い枝を根元からしっかりと切り取ります。不要な枝を取り除いたら、伸びすぎていると思う枝を切っていきます。春になり、葉が付き始めると、さらに混みあった印象になります。葉がついても風通しが確保できるように、枝が詰まっている部分は切り落としましょう。
もうひとつ切り落とすべき枝は、太い枝から上に向かってまっすぐのびている枝です。この枝は、徒長枝といい、新芽や花をつけにくい枝であるため、残しておく必要がありません。
花が咲き終わった5月から6月の剪定は、不要だと思う枝だけを切り落とすのみでよいです。この時期に大幅な剪定を行うと、場合によっては枯れてしまうおそれがありますので、注意が必要です。
このように、トサミズキの剪定のチャンスは、1年に2回行い、しっかりとした剪定は冬の落葉している間に行うようにしてくださいね。

トサミズキは自分で増やすことができる
トサミズキの木をもう少し増やしたいと思う方も多いでしょう。育てるのに慣れたら、お庭も華やかにしていきたいですよね。そんなときは、トサミズキを自分で増やすことができるのです。その方法は、3つあります。
・さし木で増やす
1つ目はさし木で増やす方法です。トサミズキをさし木する場合、暖かくなった3月ごろに行うと成功しやすいといわれています。トサミズキのさし木は、木質化していない枝の先端15センチほどを使用します。
剪定に適しているうちでも1月から2月ごろに、枝の先端15センチほどを切ってください。そしてそれを、3月になってから通気性、保水性に富んでいる赤玉土にさしておきます。トサミズキのさし木で重要なのが、とにかく乾燥をさせないことです。おおよそ1か月で根が出ますが、乾燥には常に気をつけておきましょう。
・株分けで増やす
株分けでも増やすことが可能です。どのような場合でもよいわけではありません。根元部分から、若芽が生えている場合のみ、かつ根が十分に発根しているもののみ株分けを行います。
・種まきで増やす
種まきで増やす方法も有効です。トサミズキは、秋になると成熟した種を採取することができます。これを、採取してすぐにまくか、春まで待って春にまきます。採取した種を春まで保管する場合は、種が乾燥してしまわないように注意しておきましょう。
まとめ
トサミズキは、日本で生まれた、素朴でとてもかわいらしい植物です。春に小さな花を連ねて咲かせる姿が印象的ですが、基本的には病気や害虫にも強く、あまり手間がかからないことから、初心者でも育てやすい植物としても知られています。
トサミズキを育てるポイントは、乾燥に注意することです。土が乾いていたら、たっぷりと水をあげましょう。
しかし、適度な剪定も必要です。必要以上に背が高くなってしまわないように、また葉や枝が混みあってしまわないように、注意しましょう。
また、トサミズキは、ご自身でトサミズキを増やすことができるのも、嬉しいポイントです。乾燥をさせないようにして、さらに剪定を適度に行い、春にきれいなトサミズキの花を見られるとよいですね。
剪定を依頼できる業者や料金
依頼できる業者や料金について、詳しくは「生活110番」の「剪定」をご覧ください。
\ 完全無料 /
厳選した全国の剪定業者を探せます!
×
関連記事カテゴリ一覧
剪定の記事アクセスランキング
剪定の最新記事
カテゴリ別記事⼀覧
- お庭の手入れ
- 害虫駆除
- 害獣駆除
- 電気工事
- 鍵開け・交換・修理
- 窓ガラス修理・ドアノブ修理
- 家の修理
- バッテリー上がり
- ハウスクリーニング
- ペット火葬・葬儀
- 家電修理
- パソコン修理・ネット回線
- 家具・雑貨の修理
- 外壁・屋根工事
- リフォーム
- 防犯カメラ設置
- 盗聴器・その他調査診断
- 便利屋・代行サービス
- 引越し・配送サービス
- オフィス・店舗向けサービス
- その他










