
桐は、昔から庭木として植えられることも多い木です。かつて日本では女の子が生まれると桐の木が植えられ、嫁入り道具のタンスとして加工されるほど身近な存在でした。桐を使ったタンスは肌ざわりがよく、防湿・防虫効果に優れているため、今でも高級家具として重宝されています。
しかし庭木を自分で伐採する習慣が少なくなってきた現代では、どんどん成長して大きくなる桐の木に頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、桐の木を伐採するときの手順や注意点についてご紹介します。伐採を業者に依頼するときのポイントについてもまとめましたので、ぜひご自分に合った方法をみつけてください。
目次
桐の木は早め早めに伐採を検討する必要あり!
邪魔になった桐の木は、早めに伐採をしたほうがよいといわれています。まずは、伐採したほうがよい理由についてみていきましょう。

20年で10mほどまで高くなる
桐は成長が早く、大木になりやすい木です。20年かけて10mほどまで成長していきます。成長が早いことから材木として使用されることが多のも特徴です。しかし、材木などで使用しないのであれば、どんどん成長して大木になる前に伐採したほうがよいでしょう。
雑草だと思っていたら桐の木だったことも…
桐の種子には翼がついているため、風に乗って広がりやすく、気づかないうちに庭や軒下に芽を出しているということもあります。雑草だと思って放置をしていたら桐の幼木で、気づいたときには大木になっていた、ということもあるようです。
高さが低いうちに伐採に取り掛かることが大切
大きく太くなった桐の木を伐採することは、とても難しくなります。高い木や太い木を伐採するには、時間や労力がかかるだけでなく、思わぬ方向に木が倒れたり、枝が落ちてくるとケガをするおそれもあるためです。
桐は成長早く、気づいたときには大木になっているということも少なくありません。桐を伐採するときには、木の高さがまだ低いうちにおこなうとよいでしょう。
桐の木を伐採するとき気を付けたいこと
桐の木を伐採するときに、ただ切るだけではいけないようです。労力が無駄にならないよう、伐採するときのポイントについてみていきましょう。
作業中に倒れないよう細心の注意を
桐の木は柔らかくて軽いことが特徴です。強度が低いため、伐採している途中で思ってもみない方向へ倒れてくるおそれがあります。桐の木を伐採するときにはロープを使用するなどし、倒れる方向に注意しながらおこないましょう。

根まで枯らす・除去する必要がある
桐は生命力が強いため、伐採だけしかおこなわないと切り株からまた成長することがあります。また、切り株をそのまま残しておくと、シロアリなどの害虫の住処になるおそれがあるのです。根が残っていても成長してしまうので、桐の木を伐採するときには抜根までおこない、地中の根もすべて枯らしたほうがよいでしょう。
太く生長した桐は業者に依頼を
太く成長した桐を自分で伐採するのは危険が伴います。予想していない方向に木が倒れてきたり、枝が落ちてきたりしてケガをするおそれがあるためです。
桐の幹には細い空洞があります。年数が経った木や枯れてしまった木は空洞が広がりやすく、わずかな衝撃にも耐えられず倒れてしまうことがあるのです。大きく成長した桐の木の伐採は、業者に依頼したほうが安心といえるでしょう。
根まで枯らす!桐の木の伐採方法のすべて
伐採をおこなうときには、必要な道具を揃えなければなりません。作業手順も把握しておいたほうがよいでしょう。ここでは、桐の木の伐採方法についてご紹介します。
伐採に必要な道具を準備しよう
・ノコギリ、チェーンソー
・ロープ
・スコップ
・軍手
・防護服、防護メガネ
・除草剤
伐採にはノコギリやチェーンソーを使用します。誤った方向に木が倒れないよう、倒す方法を補助するためのロープも用意しましょう。ノコギリやチェーンソーを使用していると、木くずが飛んでくることがあります。ケガをしないよう防護服や防護メガネの着用をしましょう。
抜根するときにはスコップを使用します。地中に残った根を枯らすために、除草剤も用意しておきましょう。

桐の木の伐採手順
伐採するときには、木の倒れる方向を決めます。倒れる方向を決めておかないと、周りにいる人や建物のほうへ倒れてしまい、ケガや破損などのトラブルが起こるおそれがあるためです。
倒す方向を決めたら、伐採をしていきます。伐採をするときには、根の上10cmほどを残し、「受け口」と「追い口」のふたつの切り込みを入れます。根の上10cmほどを残す理由は、抜根するときに切り株を抜きやすくするためです。
まず、倒したい方向に受け口を作ります。受け口は、30度~45度のくの字形になるよう、幹の3分の1くらいまで切り込みを入れるとよいでしょう。受け口ができたら、反対側に追い口を作ります。追い口は受け口の3分の2のくらいの高さに、水平に作りましょう。例えば、受け口の高さが30cmとすると、追い口を入れる場所は受け口の上から10cm下のところです。この際、受け口と追い口との間が幹の直径の1/10くらいになるように注意しましょう。
切り込みを入れたら、追い口から受け口の方向へゆっくりと押すと木が倒れます。木を倒すときにはロープを木に巻き付けておくと倒したい方向に倒すための補助となります。思いがけない方向に倒れてケガをする危険性があるため、ロープを使って倒れる方向への補助をしましょう。
根までしっかり枯らす
伐採をしても切り株をそのまま残しておくと、再び成長することがあります。そのため抜根をおこないましょう。抜根しやすくするために切り株にドリルで穴をあけ、穴にグリホサート系の除草剤を注入して根まで枯らします。
根まで枯らしたら、切り株の回りをスコップで掘っていきます。切り株を抜きやすくするため、木の周囲全体を掘るようにしましょう。
切り株が抜けそうなところまで掘り進めたら、切り株を揺らしながら抜きましょう。
桐の木の伐採を業者に依頼すると?
自分で伐採できる木の大きさは、高さ3m未満、太さ20cm未満までのものといわれています。それ以上大きなものになると、伐採するのに危険が伴うためです。桐の木の伐採や抜根を依頼したときにも木の高さや太さ、伐採する場所によって費用が異なります。ポイントごとにみていきましょう。
確認ポイント1:木の高さ
伐採を業者に依頼すると、木の高さによって費用が異なります。3m未満の木であれば3,000円~5,000円、3m~5mだと15,000円~20,000円、5m以上の高木であれば25,000円~30,000円ほどが費用相場となります。
確認ポイント2:木の太さ
抜根を依頼するときには、木の太さによって金額が異なることがあります。直径30cm未満のものであれば、3,000円~6,000円ほどが相場となります。大きく成長し、直径が30㎝以上のものになると25,000円以上となることもあるようです。
確認ポイント3:倒す場所があるかどうか
木が生えている場所によっても金額が異なることがあります。伐採する木を倒す場所があるかどうかによって伐採方法が異なるためです。
建物・電柱・電線などがあるため倒す場所がない場合、重機を使用することがあります。重機を使用すると、50,000円~150,000円ほど伐採費用に追加されることがあるので、業者に依頼するときは重機を使用するかどうか確認するとよいでしょう。
一度見積りを出してもらうことが大切
伐採にかかる費用は、木の高さや太さ、場所によって異なり、高い木や太い木のほうが金額も高くなります。桐の成長は早く、なにもしないと10mほどまで成長してしまうため、業者に依頼するのであれば、早めのほうがよいといえるでしょう。
状況によって費用が異なるため、伐採を依頼する前には見積りを出してもらうことが大切です。作業内容の中に、伐採や抜根だけではなく、木の処分や木を枯らすための除草作業まで入っているかなども確認しておくとよいでしょう。
合わせて見積り金額の内訳についても確認しておきましょう。たとえば木の処分までしてもらう場合、見積り金額には伐採費用だけ記載されており、処分費用は別で請求されてしまったなどということがあるとトラブルになりかねません。このようなトラブルを防ぐためにも、作業を依頼する前の確認が大切です
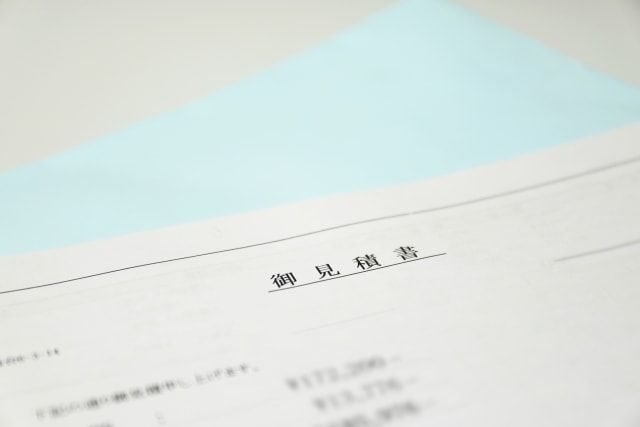
まとめ
桐の木は成長が早く、気づいたときには大木になっていたということも少なくありません。桐の木の伐採や抜根を自分でおこなうこともできますが、時間や労力がかかります。また大きく成長した木であれば、作業中にケガをするおそれがあるなど、危険も伴うでしょう。
自分で作業をおこなうことに少しでも不安がある場合は、業者に依頼することがおすすめです。業者であれば、知識や実績があるため、しっかりとした作業をしてくれることでしょう。
伐採や抜根は、木の高さや太さによって費用が異なるため、業者に依頼するときにはなるべく早くしたほうがよいといえます。弊社であれば無料でお見積りもしております。お気軽にご相談ください。
伐採のプロが迅速対応!
庭木1本からお任せください!
※対応エリアや加盟店によって変わります
木々の伐採は大きな木であればあるほど、危険度が上がってきます。自分で伐採したら電線に引っかかってしまった!なんて事がないように、安全のためにも伐採はプロにお任せしましょう!
- 『生活110番』では、
お住いの地域で人気のプロを探せます - 立ち合いがなくとも作業は可能です!お気軽にご相談ください。
-
- 伐採
- 8,200円~/本(税込)
伐採業者を検索
厳選した全国の伐採業者を探せます!

