
ある日ふと米びつの中を見てみると、真っ白いお米の中でうごめく小さな黒い影。どこから入り込んだのか、「コクゾウムシ」が住み着いてしまっていることがあります。
コクゾウムシは身体が非常に小さいうえにお米の内部に卵を産み付けるため、日ごろ確認していても見逃してしまうことが多いです。気づいたときには、お米を食い荒らされてしまっているケースも珍しくはありません。
そのままコクゾウムシごと炊いて食べても害はありませんが、せっかくの白いお米に黒い点々が混じっていたら食欲も落ちてしまうのではないでしょうか。日本人の食生活に必要不可欠なお米をおいしく食べるためにも、今日からできるコクゾウムシ対策を始めていきましょう。
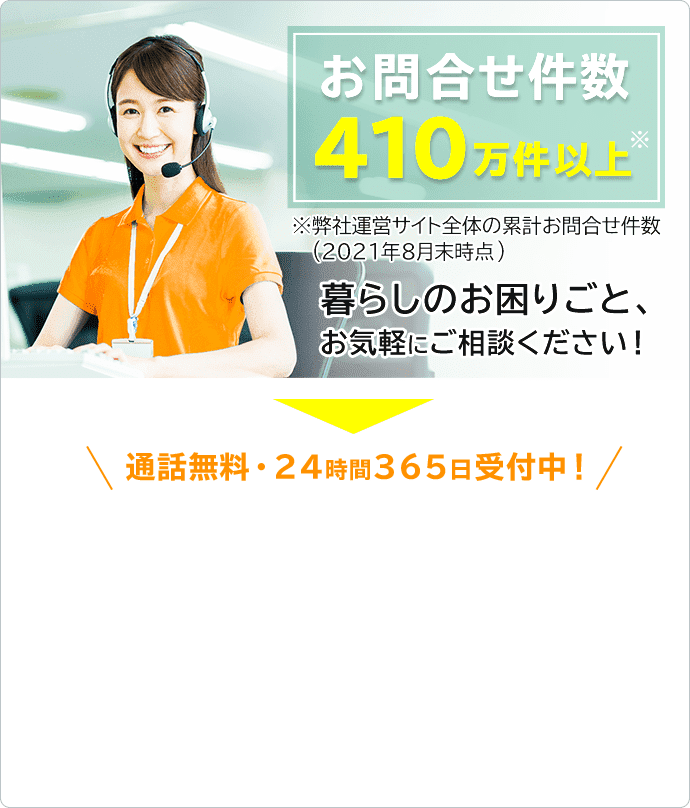
目次
コクゾウムシの生態
まずは大前提として、普段目にすることはあってもまじまじと見つめることはあまりない、「コクゾウムシ」という害虫がどんな虫なのかについて簡単にご説明いたします。
◆外見
コクゾウムシは漢字で書くと「穀象虫」となり、字面からわかるとおりゾウの鼻のように長い口吻(こうふん)をもった「ゾウムシ」と呼ばれる種類の昆虫の仲間です。口吻はいわばクチバシのようなもので、非常に硬くするどい特徴をもっています。
コクゾウムシはこの口吻で硬い生米にも難なく穴をあけ、米の内部に卵を産み付けます。卵からかえった幼虫は米を中から食い荒らして成長し、やがて黒い成虫となって別の米に卵を産み付けていきます。
体長は大きいものでも3.5mm程度と非常に小さく、幼虫は米に収まるサイズでさらに小さいため、米びつをパッと見ただけではなかなか見つけづらいというのが厄介なところです。
成虫は体色が黒いため、白いお米の中にいると非常に目立ちますが、卵と幼虫は白く米に紛れる色をしているうえに米の中に住んでいるため、米一粒一粒を手にとってみないと住んでいるかどうかが判別できません。
甲虫類特有の硬く光沢のある外皮をもち、軽い身体に力の強い翅をもっているため飛行能力が非常に高く、エサとなる米を求めて長距離を移動することが可能です。
◆生息場所
コクゾウムシの主な生息場所は草むらや水田、民家や農家に貯蔵された米の中です。エサとなる米が大量に貯蔵された米びつはコクゾウムシにとってまさに楽園のようなもので、ほうっておくとあっという間に繁殖して米びつの中身を平らげてしまいます。
コクゾウムシのメスは一生に200個から300個の卵を産むとされています。さらに、米が保管されている場所というのは人間の生活圏に近いため暖かいことが多いです。そうなると米びつの中で越冬ができてしまうため、コクゾウムシにとって繁殖しやすい条件がそろっているともいえます。

◆発生時期
コクゾウムシは越冬する虫なので年間を通して見られますが、寒さに弱いため冬場は樹皮の隙間などの寒さを防げる場所でじっとしています。活発に動き始めるのは春になってからで、春先から秋の終わりまで活動しています。
気温の低い時期は動き回ることがなく、冬場に米びつにやってくることはそうそうありません。そのため、米びつにコクゾウムシが沸く時期は4月から10月までの間となります。
ただし、お家のリビングなどに米びつを置いていて冬場も暖房で暖かく保たれているとすでに住み着いているコクゾウムシは活動と繁殖を続けている場合があります。
◆餌
コクゾウムシはその名のとおり、穀物をエサとする虫です。食害する対象は米だけに限らず、トウモロコシや小麦といった穀物全般を幅広く食い荒らします。
なかでもとりわけ、「どの家庭にも貯蔵されている」「精白(もみ殻やヌカを取り除くこと)されている」「暖房などで暖かい場所が多い」といった特徴から、コクゾウムシは米を食害することが多いです。
一昔前までは、コクゾウムシが沸くということは農薬や殺虫剤を使われていないということなので安全なお米である、という論調もありました。確かにそれは一つの見解として間違ってはいないのですが、殺虫剤などに頼らずともコクゾウムシを追い出す方法はいくつもあります。
コクゾウムシは米の中心部、つまり味の良し悪しに大きく関わる部分を食い荒らします。そのため気分の問題を度外視しても、コクゾウムシの沸いた米より沸いていない米のほうがおいしいということは間違いありません。コクゾウムシ対策はおこなっておいて損はないでしょう。
◆口吻(こうふん)
コクゾウムシのもっとも大きな特徴といえば、やはり頭部の二倍近い長さをもつ口吻です。コクゾウムシの口吻を振るう力は強く、乾燥して非常に硬くなった米にも、たやすく穴をあけてしまいます。
口吻は鳥でいうところの「くちばし」のような器官ですが、コクゾウムシの口吻は長く伸びた「先」に口があります。米に開けた穴に口吻を突っ込み、先端から米の中身を食べることが可能です。そのためコクゾウムシに食害された米は、小さな穴が空いて中身だけが綺麗にくり抜かれているといった特徴があります。
この口吻は産卵の際にも便利に使われ、米の中心部まで届くような穴をあけて、そこに卵を産み付けることで、米の内部で幼虫が孵化できるようになっています。幼虫は米を食糧兼ゆりかごとして育ち、成虫になるころに米の外皮を食い破って出てくるわけです。

コクゾウムシはどこからやってくる?
いつのまにか米びつの中に発生しているコクゾウムシですが、なにもないところから突然出現するわけではありません。コクゾウムシの発生には、かならずコクゾウムシが入り込んだルートが存在します。
コクゾウムシの侵入ルートについては、代表的なパターンが2種類あります。
◆お米についてくる
購入したお米に初めからコクゾウムシが入り込んでいたパターンです。コクゾウムシの成虫が住み着いていたケースと、成虫はおらずとも卵を産み付けられた米が混入していたケースがあります。
コクゾウムシは一般家庭のほかにも、農家の倉庫で出荷を控えている米の袋に侵入することがあります。米を大量に保管しており、農業機械の排熱などで暖かいことの多い倉庫は、コクゾウムシが入り込みやすい場所とされています。
また、水田で収穫される前の「稲」の段階のお米にコクゾウムシがとりついている場合もあります。とくに無農薬栽培をされている水田では、実っている稲はコクゾウムシに対してほぼノーガードなので、収穫時に成虫を取り除けても卵が残ってしまっているおそれがあります。
前項でもご紹介したとおりコクゾウムシの卵は米の内部に産み付けられるため、収穫した米を精白したとしても、中央部の卵まで取り除くことは難しいとされています。卵の状態で出荷待ちの米の中に紛れ込んでしまうと、どれだけ外からの侵入をシャットアウトしても袋の中で繁殖されてしまいます。
◆米びつの外から入り込む
多くのご家庭では、購入してきた米を保管するのに米びつを使います。米びつは毎日開け閉めするものなので、料理の際や米びつの隙間などからコクゾウムシが入り込んでくる可能性があります。
コクゾウムシはするどい嗅覚をもっており、かなり遠くからでも米の匂いを嗅ぎ付けてやってきます。精白された米は特有のヌカのような香りを放っているため、米びつのフタをしっかり閉めていてもコクゾウムシに勘付かれてしまうことがあります。
コクゾウムシは非常に小さな虫なので、家庭の米びつで完全に侵入を遮断することは難しいとされています。コクゾウムシを寄せ付けないためには、物理的な遮断よりも別のアプローチが必要になるかもしれません。

お米のコクゾウムシを取り除く方法
一度コクゾウムシが沸いてしまったら、手で一匹一匹取り除いていくのは気の遠くなるような作業です。成虫であれば見分けもつきますが、幼虫や卵を完全に見分けて除去することはほとんど不可能といっていいでしょう。
では、コクゾウムシが沸いてしまったら米びつの中身を捨てない限りコクゾウムシを食べない方法はないのでしょうか。実は、より簡単な方法でその日食べる分の米からコクゾウムシを取り除くことができるのです。
◆ゆっくり研いで水に浮かべる
コクゾウムシは水に浮きます。これは成虫にも幼虫にも、卵にもいえる特徴です。そのため、米を研ぐ際にゆっくり丁寧に、米全体を水ですすぐようにかきまわし、しばらくおいておくと、米から出てきたコクゾウムシが水面に浮かんできます。
また、コクゾウムシに食い荒らされてしまった米も、中身が空洞になっているため水に浮きやすくなっています。コクゾウムシと一緒に浮かんできた米があったら、中がスカスカになっていることや卵が入っているおそれがあるので、この時点で捨ててしまっても大丈夫です。
◆まんべんなく日光を当てる
コクゾウムシは臆病な性質の生き物で、また光に対して反応を示す習性をもっています。この性質を利用し、米に光を当てることでコクゾウムシを米から追い出すことが可能です。
光を使う場合は、すべての米にまんべんなく光があたるよう、ブルーシートや新聞紙などに米を広げて日中にさらしましょう。数時間ほどであらかたのコクゾウムシが米から逃げていきます。
この方法は行動力の高い成虫に有効です。幼虫や卵は米から出られない場合が多いため、米びつから完全にコクゾウムシを排除するためには、幼虫が成虫になるタイミングを狙って何度か光にさらす必要があります。
また、直射日光に当たり続けると米は品質が低下してしまい味も落ちてしまうため、夏場など日差しの強い季節は日干しではなく陰干しするようにしましょう。

コクゾウムシを増やさない予防法
外から入り込んでくるコクゾウムシを完全に予防することは難しいですが、今住み着いているコクゾウムシをこれ以上増やさないように対策を施すことは可能です。
◆温度の低い場所に保存
コクゾウムシは寒さに弱く、気温が18℃を下回ると途端に動かなくなります。そのため、20℃以下の寒い場所に米びつをおいておくだけでも十分にコクゾウムシ対策になります。
ただし、日本の環境下ではコクゾウムシのもっとも活発になる夏場に18℃以下の保管場所を用意することは難しいため、冷蔵庫や冷凍庫を利用することも一つの手段となります。15℃以下になると卵が孵化することもないため、米を小分けにして冷蔵庫に入れておくとコクゾウムシが繁殖しません。
また米びつの中には、内部の温度を低温に保つ保冷機能付きのものも市販されていますので、そういった設備を導入することも有効な対策になります。
◆唐辛子を米びつに入れておく
唐辛子に含まれる「カプサイシン」という辛み成分には虫避けの効果があります。古くから唐辛子を畑で一緒に育てると虫がつきにくくなるという効果は利用されていました。
同様に、唐辛子を何本か米びつに放り込んでおいても防虫効果を発揮します。また唐辛子は食べ物ですので、米と一緒に入れておいても安心という点でも優秀です。
このとき気を付けておくべきことは、唐辛子は完全乾燥したものを使うことと、あらかじめヘタは取り除いておくという点です。生の唐辛子には雑菌やカビが住み着いていることがあり、とくにヘタの部分は乾燥していてもカビの胞子が付着していることがあります。
「鷹の爪」として市販されているような乾燥した唐辛子を、米10kgに対して5本程度入れておくのが適量とされています。
また、市販されている米びつの防虫グッズには、唐辛子の成分を抽出したものも多くあります。これらの防虫グッズを利用するのも有効です。

コクゾウムシ予防に役立つグッズ4選
コクゾウムシを米びつから追い出すために便利な防虫グッズをいくつかご紹介いたします。
エステー 米唐番(こめとうばん) 10kgタイプ お米の虫よけ
唐辛子の防虫成分を抽出したゼリータイプの米びつ防虫剤です。米びつに入れた米の上に置いておく、あるいは米に刺しておくといった使い方で、長いものでは数か月間コクゾウムシを防いでくれます。内部のゼリーの減り具合で交換時期がわかりやすいのも魅力です。
レック 最強米びつくん
唐辛子と同じように防虫効果をもつワサビの成分を使った防虫剤です。こちらは米びつの内側の壁やフタの裏側に張り付けておくタイプで、最長で半年と長く効果を発揮してくれます。また米の量も40kgまで防虫可能と強力なパワーをもっています。
アスベル 密閉米びつ2kg ホワイト 7509
こちらはコクゾウムシに対して有効な「米びつ」です。ゴムパッキンによってつねに密閉状態にあるため、小さなコクゾウムシであっても入り込むことができなくなっています。また小型なため、冷蔵庫に保管することで卵や幼虫が紛れ込んでいても繁殖することができなくなります。
エムケー精工 保冷米びつ Cool Ace
コクゾウムシが活動をやめる15℃にお米の温度を保ち続けてくれる、保冷機能つきの米びつです。夏場であっても15℃を維持できる冷却性能をもち、さらにパッキンつきのフタで外からのコクゾウムシの侵入も防ぎます。計量機能があるのも便利です。
コクゾウムシを食べてしまったら大丈夫?
どれだけ細心の注意をはらって取り除いたとしても、米の中に隠れ続けている幼虫や卵、こちらの目を逃れた成虫などが紛れ込んだまま炊飯してしまうことがあります。白米と一緒に炊きあがってしまったコクゾウムシは、食べても大丈夫なのでしょうか。
コクゾウムシ自体に毒はなく、雑菌も炊飯の際に熱で死ぬため、そのまま食べてしまっても健康に影響はありません。成虫も幼虫も同様で、身体に害はありません。
しかし、米自体のおいしい部分が食い荒らされているうえに、コクゾウムシは甲虫なのでプチプチとした嫌な歯ごたえがあります。コクゾウムシに味はありませんが、できる限り虫は食べたくないものです。
まとめ
コクゾウムシは、お米を主食とする日本人の食生活において、切ってはなせない害虫であるともいえます。どこからでも入り込み、知らない間に繁殖しているので、気づけば米びつが真っ黒ということも珍しくありません。
食の根幹となるお米に関わることですから、決して妥協せずしっかりとした予防と駆除でコクゾウムシを追い出し、白くおいしいお米の味を楽しみましょう。
コクゾウムシ対策は難しくはありませんが、どうしても追い出しきれないといった場合は、害虫駆除業者に依頼することも一つの手段です。経験豊富な業者の手腕で、清潔安全な食生活を取り戻しましょう。
\ 完全無料 /
厳選した全国のダニ・ノミ・トコジラミ駆除業者を探せます!
×
関連記事カテゴリ一覧
ダニ・ノミ・トコジラミ駆除の記事アクセスランキング
ダニ・ノミ・トコジラミ駆除の最新記事
カテゴリ別記事⼀覧
- お庭の手入れ
- 害虫駆除
- 害獣駆除
- 電気工事
- 鍵開け・交換・修理
- 窓ガラス修理・ドアノブ修理
- 家の修理
- バッテリー上がり
- ハウスクリーニング
- ペット火葬・葬儀
- 家電修理
- パソコン修理・ネット回線
- 家具・雑貨の修理
- 外壁・屋根工事
- リフォーム
- 防犯カメラ設置
- 盗聴器・その他調査診断
- 便利屋・代行サービス
- 引越し・配送サービス
- オフィス・店舗向けサービス
- その他













