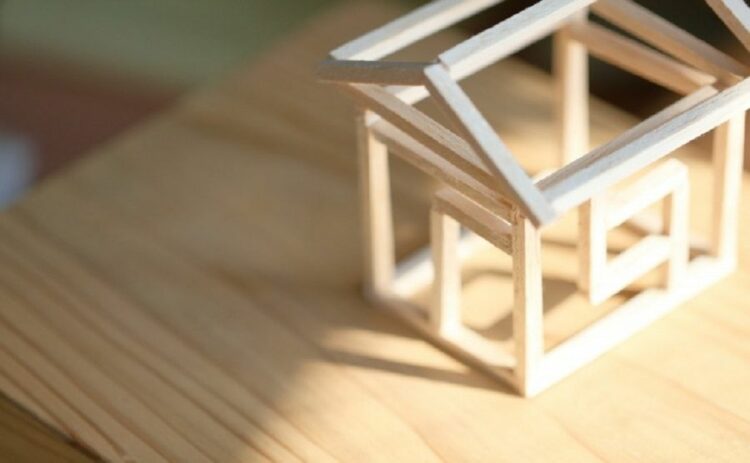
今住んでいる自分の持ち家が地震のゆれにどれくらい耐えられるのかを知っておくことは大事です。どれくらい耐えられるのかを知っておくことで、必要な耐震工事の程度を判断することができるからです。
自分の持ち家が木造住宅である場合、地震の強いゆれに耐えられないのではないかと不安に思っている方もいらっしゃるでしょう。木造住宅は鉄筋の建物にくらべて軽そうなので地震のゆれに弱いと思われがちですが、軽いほうが地震に強いこともあるのです。
今回は木造や鉄筋を比較した家の重さのちがいや、強度についてご説明します。ご自身が住む家の耐震性を知れば、地震に強い家へより対策がしやすくなるでしょう。
目次
家の重さはこれくらい
自分の家の重さがどのくらいであるか、考えたことがない方も多いのではないでしょうか。家の重さは地震のゆれへの強さにかかわるものです。ここでは一般的な2階建て木造住宅を例にあげて家の重さについてご説明します。
家の重さの目安
建物の種類は大きく分けて、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の3種類の構造があります。木造の家は、家の構造部分に木材を使っていて、日本の住宅の8割が木造です。鉄骨造りの家は、構造部分に鉄筋とよばれる鉄でできた芯材を使用しています。鉄筋コンクリートは、鉄筋とコンクリートを両方使用してるもので、RC造りともいわれます。
こちらは住宅全体の面積である延床面積約30坪(各階約15坪=50平方メートル)当たり、建物の重さの目安です。
木造2階建て 約30トン
木造3階建て 約45トン
鉄骨2階建て 約37.5トン
鉄筋コンクリート2階建て 約160トン
このように、おなじ約30坪の面積でも、木造と鉄筋コンクリートを比較すれば、5倍以上の差があるのです。住居用であるのか、または事務所なのか、店舗として使うのかによっても家の重さはことなります。

家の重さの内訳
建築面積が30坪(各階15坪=50平方メートル)である2階建ての平均的な木造住宅は約30トンですが、その内訳については、「固定荷重」「積載荷重」がかかわっています。さらに家の土台である基礎部分を含めると、家はさらに重くなります。
屋根や外壁、柱、窓などの建材を「固定荷重」といいます。固定荷重に加えて、人、家具、荷物をどれだけ載せられるか、建築基準法で最小値が決められているのが「積載荷重」です。
積載荷重は住宅用や事務室用など、その部屋の用途によって最小値はことなりますが、住宅用は1平方メートルあたり、約180㎏以上載せられるように設計するきまりがあります。
住宅には通常、コンクリートの基礎があります。一般的な住宅のコンクリート基礎(50平方メートル)は、約20トンです。つまりコンクリート自体の重さ(約20トン)を上回る家の重さ(約30トン)を、コンクリートの基礎がささえているということになります。
家の重さと耐震性
一般的な2階建て住宅の重量がわかったところで、つぎに家の重さと耐震性の関係を見ていきましょう。木造住宅は、鉄骨やRC造りにくらべて地震のゆれに強いのですが、これは材質や家の重心がかかわっているためです。
家は重いほど地震に弱い
地震のエネルギーは、建物の重さに比例してはたらきます。建物が重ければ重いほど、地震のゆれが伝わりやすいのです。つまり、木造、鉄骨、RC造りの3種類の中では、木造がもっとも地震のゆれが少なくなります。
屋根や2階が重いとゆれが大きくなる
地震のときにタワーマンションの高層階がゆれやすいといわれていますが、木造住宅でもおなじことがいえます。これは、重心が上にあるほど、建物がゆれやすくなるからです。
2階建ての木造住宅は、頭にフロア1層分を載せているので、平屋住宅よりも重心が高くなります。そのため、地震でゆれやすいのです。
木造住宅の家の重さは、屋根の重量が大きくかかわります。これは、屋根が家の上部にあるため、重心が上になるためです。屋根が重ければ重いほどゆれやすくなります。屋根を軽量瓦や軽量のスレートにすると、家がゆれにくくなります。
2階部分に大きな家具を置かないようにすることも対策になります。ピアノや箪笥などは、できれば2階に置かないようにして、1階に置くとよいでしょう。1階に重いものを置くと、家の重心を下げられます。

基礎と地盤について
木造住宅は比較的地震のゆれに強いものの、家だけ対策をすれば十分ということではありません。基礎工事と地盤調査をやって、はじめて耐震性が高い家づくりができるのです。
基礎の役割と種類
住宅はきちんとした構造の家があってこそ、地震に強いといえます。しかし、構造がしっかりとした家を建てるには、その家の下にある基礎が家の重さをささえられるほど丈夫でなくてはいけません。
多くの住宅の基礎工事でおこなうのが、地中にくい打ちなどをせずに基礎を敷く「直接基礎」です。直接基礎には、「ベタ基礎」「布基礎」などの種類があります。
布基礎は、逆T字の形をした鉄筋コンクリートを壁の下にのみ敷いて作る基礎で、日本の多くの住宅で使われています。部分的に敷かれているため、使う鉄筋コンクリートの量が少なく、ベタ基礎よりも低コストで工事が可能です。
ベタ基礎は、建物が地面に接地する部分すべてに鉄筋コンクリートを敷く基礎のことです。重い建物や地盤が軟弱である場合は、ベタ基礎の工事がおこなわれます。

地盤の重要性
いくらしっかりとした構造や基礎の家であったとしても、ささえる地盤が弱ければ、耐震効果がなくなってしまいます。地盤が弱いと地震のときに地盤沈下を起こし、家が傾いてしまいます。基礎工事とあわせて、地盤調査をしておくことも大切です。
20年前に建てられた中古住宅は、地盤調査をせずに建てられたものも多くあり、地盤がゆるい場所であるかもしれません。中古住宅を購入する場合も、地盤調査をすることをおすすめします。
耐震診断で耐震性をチェックしよう
木造住宅の重量や基礎、地盤が耐震性に大きくかかわることがわかりました。そこで気になるのは、家や基礎などが家の重さをささえられるほどの強度があるかどうかです。耐震診断をして、地震のゆれから守ってくれるかどうかの耐震性を調べてみましょう。
耐震診断で見る項目
耐震診断の流れとして、「予備調査」「1次調査」をおこないます。必要に応じて実施するのが「2次調査」「精密診断」です。
まず予備調査では、調査する建築物の概要を確認します。図面の有無、関係資料の有無、新築からの履歴を大まかに把握します。そして1次調査でおこなうのが、実際に現地で建物の外観やコンクリートの強度を調べる耐震診断です。
建築物にひび割れや変形などを確認したときは、2次調査をおこないます。ひび割れが構造によるものか、乾燥によるものか、などを現地で実際に調査するのです。精密検査は2次調査よりもさらに詳細な調査をします。
耐震診断の費用
木造住宅の耐震診断料金は、延床面積が120平方メートルの建物で、約20万円~50万円です。ただし、建築図面がない場合は復元する必要がありますので、さらに料金が高くなることがあります。
耐震基準を満たしていない建築物は、耐震改修促進法における認定を受けると、耐震改修工事費用の補助金が受けられる可能性があります。地方自治体により、対象となる条件はことなりますので、事前に窓口へ相談することをおすすめします。

まとめ
地震が起きたとき、家の重さが鉄骨やRC造りのものにくらべると木造の方が軽いため、ゆれに強くなっています。ただし、木造であることだけでは、地震に強いとはいえません。家の構造や基礎の強度、地盤の固さなども大きくかかわってきます。
家や基礎などを総合的に見て、本当に耐震性があるかどうかがわかるのが耐震診断です。専門家が図面の確認や現地を実際に見て調査をします。
もしご自宅の耐震性に不安がある場合は、耐震診断をしてみましょう。はやめに対策をすれば、万が一に大きな地震が発生しても、被害を最小限にとどめることができるかもしれません。

