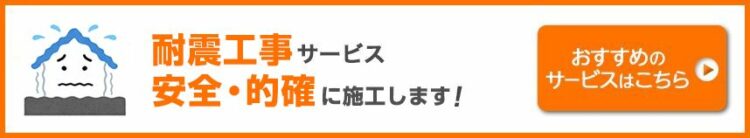地震の揺れは、さまざまですよね。そのなかでも直下型地震の揺れ方はどんなものだと思いますか?
このコラムでは、直下型地震の揺れ方の特徴や、発生したときの被害想定などを紹介しています。さらに、直下型地震が発生したときのために、おこなっておきたい準備も同時に紹介しています。
地震大国日本で地震への備えを考えている方は、このコラムを読んでいただき、いつ起こるかわからない地震への対策を検討していただければ幸いです。
目次
突然大きな揺れが…直下型地震の揺れ方の特徴について
地震が発生したとき、直下型地震と呼ばれるものがありますが、この直下型地震はとても危険だといわれています。
直下型地震がなぜ危険なのか?それは、地震の発生状態によるからなのです。直下型地震は、名前のごとく私たちが生活している場所の真下で起こっているのです。
直下型地震の特徴は3つです。
②生活している真下から突き上げてくる縦揺れが発生
③地震が発生した途端とても大きな縦揺れが発生
直下型地震の特徴は上記の3つになります。直下型地震の揺れ方でないときは、「地震かな?あっ!地震だ!揺れてる!」といった徐々に揺れを感じるのではないでしょうか。しかし、直下型地震の場合は、そんなことを感じている余裕はありません。
最近では、地震が起こるまえには、地震速報で「地震がきます」と事前に教えてくれます。しかし、直下型地震は前触れもなく、いきなり「ドン」という音とともに、縦揺れがはじまるため、地震速報を流す暇すら与えてくれることのない地震です。
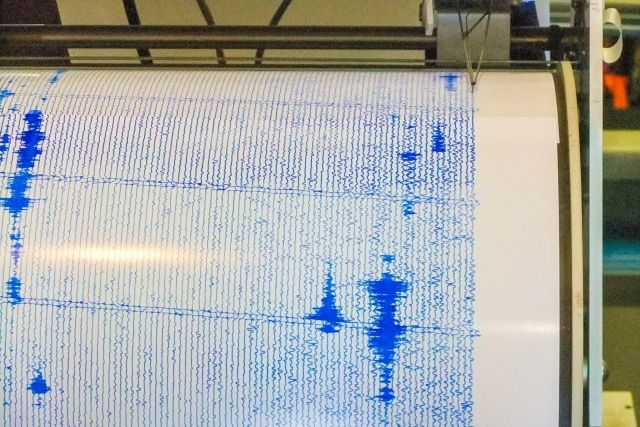
直下型地震が発生したときに想定される被害とは
現在、日本では多くの地震が発生していますが、国は首都直下型地震についての被害想定を発表しています。
この直下型地震が首都で起こったとき、どのような被害が想定されるのか見ていきましょう。
地震による揺れの被害
直下型地震によって、家屋は約17万5,000軒倒壊することが想定されています。また、建物が倒壊することにより救助が必要となる人数は約7万2,000人だそうです。
市街地での火災被害
地震による二次災害として代表的な火災による焼失は、約61万軒と非常に甚大な被害になるでしょう。さらに先ほどの倒壊と火災の犠牲者は合わせて、2万3,000人と予想されています。
インフラやライフライン
電力に関しては、地震発生直後から約50%の区域で停電が起こり、電力供給の不安定さが7日間ほど続いてしまうでしょう。さらに、通信機器に関しては9割が規制状態になると想定されています。
また、上下水道は都心部は約50%が断水して、10%の下水道は使用不可となってしまいます。交通網に関しては、地下鉄は約7日間、在来線は約30日以上使用できないと想定されているのです。
港湾関係は、耐震構造になっていないものを復旧するには30日以上の期間がかかると想定されています。
このように、直下地震が発生したときには多くの被害がでてしまうことが想定されています。直下型地震の揺れ方は、地面からの揺れが近いため、家屋の倒壊被害か多くなると想定されており、倒壊した家屋からの出火などで二次被害がでることも考えられます。
そのため、少しでも被害を食い止めるためには、今から耐震診断をおこない、必要であれば耐震工事をおこなうことで倒壊のリスクを下げておきましょう。

直下型地震以外の地震の種類とその揺れ方
ここまで、解説した直下型地震は内陸地震とも呼ばれています。このほかに、海溝型地震という直下型地震とは揺れ方の違う地震があるのです。海溝型地震の発生メカニズムと揺れ方についてみていきましょう。
海溝型地震が発生する仕組みは、海と陸にあるプレートがずれることで、海のプレートが陸のプレートの下に入ろうとします。しかし、海のプレートが無理矢理入ろうとするため、陸のプレートは拒絶をするのです。
それでも、海のプレートが入りこもうとするため、陸のプレートは我慢の限界に達して、跳ね返ってしまうため、その衝撃で地震が発生してしまうのです。
この地震が発生すると、「なんか揺れてる?」といった小さな揺れからはじまります。そして、大きな横揺れが長い時間続くのが、海溝型地震の揺れの特徴です。
直下型地震に備えて準備しておくべきこと
日本は、地震大国と呼ばれれているくらい、地震が多いです。そのため、直下型地震がいつ発生してもいいように、準備しておくことを紹介します。
まずは、耐震診断というものがあります。この耐震診断は、自分の自宅がどの程度の揺れまでなら耐えることができるのかを知ることができます。この耐震診断は、診断をしてくれる業者に依頼することで、自宅の構造などから弱点を導き出してくれるのです。
この導きだされたことから、耐震の補強工事をおこなうことでさらに強固な準備となります。耐震の補強工事にはさまざまなものがあり、直下地震の揺れ方に耐えられる耐震補強をすることで、直下地震に対して準備することができるでしょう。
耐震補強をおこなうには3種類の方法があります。耐震構造、制震構造、免震構造ですが、それぞれ違いがあるのでご自身の自宅などに適した方法で補強することをおすすめします。
直下地震というものは、いつどんなときに発生するかわかりません。そのため、地震が発生したときのことを考えて、耐震診断や耐震工事をおこなうことで地震に備えた準備をしておきましょう。
さらに、自宅内の家具などは突っ張り棒や家具と壁をボルトで止められるものを使い、転倒防止措置をおこない自宅内での被害を減らしましょう。また、家具の配置などでも工夫をして、転倒したときに入り口がふさがれることのないような配置にするなど、配慮しておきましょう。
まとめ
地震は、いつどんなときに発生するのかわかりません。直下型地震はさらになんの告知もせずにやってくる地震です。
直下型地震は、被害範囲は小さくても揺れた場所での被害は、とても大きくなる可能性があり、建物の倒壊の危険性が極めて高いです。そのため、現在お住まいの自宅がどの程度の揺れに耐えられるのかを診断して、必要であれば耐震工事をするようにしましょう。
耐震工事をおこなうことで、地震が発生しても直下型地震の揺れ方に耐えられる自宅を手に入れることができるでしょう。耐震工事をお考えの方は、業者に依頼して、安心できる自宅にしてみてはいかがでしょうか。