
「もしかしたら家にシロアリの巣(コロニー)があるかも……」そう思ったときは、早めに点検をしておきましょう。シロアリは毎日活動し、大切な建築材を食害してしまいます。万が一本当にシロアリ被害が起きている可能性を考えて行動しておくと、被害を最小限に抑えることができるのです。
そこで今回は、シロアリの巣を発見するために必要な知識と実際に巣を探す方法を紹介します。
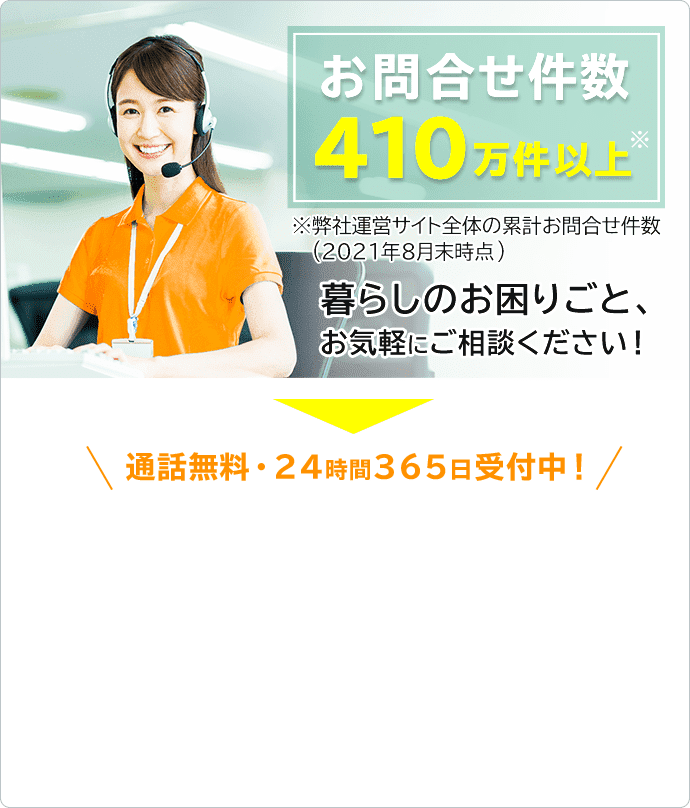
目次
シロアリの巣で知っておきたい知識
シロアリの巣の特徴はシロアリの種類によってさまざま。ただ、家の中を食害する多くのシロアリにあてはまる特徴があるため、先に知っておくと各種類でシロアリの巣の特徴がわかりやすいでしょう。
シロアリが巣を作りやすい場所

家屋の木材を狙う多くのシロアリにあてはまる特徴として「湿気を好み、乾燥を嫌う」というものがあります。そのため、シロアリは基本的に人の見える位置で巣を作ることはなく、暗くてじめじめした場所を好んで巣を作る傾向があるのです。
そのなかでも「住宅の床下」はシロアリにとって絶好の巣作り場所。床下は基本的に風通しが悪く、さらに気候や土壌の影響により湿度が上がりやすい環境になっています。カビも生えやすく、シロアリに限らず害虫が寄ってきやすいため注意してください。
シロアリの侵入経路
「床下の周りはコンクリートで囲んでいるから大丈夫じゃないの?」と疑問に感じる方もいることでしょう。
たしかに現在では、家の土台にあたる「基礎」の部分を硬いコンクリートで覆う「ベタ基礎」や「布基礎」が主流であり、一見侵入できないように思えます。ところが、シロアリは小さい体を駆使してコンクリートの基礎でも侵入することがあるのです。
その原因はコンクリートの劣化による亀裂。シロアリは体長1センチメートルも満たないほど小さな体をしており、わずかなすき間さえあれば侵入することができます。さらに、シロアリは「蟻酸(ぎさん)」という酸性の物質を出すことができ、アルカリ性であるコンクリートに穴を開けて侵入するのです。
羽アリの活動時期は要注意!
シロアリは自然で見かけるクロアリのように「働きアリ・兵隊アリ・女王アリ」といった役割をもつ社会性昆虫のひとつとして知られています。その役割のひとつに「ニンフ」という階級があり、ニンフは成長することで羽をもって巣を探す羽アリへ変化するのです。
シロアリが羽アリになると集団となって空を飛ぶ「群飛(ぐんぴ)」という行動をおこないます。飛んでいった先で羽アリのオスとメスがペアとなり、巣作りをおこなうのです。家の周りに羽アリがあらわれたら、巣を作られる前に対処しなければなりません。
種類によって異なりますが、羽アリの群飛時期は春~夏の間であることが多いです。羽アリは以下のような見た目をしているため、小さな羽虫を見かけたらよく観察して見分けてみましょう。
種類で違うシロアリの巣の特徴
先ほどご紹介したシロアリの巣の情報は、「人間の家に侵入する多くのシロアリ」に見られる傾向です。ただし、シロアリの種類によって巣の特徴や生態に違いがあることを覚えておきましょう。日本の家屋を加害するシロアリの巣の特徴を種類別でご紹介していきます。
ヤマトシロアリの巣の特徴
【ヤマトシロアリの巣の生態】
- 一部を除いた日本全国に生息
- 食害した木材の内部に巣を作る
- 腐った木材や湿気の多い場所が大好き
- 1つの巣の個体数は2~3万匹ほど
日本のシロアリ被害のなかで特に多いのがヤマトシロアリによるもの。ヤマトシロアリはある程度寒い地域でも活動することができるため、北海道北部を除いた日本全体で見られる害虫です。
ヤマトシロアリは湿気のある腐った木材を好んで食べる傾向があり、エサ場となる木材を巣として使う習性があります。風呂場(浴室)やトイレ、水漏れ・雨漏りが起きている場所に発生しやすいでしょう。個体数は2~3万匹であるため、対処が遅れると大事な建築材をスカスカにされてしまいます。
イエシロアリの巣の特徴
【イエシロアリの巣の生態】
- おもに西日本の沿岸部に生息している
- 大きな土の塊の巣を作る
- 多少乾燥した場所でも生きられる
- 最大で100万匹ほどに増えることもある
ヤマトシロアリと比較してそれ以上に厄介なのがイエシロアリ。生息地域は西日本を中心としているのですが、厄介さでいえばイエシロアリが群を抜いています。その理由は、巣の規模と個体数の多さ。イエシロアリは女王アリのいる巨大な「本巣」とそこから分岐する「分巣」という形で巣を作り、ヤマトシロアリよりも巣の規模が拡大しやすいのです。
イエシロアリは水分を運ぶ能力をもっているため、ヤマトシロアリがあまり好まない新しい木材も好んで食害してしまいます。そのため、新築で立てたばかりの物件でもイエシロアリ被害に注意しなければなりません。イエシロアリの巣の個体数は100万匹にもなることがあり、早めの予防と駆除が求められます。
アメリカカンザイシロアリの巣の特徴
【アメリカカンザイシロアリの巣の生態】
- 日本北部を除き、あちこちに点在している
- 乾燥した木材でも巣を作ることができる
- 食害する場所を選ばず、床下以外からも侵入する
- 個体数は少ないが、最大で2000匹に増えることも
木材の輸入とともに日本にやってきたとされるアメリカカンザイシロアリ。日本北部では発見されていないこと以外に、日本での分布にはこれといった傾向が見られません。
アメリカカンザイシロアリは「カンザイ(乾材)」と名の付くとおり、乾燥した場所でも平気で巣を作るのが特徴で、多くのシロアリが乾燥対策として作る「蟻道(ぎどう)」というトンネルを作りません。床下以外にも屋根裏や天井裏、外壁といったところから見境なく巣を作る可能性もあるので注意が必要です。
また、アメリカカンザイシロアリは個体数が少ないというのも厄介なポイント。数年以上かけてようやく数百以上の個体になるほどの繁殖スピードの遅さです。数が少ないため人間に見つかりにくく、気付いたときには木材がすでにボロボロになっているかもしれません。
ダイコクシロアリの巣の特徴
【ダイコクシロアリの巣の生態】
- 沖縄を中心とした離島で見られる
- 湿気を嫌い、乾燥した木材を好む
- 小さな巣を複数作るため駆除難易度が高い
- 数十~数千と小規模の個体数
日本ではおもに離島で見られるため、かなり珍しい種類のシロアリです。基本的に寒さを苦手としているため生息地が限定されていますが、温暖化が進むにつれて今後生息地域が広くなる可能性もあるので一応覚えておくとよいでしょう。
ダイコクシロアリはアメリカカンザイシロアリと似たような生態をもち、床下だけでなくさまざまな場所から巣を作る可能性があります。しかもダイコクシロアリは小さな巣を複数作る習性をもつため、完璧に駆除することはなかなか難しいのです。
シロアリの巣を発見する方法
基本的にシロアリは人の見えないところで行動するため、目視でシロアリの姿を見つけるのはなかなか難しいです。しかし、絶対に見つからないというわけではなく、これからご紹介する方法で、シロアリの巣がある場所をある程度特定できます。
床や壁を叩いてみる
床下はシロアリ被害に最も遭いやすいといっても過言ではない場所です。もし床下の木材に被害が出ていると、中身に空洞ができることで床がきしむことがあります。床下を踏んで点検し、音がしたりへこんだりしている場所があるのであればシロアリ被害を疑ってみてください。壁も同様に、叩いたときに空洞音がすればシロアリ被害の可能性があります。
蟻道(ぎどう)を探す

ヤマトシロアリ・イエシロアリといった乾燥を嫌うシロアリは「蟻道(ぎどう)」という特有のトンネルを作り、床下の木材へ侵入します。蟻道は上記イラストのように土の中から盛り上がり、木材などのエサ場につながっているのが特徴です。
シロアリは蟻道を通って、コンクリートのひび割れの中へ侵入することも。そのため、床下の基礎部分だけでなく家の外周にあるコンクリート付近も念入りにチェックすることが大切です。見つけた蟻道を壊してもすぐに修復されて対策にはなりません。業者に依頼して駆除をしてもらってください。
床下に潜って調べる
もし自宅に床下点検口があれば、自分で床下に潜ってシロアリの被害状況を確認することが可能です。蟻道がないか、ボロボロになっている木材や断熱材はないかを確認することで、シロアリの有無を確かめることができます。
ただし、床下は狭くて動きにくいため個人での床下調査はケガをしてしまうリスクが高いです。安全を考えるなら業者に床下点検をお任せしたほうが安心です。
不自然な穴や形跡はないか
木材の中から羽アリが外に出るための群飛孔、アメリカカンザイシロアリが開ける小さな穴はないか調べることも大切です。壁や木柱といったところから窓サッシの枠や玄関に使われる木材まで念入りに調べてください。また、アメリカカンザイシロアリが開けた穴の近くには、細かい砂粒のようなフンが散らばっていることが多いです。
シロアリの巣を見つけたときの駆除方法
もしシロアリの巣が作られている可能性があるなら、できるだけ早くシロアリ駆除をしておきましょう。この章では、個人でも簡単にシロアリ駆除ができる「ベイト工法」という方法をご紹介します。
ベイト工法は自力駆除が可能

「ベイト剤」とよばれる毒エサを使用し、シロアリに食べさせて駆除する方法のことをベイト工法といいます。上記イラストのように土に埋めて使用することで、エサのニオイにつられたシロアリがやってきて毒エサを巣に持ち運んでくれます。持ち帰らせて巣にいる仲間にも毒エサを食べさせることで、シロアリを巣ごと駆除できるのです。
ベイト工法の手順は土を掘ってベイト剤を埋めるだけでよいのですが、シロアリが食べてくれるかは設置する場所によります。場所が合っていないと駆除が思うように進まないため注意が必要です。
駆除のプロに施工してもらうのが無難
一度食べられた木材は再生するわけではないので、家を守るためには食害される前に早く駆除することが大切。もし、一刻も早く確実にシロアリ駆除をしたいとお考えならシロアリ駆除のプロにお任せしてみましょう。シロアリ駆除業者はベイト剤設置の他に、「バリア工法」という即効性の高い作業でのシロアリ駆除が可能です。
バリア工法とは、シロアリがいる木部に穴を開けて薬剤散布する方法で、ベイト工法よりも早くシロアリ駆除できます。さらに、シロアリ駆除業者なら駆除後の予防もしてもらえるので、再発に怖がることなく駆除後も生活できます。
また、シロアリ駆除業者に依頼しようか検討している方は弊社にぜひご相談ください。弊社の加盟店様はシロアリに関する知識と実績が豊富なスタッフもいらっしゃいますので、効果的なシロアリ駆除をしてもらうことが可能です。
シロアリの巣を作らせないために
業者に駆除をしてもらったり、運よくシロアリ被害に遭ってなかったりする場合は、それで安心せずにシロアリ予防をしましょう。シロアリにとって都合の悪い環境を作ることで、シロアリ被害に遭う確率を減らすことが可能です。
床下の湿度を下げておく
日本で被害の多いヤマトシロアリとイエシロアリの2種類は、湿った木材を好みます。そのため、床下の湿度をなるべく下げておくことでシロアリ対策になるのです。例えば床下に換気扇を付けたり、乾燥材をまいたりなど。乾燥しやすい環境を作ることで、シロアリ対策だけでなくカビもできにくいので一石二鳥です。
地面に木材を置かない

地面に接触する形で木材を置いていると、地中から穴を開けてシロアリが侵入してくるおそれがあります。木材の下にはシートなどを敷くか、できれば屋外に木材を置かないようにしましょう。また、シロアリはダンボール類も食害してしまうので、外に放置しないように気を付けておきたいところです。
業者に定期メンテナンスを依頼する
シロアリ予防は個人だけでなく、業者にも協力してもらいましょう。プロの目で定期的にシロアリ被害の点検をしてもらうことで、シロアリの早期発見と駆除がしやすくなります。
シロアリ予防としてベイト剤の設置や床下の木材や土壌に薬剤を吹きかける処置をしてもらうことも可能です。業者によるメンテナンスは少なくとも半年~年1回の頻度でおこなうとよいでしょう。
まとめ
シロアリは食欲旺盛で日に日に木材を食べられてしまいます。シロアリに巣を作られている可能性があるときは、すぐに行動して有無を確かめることが大切です。ご紹介したシロアリの巣の特徴と確認方法を参考にし、ご自身で一度点検をしてみてください。もし何か怪しい箇所があれば、業者に依頼するときに伝えておくとよりスムーズです。
また、シロアリ駆除や点検が必要であればぜひ弊社のサービスをご利用ください。弊社では、シロアリに関する知識と駆除経験が豊富な加盟店様が多数いらっしゃいますので、効果的なシロアリ駆除をしてもらうことが可能です。24時間365日体制で対応可能なので、困ったときに無料電話ですぐに相談ができます。
シロアリ駆除のおすすめ記事
\ 完全無料 /
厳選した全国のシロアリ駆除業者を探せます!
×
関連記事カテゴリ一覧
シロアリ駆除の記事アクセスランキング
シロアリ駆除の最新記事
カテゴリ別記事⼀覧
- お庭の手入れ
- 害虫駆除
- 害獣駆除
- 電気工事
- 鍵開け・交換・修理
- 窓ガラス修理・ドアノブ修理
- 家の修理
- バッテリー上がり
- ハウスクリーニング
- ペット火葬・葬儀
- 家電修理
- パソコン修理・ネット回線
- 家具・雑貨の修理
- 外壁・屋根工事
- リフォーム
- 防犯カメラ設置
- 盗聴器・その他調査診断
- 便利屋・代行サービス
- 引越し・配送サービス
- オフィス・店舗向けサービス
- その他










