
あなたはスズメバチの生態についてどれくらい知っていますか?スズメバチが危険な生物であるというのは、よく耳にすることですよね。しかし、体の特徴や活動時期、食性や遺伝子について詳しく知っているという方は少ないのではないでしょうか。
スズメバチは種類によっては都会にも順応し、住宅街に巣を作ることも珍しくありません。もしもご自宅に巣を作られてしまったら、スズメバチの生態に合わせた駆除をおこなう必要があります。
スズメバチの活動サイクルや体のしくみを知れば、被害を未然に防ぐこともできるでしょう。そして、スズメバチの生態を知れば、蜂の巣駆除の危険性やスズメバチの本当の怖さを知ることにもなります。
住宅にできてしまったスズメバチの巣は、一刻も早く駆除することが重要です。安全なスズメバチ駆除は「生活110番」にお任せください。
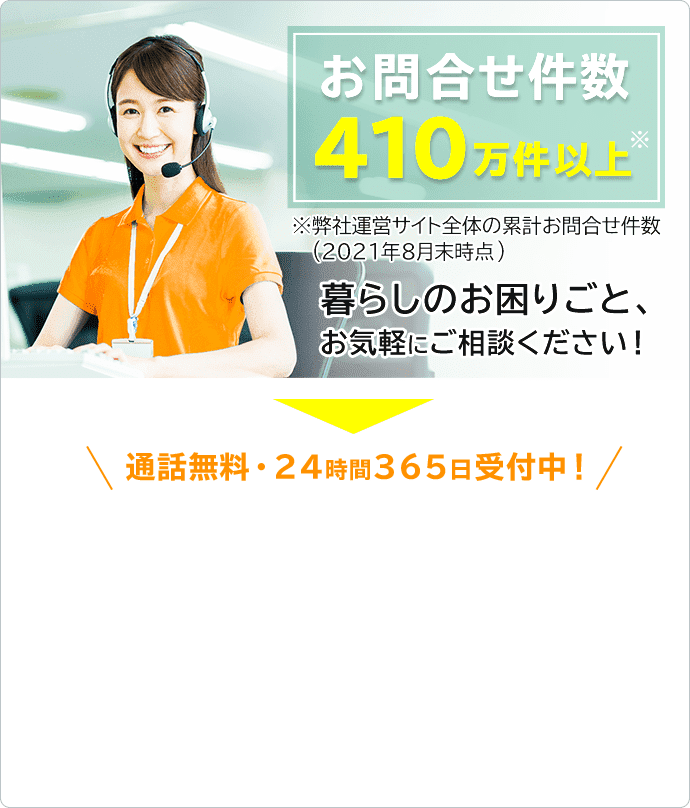
目次
スズメバチは「社会性昆虫」
スズメバチは基本的に、集団の中に「女王蜂」「働き蜂」「雄蜂」という階層をもち、分業して社会生活を営む「社会性昆虫」と呼ばれる生き物です。
ただし、チャイロスズメバチやヤドリスズメバチ、ヤドリホオナガスズメバチは、ほかスズメバチの巣を乗っ取ることで繁殖する「社会寄生性昆虫」で、その生態から活動時期などに違いがあります。
ちなみに、スズメバチの「スズメ」という名の由来は、スズメバチの体の大きさが鳥類のスズメの大きさほどであることからといわれています。(※諸説あり)
女王蜂
女王蜂は唯一卵を産むことができる蜂です。女王蜂だけが冬を越すことができ、寿命は基本的に1年です。女王蜂は受精卵から産まれたメスの蜂で、遺伝子的には働き蜂と同じだといわれています。大きな育房に産みつけられて、栄養価の高いエサをたくさん与えられたものが女王蜂になると考えられているのです。
働き蜂
働き蜂は、受精卵から産まれた蜂ですべてメスです。エサをとってきたり、巣の中を掃除したり、巣作りをしたりとよく働きます。巣のなかで一番多くの割合を占めるのが、働き蜂です。幼虫の状態とサナギの状態でそれぞれ2~3週間ほど過ごします。成虫になってからの寿命は1ヶ月ほどで、合わせて2~3ヶ月ほどの命です。
雄蜂
雄蜂(おばち)は、無精卵から産まれたオスの蜂です。繁殖のためだけに存在しており、毒針をもっていません。エサ集めや巣作りなどの仕事は一切せず、交尾を終えるとそこで役目が終わって死んでしまいます。そのため雄蜂の寿命は2ヶ月ほどと短いです。
スズメバチのオスの数は、巣全体の5~10%程度だといわれています。
スズメバチが特攻できるのは遺伝子のせい!?
多くの生物は、自らの生命を守るために攻撃や防御をおこないます。しかし、スズメバチの働き蜂は、ときには危険をかえりみずに大きな敵に対しても特攻します。捨て身の攻撃は生物の本能に反しているようにも思えますが、スズメバチの遺伝子の特性を知れば理にかなった行動であることがわかるでしょう。
母子間の遺伝子共有率は50%
スズメバチは女王蜂のみが卵を産み、雄蜂の精子と掛け合わせた受精卵はメスに、精子を掛け合わせない無精卵はオスになります。働き蜂は有精卵から産まれたメスであり、母親である女王蜂の遺伝子と、父親である雄蜂の遺伝子を半分ずつ受け継いでいるため、母子間での遺伝子共有率は50%です。
新女王蜂も有精卵から産まれたメスであるため、母子間での遺伝子共有率は同じく50%です。では、働き蜂同士や働き蜂と新女王蜂といった姉妹間ではどうでしょう。
姉妹間の遺伝子共有率は約75%
DNAに含まれるすべての遺伝情報のことを「ゲノム」といいます。有精卵の場合は、母親由来のゲノムと父親由来のゲノム、2組のゲノムをもっています。しかし、スズメバチの雄蜂は無精卵から産まれてくるため、母親由来の1組のゲノムしかもっていません。
スズメバチの遺伝子情報図

そのため、同じ雄蜂との受精卵から産まれたメスは、父親からの遺伝子は100%同じで、母親からの遺伝子は50%の確率で同じだということになります。すると、姉妹間での遺伝子共有率は平均75%と、母子間よりも高くなるのです。

つまり、スズメバチの働き蜂は、たとえ自分の命を犠牲にしても、姉妹であるたくさんの働き蜂や新女王蜂を生かすことで自らの遺伝子を残すことができるのです。
スズメバチの体の特徴
スズメバチの成虫の体は、頭部・胸部・腹部の3つに分かれています。胸部と腹部のあいだは細くくびれており、このくびれのおかげで体を折り曲げて自在に毒針の向きを変えられるため、狙いを定めて敵に毒針を刺すことができるのです。

触角
スズメバチの頭部から生えている1対の触角には、匂いを感じ取る役割と大きさを測る定規のような役割があります。触角を使ってフェロモンの匂いをかぎ分けたり、巣作りの際に育房の大きさや形を測ったりするのです。
メスの触角には12の節があり、付け根側の1節目が曲がっています。オスの触角には13の節があって真っ直ぐです。この違いからメスとオスを見分けることもできます。
目
スズメバチの目は、額の部分に3個の単眼と、その左右に1対の複眼があります。単眼は明るさを、複眼は物の形や動きを見る働きをしています。
視力は、3~5m先までしか見えないといわれており、人間と比べるとかなり悪いですが、動体視力はとても優れていて、人間の7倍にもなるといわれています。視野は水平方向に広く、垂直方向には狭いです。また、スズメバチは青色と緑色に加えて紫外線も感知することができますが、赤は色としては見えません。
顎
スズメバチの顎はよく発達しています。巣の材料となる樹木の繊維をかじり取るほか、虫やや動物を噛み砕いて幼虫に与えることや、戦いの際には噛みついて攻撃することもあるためです。巣に近づくものを威嚇する際には、顎をカチカチと鳴らして警告音を発します。
羽
スズメバチの羽は一見2枚に見えますが、前後1対ずつの4枚の羽が生えています。うしろの羽の縁は細かいフックのような形状になっており、前の羽を引っかけて一緒に動くため2枚に見えているのです。非常に薄く小さな羽を効率的に動かすことによって、時速40kmもの速さで飛ぶことができるスズメバチもいます。
その薄さから、雨に弱いという性質ももっています。透けるほどの薄さの羽は、水分を含むと重くなり、素早く羽ばたけなくなってしまうのです。
脚
スズメバチの胸部からは6本の脚が生えています。脚の先には鋭い爪が2本生えており、爪と爪のあいだには「褥盤(じょくばん)」と呼ばれる器官があります。この褥盤が吸盤のような役割をすることで、ツルツルとしたガラスや垂直な壁にもとまることができるのです。
毒針
スズメバチの毒針は「産卵官」が変化したもので、メスである女王蜂と働き蜂だけが毒針をもっています。また、雄蜂には毒針はありませんが、威嚇のために刺す姿勢をとることはあります。
同じ蜂類でも、たとえばミツバチは毒針についたギザギザの「かえし」が引っかかり、一度刺すと多くの場合抜けなくなった毒針はミツバチの体から千切れてしまいます。しかし、スズメバチの毒針のかえしは非常に小さいため抜けなくなることはなく、何度でも敵や獲物を刺すことができるのです。
スズメバチはフェロモンで会話する
集団で生活するスズメバチは、体内で生成した「フェロモン」を分泌することで情報の伝達をおこなったり、仲間の行動や発育に影響を与えたりしています。女王蜂と働き蜂と幼虫、それぞれの役割や目的によって分泌するフェロモンにはさまざまな種類があります。
| 蜂 | フェロモン | 特徴 |
|---|---|---|
| 女王蜂 | 階級維持フェロモン (女王物質) |
メス蜂である働き蜂の卵巣機能が発達することを抑制するフェロモンです。新女王蜂用の大きな育房を作る際にもこのフェロモンが関係しているといわれています。 |
| 性フェロモン | 新女王蜂が発するフェロモンで、雄蜂に交尾行動を引き起こさせます。 | |
| 働き蜂 | 警報フェロモン | 働き蜂が出す毒液の中に含まれています。敵が来たことを仲間に知らせて、攻撃を仕掛けるように働きかけます。香水や整髪料などの中には、警報フェロモンと同じ物質が含まれているものや、よく似た匂いを発するものがあります。 |
| 集合フェロモン | 雄蜂を巣の入り口に誘導します。 | |
| 造巣フェロモン | 「キイロスズメバチ」や「モンスズメバチ」など、手狭になると巣の引越しをおこなう習性のあるスズメバチが分泌するフェロモンです。引越し先の巣を作る場所を仲間に知らせます。 | |
| 仲間認識物質 | 同じ巣の仲間を識別する物質です。 | |
| エサ場マークフェロモン | 集団で狩りをおこなう習性のあるオオスズメバチが分泌するフェロモンです。エサ場にこの匂いをつけることで、ほかの働き蜂を集めて集団で攻撃します。 | |
| 幼虫 | 蜂児フェロモン | 幼虫が働き蜂に自分の居場所を知らせて、給餌行動を促します。 |
幼虫と成虫で異なるスズメバチの食性
強い毒性や攻撃性をもつことから害虫として扱われ、おそれられるスズメバチですが、生態系のバランスを保つうえで欠かせない生物でもあります。自然界では食物連鎖の上位に位置し、樹木や草花につく虫を捕食する益虫でもあるのです。幼虫と成虫で異なる、スズメバチのエサについて説明します。
幼虫のエサ
スズメバチの幼虫はたんぱく質を栄養源にして成長します。虫や動物などを成虫が噛み砕き、肉団子にして幼虫に与えます。
成虫のエサ
スズメバチの成虫は樹液や花の蜜、熟した果実などの炭水化物をおもな栄養源にしています。多くのスズメバチが甘いものを好むため、飲みかけのジュースの缶にスズメバチが入ってしまい、ふたたび飲もうと口をつけたところを刺されるという事例もたびたび発生しています。

栄養交換
スズメバチの成虫は胸部と腹部のあいだが極端に細くくびれているため、虫や動物などの固形物をそのまま摂取することはできません。しかし、幼虫は成虫が与えた肉団子を食べる際に、その一部を唾液に作り変えて分泌します。成虫は幼虫の分泌液を舐めることでたんぱく質を摂取できるのです。
幼虫の分泌液には人間の母乳にも匹敵するほどの栄養が含まれていて、成虫の貴重なエネルギー源になっています。このように、成虫と幼虫のあいだで栄養のやりとりをすることを「栄養交換」といいます。
スズメバチの活動サイクルは時間・時期で決まっている
種類によって多少の違いはありますが、スズメバチが活動するおもな季節は春から秋にかけてです。短い寿命のなかでも活動サイクルが決まっており、スズメバチの活動が活発になる春から秋にかけてが、人への被害が増えやすい季節であるといえます。
そして、1年のなかで活動のサイクルがあるように、1日のなかでも決まったサイクルでスズメバチは活動しています。
| 活動時間 | 活動内容 |
|---|---|
| 早朝 | エサや巣の材料を探しに巣の外へ出かけます。1日の中で一番スズメバチの出入りが激しい時間帯です。 |
| 昼 | 引き続きエサ集めや巣作りのために蜂が巣を出入りします。しかし日差しが強くなるとゆったりとした活動になる特徴があります。 |
| 夕方 | 多くのスズメバチが日没前に巣に戻ります。一部の種類を除いて、スズメバチは暗闇での視力がないためです。夕方も慌ただしくスズメバチが動く時間帯です。 |
| 夜 | スズメバチは巣に戻っても休むわけではなく、夜間も眠らずに巣や幼虫の世話をしているといわれています。 |
【4~5月ごろ】女王蜂が活動をはじめる
4~5月ごろに見かけるスズメバチはすべて女王蜂で、体力とともに攻撃性も落ちているため、活動が最盛期に比べて危険度は低いです。
前年に羽化し越冬した女王蜂が冬眠から目覚めて活動をはじめます。冬眠中はまったくエサを採らず体内に溜め込んだ脂肪を栄養にして生き延びていたため、体力を回復するために樹液や花の蜜を摂取します。
体力が回復した女王蜂がおこなうのが、営巣場所探しです。すぐに巣作りをはじめるわけではなく、いくつかの候補地を見つけて何度も飛び回り、巣作りに適した場所を見極めるまでに数日間費やすといわれています。
そうして営巣場所を決めると、単独で巣作りをはじめます。巣の材料は、朽木などをかじり取って噛み砕き唾液と混ぜたものです。
スズメバチの巣は、何層にも重なった「巣盤」とそれを覆う外被によって作られています。巣盤には「育房」と呼ばれる小さな部屋があり、育房を3室くらい作ると女王蜂はそこに産卵をはじめます。
働き蜂が羽化するまでの約1ヶ月は、エサ集め、巣作り、産卵、幼虫の世話、巣の保温や防衛などのすべてを女王蜂1匹でおこなっているのです。
この時期に雨が多かったり気温が低かったりすると、女王蜂が死んでしまうことがあります。逆に雨が少なくスズメバチの巣作りに適した30~32度くらいの日が続けば、多くの女王蜂が生き残って巣の数の増加や巨大化が起こりやすくなります。このように、スズメバチの巣は気候に左右されやすいという特徴があります。
また、社会寄生性のチャイロスズメバチなどの女王蜂は、ほかのスズメバチよりやや遅く冬眠から目覚めて営巣初期の巣を乗っ取ります。
【6~8月ごろ】働き蜂が活動をはじめる
6月になると、最初に産卵した卵から育った働き蜂が羽化しはじめます。働き蜂が巣作りに参加しだすと、巣は急速に成長します。女王蜂は産卵に専念するようになり、巣の規模はますます大きくなるのです。
そして複数の働き蜂がそれぞれ違う場所から材料をもち帰るため、色に違いが生じて特徴的なうろこ状の模様になります。この時期に、営巣場所が手狭になると巣の引越しをおこなう種類のスズメバチもいます。
【8~10月ごろ】危険度MAX!最盛期
8~10月ごろは働き蜂の数がもっとも多く、巣のサイズも最大になります。雄蜂と新女王蜂が誕生し、繁殖期に備えて防衛本能や警戒心が強くなるため、攻撃性が非常に高まります。この時期のスズメバチは、近くを通っただけで襲ってくることもあるほど危険なので、巣を見つけても絶対に刺激しないでください。
もしもスズメバチに刺されたときは、念のために病院へいきましょう。スズメバチの毒は大変強力なうえ、「アナフィラキシーショック」というアレルギー反応によって死にいたることもあるのです。
【10月下旬~11月下旬】越冬の準備
営巣活動が終わり、働き蜂は寿命を迎えて徐々に数が減っていきます。新女王蜂と雄蜂は巣を離れて、その多くが違う巣で育った配偶者とそれぞれ結ばれます。交尾を終えると、雄蜂は死んでしまいますが、新女王蜂は精子を体内に溜めた状態で越冬するのです。
寒い冬のあいだは枯れ木や倒木、土の中などでじっと動かず、春が来るのを待ちます。すべての女王蜂が無事に越冬できるわけではなく、厳しい寒さに耐えきれずに死んでしまう個体も少なからずいます。
スズメバチの毒がさまざまな症状を引き起こす理由
スズメバチの毒には、おもに「アミン類」「低分子ペプチド」「酵素類」の3種類と、オオスズメバチのみがもつ「マンダラトキシン」という神経毒があります。どの物質がどれだけ配合されているのかはスズメバチの種類によって異なり、成分が複雑に合わさることでさまざまな症状を引き起こします。
スズメバチに刺されると、毒自体の直接作用によって引き起こされる痛みや腫れなどの症状のほかに、アレルギー作用によって「アナフィラキシーショック」を引き起こすおそれがあります。
直接作用は毒の注入量が影響するのに対し、アレルギー作用は量に関係なく命にかかわるものです。スズメバチに刺されたときは、とくに症状がなくても病院で診察を受けておくことをおすすめします。
また、スズメバチは針で刺すだけでなく、毒を噴射することもあります。目に入ると失明のおそれもあり大変危険です。万が一目に入ってしまった場合には、こすらず流水で洗い流し、すぐに医師の診察を受けてください。

スズメバチにも天敵はいる!
スズメバチは強い毒と高い攻撃力をもち、自身の何十倍もの大きさの生き物でさえ殺傷してしまうことがありますが、生態系のなかではもちろん捕食される側になることもあります。スズメバチの天敵となる生物で、代表的なものをご紹介します。
| スズメバチの天敵 | |
|---|---|
| 動物 | クマ |
| ハチクマ | |
| クモ | |
| 肉食昆虫 | オニヤンマ |
| オオカマキリ | |
| ムシヒキアブ | |
| 寄生虫 | スズメバチネジレバネ |
| スズメバチタマセンチュウ | |
クマ
日本には、北海道にはヒグマが、本州にはツキノワグマが生息しています。硬い毛に覆われた丈夫な皮膚をもち、スズメバチに襲われながらも巣を襲って幼虫やサナギ、成虫まで食べてしまうことがあります。
ハチクマ
ハチクマは、タカなどと同じ猛禽(もうきん)類で、初夏に日本にやってくる渡り鳥の一種です。スズメバチの幼虫やサナギが好物で、ヒナに与えるために巣を破壊してもち帰ります。全身がウロコのように硬い羽毛に覆われており、スズメバチの毒針が効きません。また、ハチクマにはスズメバチの攻撃性を奪うフェロモンや体臭のようなものがあるとも考えられています。
クモ
スズメバチのなかには、幼虫のエサとしてクモを狩るものもいます。しかし、高い攻撃力をもっていてもクモの巣に絡まってしまえば身動きがとれず、逆に捕食されてしまうこともあるのです。
オニヤンマ
大型のトンボで、日本に生息するトンボの中では最大級の大きさです。獲物に背後から襲いかかり、無数のトゲがある手足で捕獲します。オニヤンマもまた大きな顎をもっており、スズメバチをバリバリと噛み砕いて食べてしまえるのです。
オオカマキリ
オオカマキリは、大きなカマで獲物を捕らえて捕食します。不意打ちで先制攻撃を仕掛けることができれば、スズメバチを抑え込むこともできるのです。しかし正面から戦えば、強い顎や鋭い毒針をもち、自由に飛び回ることのできるスズメバチに勝つことは困難です。そのため、スズメバチに捕食される側になることもあります。
ムシヒキアブ
ムシヒキアブは、ハエ目ムシヒキアブ科に属する昆虫で、アブの仲間です。性格は獰猛(どうもう)で、その狩りは激しく、獲物を待ち伏せて頭上や背後から奇襲します。スズメバチもこの奇襲攻撃で捉えることができますが、先制攻撃を受けたときや蜂の集団に襲われたときには負けてしまいます。
スズメバチネジレバネ
スズメバチに寄生する昆虫として知られているのが「スズメバチネジレバネ」です。樹液を舐めに来たスズメバチの成虫の体にしがみつき、そのまま運ばれて巣の中に入り込みます。巣に入ると成虫から降りて育房へ向かい、幼虫の体内に住みついて栄養を摂ります。そして、スズメバチが成虫になっても寄生し続けるのです。
スズメバチネジレバネに寄生されたスズメバチは、巣作りやエサ集めなどをせず、巣の中でじっと過ごすことが多くなります。また、新女王蜂や雄蜂の生殖機能を奪うこともわかっています。スズメバチネジレバネの寄生が拡大した巣は、正常な活動ができなくなってやがて崩壊してしまうのです。
スズメバチタマセンチュウ
近年、スズメバチ防除の素材として注目されているのが「スズメバチタマセンチュウ」という生物です。朽木などで越冬中の新女王蜂に寄生し、卵巣の発達を妨げて不妊化することがわかっています。現在、オオスズメバチ・キイロスズメバチ・チャイロスズメバチ・ヒメスズメバチ・モンスズメバチの5種の大型スズメバチへの寄生が確認されています。
スズメバチの生態を利用した対策をしよう
スズメバチの生態を知ることは、蜂の巣駆除やスズメバチ被害への対策にも役立ちます。
スズメバチの駆除をする際に役立つ生態
できるだけ安全にスズメバチの駆除をおこないたいのであれば、スズメバチの活動サイクルや弱点を利用しましょう。
- 春先は女王蜂が単独で活動している
- スズメバチの多くは暗闇での視力がない
- スズメバチは寒さや雨が苦手
4~6月は冬眠から目覚めた女王蜂が単独で巣作りをしており、凶暴な働き蜂がいないため比較的安全に駆除できるでしょう。6月を過ぎると働き蜂が羽化しはじめ、スズメバチの仲間が増加します。そのため、巣が一気に巨大化して駆除の難易度は高くなってしまいます。
ただし、営巣初期であってもスズメバチに刺される危険性がないわけではないので十分注意してください。
駆除の時間帯は、日没後2~3時間経ってからがよいでしょう。ほとんどのスズメバチは暗いところでは目が見えないため、基本的に夜間は巣の中で過ごします。蜂を取り逃がさないためにも、蜂の巣の駆除は夜間におこなうとよいです。もしも女王蜂を取り逃がしてしまえば、近くにまた新しい巣をすぐに作られてしまいます。
スズメバチには寒さや雨に弱いという特徴があるため、気温の低い日や雨の日を狙って駆除するのもよいかもしれません。動きの鈍ったスズメバチであれば、駆除しやすいのではないでしょうか。
スズメバチを刺激しないために注意すべき生態
スズメバチに遭遇したときには、以下のような生態に注意することで、スズメバチに刺されないようにしましょう。
- 繁殖期(夏~秋)は攻撃性が高まる
- スズメバチは左右に動くものに敏感に反応する
- スズメバチは警告音を発することや威嚇行動をとることがある
- スズメバチは黒っぽいものを認識しやすい
- スズメバチは匂いに敏感
スズメバチが人を刺すのは、自分の身や巣に危険が迫っていると感じたときです。とくに夏の終わりから秋の繁殖期にかけては、巣の拡大とともに警戒心や攻撃性も非常に高まります。スズメバチの巣にむやみに近づかないことが重要です。
また、スズメバチは左右に動くものに反応して興奮してしまいます。スズメバチが近くを飛んでいても手で払うことはやめてください。前後の動きにはそこまで敏感ではないので、ゆっくりとあとずさりするようにして退避するとよいでしょう。
スズメバチが発する音にも注意しましょう。というのも、スズメバチは巣に近寄るものに対して、顎を使ってカチカチという音を鳴らし警告をします。この警告音を無視して巣に近づけば、興奮状態になった蜂の襲撃を受けるかもしれません。しかしこれは「警告音がするまでは大丈夫」という意味ではなく、実際は無警告で攻撃してくることもあります。「蜂が周囲を飛び回る」などの威嚇行動に気づいた段階で、静かに来た道を引き返してください。
スズメバチの目は白黒で物をとらえています。そのため、黒色はスズメバチに認識されやすく、攻撃対象になりやすいのです。キャンプやハイキングなどの野外活動に出かける際には黒っぽい服装は避けて、白い帽子をかぶるなどして髪の毛を隠すことも大切です。
スズメバチはフェロモンを使って仲間の蜂と連絡をとります。そして、危険を知らせる「警報フェロモン」とよく似た匂いが、香水や整髪料の中に含まれていることがあります。制汗剤や柔軟剤なども、匂いの強いものはスズメバチの攻撃を誘発するおそれがあるため避けてください。

スズメバチ駆除の相談は生活110番へ
スズメバチは駆除をする時期によって危険度や難易度が変わります。夏の終わりから秋にかけて、巨大化したスズメバチの巣を見つけたら迷わずプロの蜂駆除業者に任せるべきです。
たとえ危険性が比較的低いとされる時期であっても、強い毒をもっていることに変わりはありません。やはり無理に手を出さず、プロに依頼したほうが安心でしょう。
スズメバチは機動性・攻撃性に優れた生物で、生態系のなかでも上位に位置しています。遺伝的な要素からも、命がけの攻撃ができてしまうという怖さもあり、駆除には大変な危険がともなうのです。
スズメバチを見かけたら、すぐに生活110番までご相談ください。
\ 完全無料 /
厳選した全国の蜂の巣駆除業者を探せます!
×
関連記事カテゴリ一覧
蜂の巣駆除の記事アクセスランキング
蜂の巣駆除の最新記事
カテゴリ別記事⼀覧
- お庭の手入れ
- 害虫駆除
- 害獣駆除
- 電気工事
- 鍵開け・交換・修理
- 窓ガラス修理・ドアノブ修理
- 家の修理
- バッテリー上がり
- ハウスクリーニング
- ペット火葬・葬儀
- 家電修理
- パソコン修理・ネット回線
- 家具・雑貨の修理
- 外壁・屋根工事
- リフォーム
- 防犯カメラ設置
- 盗聴器・その他調査診断
- 便利屋・代行サービス
- 引越し・配送サービス
- オフィス・店舗向けサービス
- その他








