
細長くて脚の多い虫がうねうね這いまわっているのを見かけたら、まずムカデだと思って警戒しますよね。強力な毒と鋭い大アゴをもったムカデは、場合によっては強い痛みと腫れを引き起こす非常に危険な害虫です。
ムカデの種類はとても多く、約3000種類といわれています。そのうち日本に生息している種類は100ほど。
その中でも家に侵入するムカデは3種類程度と少ないものの、有毒で凶暴なムカデは1匹でもいたら注意が必要です。
たとえそれが小さな赤ちゃんムカデだとしても、やはりムカデはムカデ。しっかり顎で咬んできます!
ムカデの幼虫くらいなら簡単に退治できそうですが、本当に恐ろしいのはここから。ムカデは子育てをする生き物なので、幼虫を見かけたら近くに親がいる証拠です。
今回のコラム内容は、ムカデの種類と幼虫、ヤスデとの見分け方を中心に解説していきます。
もちろんムカデが家に出たときの対処法についてもご紹介しているので、ムカデについて気になることがあれば、ぜひ一読ください。
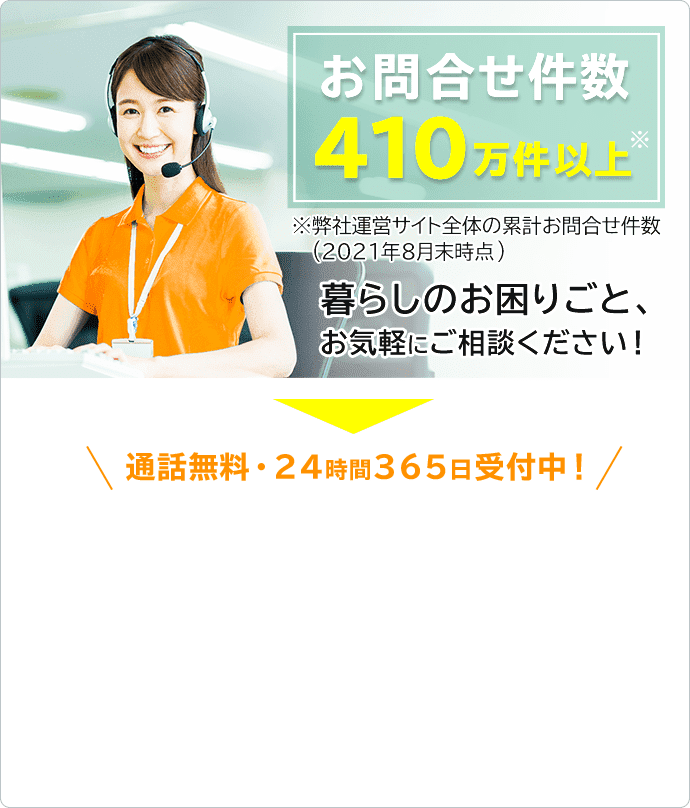
目次
ムカデは世界に3000種類以上いる
ムカデは日本では100種類以上が確認されています。世界では何十倍も多くその数なんと3000以上。
毒の強い種類や色鮮やかな種類などさまざまです。
でもみなさんが気になるのは「家に出るムカデ」かと思います。
毒性が強く特に注意しておきたい3種について詳しくご紹介します。
毒の強いムカデ3種の生態
| トビズムカデ | |
|---|---|
 |
|
| 生息地 | 北海道南部~沖縄 |
| 体長 | 8~15cm |
| 特徴 | 頭と足が赤色系 |
| 足の数 | 42本 |
| アオズムカデ | |
|---|---|
 |
|
| 生息地 | 青森県以南 |
| 体長 | 8~10cm |
| 特徴 | 頭が青い |
| 足の数 | 42本 |
| アカズムカデ | |
|---|---|
 |
|
| 生息地 | 本州~九州 |
| 体長 | 4~7cm |
| 特徴 | 頭が赤い |
| 足の数 | 42本 |
そのほかのムカデの生態
毒性は弱いものの、家に侵入することもあるので注意は必要です。
◆タイワンオオムカデ
沖縄に生息
体長20~27cmと大きい
黒色をしている
◆セスジアカムカデ
全国に広がり生息
体長4~7cmと小さめ
赤系の色をしている
◆ヤンバルオオムカデ
沖縄に生息
体長20~27cmと大きめ
緑系の色をしている
毒は弱くても咬みつかたら、痛く赤くなるのでムカデは種類に限らず、見かけたら早めに退治したほうがよいでしょう。
国内最大のムカデとは?
2021年4月に沖縄4地域と台湾で、新種のオオムカデが発見されました。
体長20cm、体幅2cmと最大級の大きさです。
ヒスイ色で、川に飛び込む習性から「リュウジンオオムカデ」と命名されました。
参考文献:琉球大学
ムカデは赤ちゃん幼虫でも怖い
まずはムカデの幼虫がどのような存在なのかについて確認しておきましょう。
ムカデの幼虫は、種類にもよりますがおおむね体長2mm程度のサイズです。形状は成虫のムカデとほとんど変わりませんが、体色は半透明や淡い色をしています。
ほとんどのムカデは母親を中心とした家族で生活しているので、ムカデの幼虫を1匹だけ見かけることはあまりありません。屋外では石や落ち葉をめくると見つけられることがあります。
ムカデは「子育て」をする生き物
群れをつくらないタイプの虫にしては珍しく、ムカデは幼虫が一人前になるまで親のもとで守られながら過ごす、「子育て」をする虫です。
ムカデは梅雨の時期に年2回20~50個ほどの卵を産み、孵化したムカデの幼虫は2カ月かけて体長20mm程度にまで成長します。この2カ月の間は、母ムカデがそばで付きっきりで面倒をみて、エサを分け与えて育てます。
時期が夏に差し掛かるころには幼虫も自力で餌を狩ることができるため、母親のもとを巣立って1匹で単独行動をとるようになります。その後、10回程度の脱皮を経て、我々が恐れる凶悪な「ムカデの成虫」として姿を現すのです。
ムカデの幼虫には要注意!
ムカデは幼虫であっても不用意に触れれば咬みつかれることがあります。そして、ムカデの幼虫がもたらす危険はそれだけではありません。前述の通りムカデは子育てする生き物なので、ムカデの幼虫が居る場所には、高確率でさらに危険な親ムカデもいることになるのです。
また、親元を巣立ったばかりのムカデの幼虫はサイズが20mm程度しかないため、見た目がヤスデの成虫とよく似ています。そのため、ムカデの幼虫とヤスデはしばしば混同され、油断して触ったら噛まれてしまったといったトラブルにつながることもあります。
危険な害虫に不用意に触れないためにも、ムカデの幼虫とヤスデの見分け方をおぼえておきましょう。
意外と違う?ムカデの幼虫とヤスデの見分け方
ヤスデは、ムカデと同じ「多足類」という種類の虫の1種です。ムカデと違って気性はおとなしく食べるものも落ち葉などで、ムカデに比べると全般的に身体のサイズが小さい傾向にあります。
ムカデの幼虫とヤスデ、このふたつの虫を見分けるには、それぞれの特徴を比較してみるのがわかりやすいかもしれません。そこで以下に、お互いの特徴をまとめておきました。
| ムカデ(幼虫) | ヤスデ(成虫) | |
|---|---|---|
| 写真 |  |
 |
| 身体の形状 | 平べったい形 | 厚みのある半筒状 |
| 触角 | 長い | 短い |
| 体色 | 半透明または淡い色 | 黒から茶褐色 |
| 動き | 凶暴ですばやい | おとなしくゆっくり |
| 食べるもの | 昆虫や小動物 | 腐った落ち葉など |
| 脚の数 | 長い脚が体節ごとに1対(2本) | 短い脚が体節ごとに2対(4本) |
こうして比較してみると、ムカデの幼虫とヤスデには意外と異なる点が多いことがわかります。這いまわっているムカデを間近で観察するのは少々気がひけますが、ハチのように高速で飛ぶ虫でもないので、一度確認してみるのがよいかもしれません。
また、ムカデの幼虫と違ってヤスデには刺激を受けると丸まって身を守るという性質があります。そのため、十分な安全を確保したうえで、棒かなにかでつついて反応を見てみるというのもひとつの判断基準として有効です。
おぼえておこう!ムカデの特徴
家の中で見かけた虫がムカデの幼虫だった場合にそなえて、ムカデの特徴についておさらいしておきましょう。特徴を把握することで、いざというときの対処に役立てられるかもしれません。
ムカデの毒性
ムカデの危険性の大部分を占めるのが、鋭く凶悪な形状をした大アゴから放たれる毒です。ムカデの毒はアゴの付け根にある「毒腺」という器官から分泌され、アゴで獲物に噛みついたあと傷口から毒を注入します。
ムカデの毒は種類によって細かい配合は異なりますが、おおむねアレルギー反応を引き起こすヒスタミンやセロトニンが主な成分です。この毒は人体に対しても影響があり、咬まれると強い痛みや腫れ、発熱などを引き起こします。
ムカデに咬まれたことで人が命を落としたという事例は、2018年現在報告されていません。しかし、アレルギー系の毒は体質によっては「アナフィラキシーショック」と呼ばれる重度のショックを発症するケースもあり、命に関わる危険性は否定できません。
またムカデ被害には咬まれることのほかに、無数の足で皮膚に傷をつけられ、そこから毒が入り込むケースもあります。いずれの場合もムカデに触れないことが何よりの予防策となるため、見つけた場合は絶対に素手で触るようなことは避けましょう。
ムカデの天敵
地上に住む虫の中では最強クラスの実力をもつムカデですが、自然界にはムカデを捕食する天敵も多数存在します。一例をまとめると以下の通りです。
- 大型のサソリ、カマキリ、クモ
- ヘビなどの爬虫類や大型のカエル
- ムカデの毒に耐性をもった「イソヒヨドリ」
- 猫やネズミなどの哺乳類
大型のムカデはクモやカエル、小鳥さえも捕食することがありますが、一方でムカデよりも大きな虫や動物には食べられてしまう関係にあります。猫をペットとして飼っているご家庭では、意外と猫が侵入したムカデを食べてくれているかもしれません。
またムカデの天敵については、「ムカデに天敵はいないのか??ムカデの恐るべき生命力と下剋上!!」という記事でも詳しくご紹介しています。もしご興味がおありでしたら、ぜひ参考にしてみてください。
どうして家に入ってくる?ムカデが生息しやすい環境とは
凶暴な性質と強力な毒アゴによって、ときには人間にすら襲い掛かることのあるムカデ。そもそもムカデたちは、なぜ人間の住む家に入り込んでくるのでしょうか。ムカデや幼虫の出現を防ぐための前提知識として、ムカデの住み着きやすい環境について確認しておきましょう。
ムカデは巣を作らない!
家の中でムカデや幼虫を見かけたとしても、家に巣を作って住み着いているとは限りません。ムカデは巣作りして一カ所に定住する生き物ではないためです。エサとなる小さな虫を求めて徘徊するなかで、偶然民家の中に入り込んできたというケースがほとんどです。
ムカデが家の中に出現する理由
前述のとおり、ムカデは特定の住処をもたない生き物です。とはいえ、どこにでも現れるというわけではありません。ムカデにも好む環境とそうでない環境があり、ムカデにとって過ごしやすい場所にはムカデが出現する可能性が高くなります。
ムカデの好む環境とは、「ジメジメしている」「狭くて暗い」「エサとなる虫が豊富にいる」という3つの条件を満たした場所です。ムカデは乾燥と高温に弱く、また大きな身体を維持するためにたくさんのエサを必要としています。
つまり、家の中にジメジメした暗くて虫の多い場所があると、ムカデが過ごしやすい環境をもとめて侵入してきやすくなるのです。
家の中に多く生息している虫というと、まずゴキブリが思い浮かびますよね。ゴキブリの発生は、ゴキブリを捕食するムカデを呼び寄せます。したがって、ゴキブリの多い家にはムカデも寄ってきやすいという最悪の連鎖反応が起こってしまうのです。
侵入経路をふさいで対策!ムカデの予防・駆除方法
被害を受けるリスクを極力減らすためにも、ムカデやムカデの幼虫が家の中に入り込ませない予防策を考えてみましょう。
ムカデの寄り付きにくい環境をつくる
ムカデは定住することのない生き物なので、居心地の悪い環境からはすぐに出ていきます。ムカデの好む湿気や他の虫を防ぐことで、めぐりめぐってムカデ対策にもなるのです。
まずは、家の掃除から始めましょう。長い間動かしていない家具や、閉じっぱなしの収納などは湿気がこもる原因となります。定期的に掃除をおこなうことで、風通しがよくなり湿気もこもりにくくなることでしょう。
また食べかすや生ごみ、積もったホコリはゴキブリなどの害虫のエサになります。とくにゴキブリはムカデの大好物なので、徹底的に駆除してしまうのが一番です。
侵入経路をふさぐ
ムカデは本来屋外に住む生き物なので、家の中に出現する場合はまず間違いなく外から入り込んできています。ムカデの侵入経路をふさぐことで、家の中でムカデに出会う確率を大幅に減らせるはずです。
ムカデは平たい形状の身体をしており、ほんの数mm程度の隙間からでもたやすく家の中に入ってきてしまいます。またエアコンの排水ホースは屋外から室内機につながっているので、これもムカデの侵入経路になります。
排水ホースの先端に害虫防止ネットを被せ、がたついた網戸など小さな隙間のある場所にはムカデ除けの薬剤をまいておきましょう。
ムカデに遭遇してしまったときは……
予防策を講じてもなお、家の中で小さなムカデのような虫に遭遇してしまったときは、まずそれがムカデの幼虫なのかヤスデなのかを確認しておきましょう。もしもムカデの幼虫だったら、すぐに対処が必要です。
ムカデ退治には、市販の殺虫剤が有効です。殺虫剤が手元にないときや、ペットの近くなど薬剤を使いにくい場合は、ドライヤーの温風を使ってみましょう。
ムカデは熱に弱く、体温が50℃以上になると身体のタンパク質が固まって動けなくなります。殺虫剤に比べると多少時間はかかりますが、逃がすことなく退治できるはずです。
ムカデ駆除なら生活110番へご相談ください
弊社「生活110番」は、ムカデの生態に詳しい駆除専門業者をご紹介しております。全国各地に加盟店を持っているので、ご連絡いただければ早急に業者の手配をいたします。そのため、緊急のときでもお待たせすることなく、安心してご活用いただけるシステムです。
生活110番をおすすめするポイントは、相談、調査、見積りがすべて無料であることです。
「話だけ聞きたい」「費用だけ知りたい」という方も大歓迎。お見積りをご提案いたしますので、ゆっくりご検討ください。正式なご契約を結ぶまではキャンセル料も一切ございません。
ムカデの発生にお困りの際は、ぜひとも生活110番までご相談を。駆除~予防まで自信もって施工させていただきます。
24時間365日オペーレーターが待機しておりますので、お電話・メールお気軽にご連絡ください。お待ちしております。
\ 完全無料 /
厳選した全国のムカデ駆除業者を探せます!
×
関連記事カテゴリ一覧
ムカデ駆除の記事アクセスランキング
ムカデ駆除の最新記事
カテゴリ別記事⼀覧
- お庭の手入れ
- 害虫駆除
- 害獣駆除
- 電気工事
- 鍵開け・交換・修理
- 窓ガラス修理・ドアノブ修理
- 家の修理
- バッテリー上がり
- ハウスクリーニング
- ペット火葬・葬儀
- 家電修理
- パソコン修理・ネット回線
- 家具・雑貨の修理
- 外壁・屋根工事
- リフォーム
- 防犯カメラ設置
- 盗聴器・その他調査診断
- 便利屋・代行サービス
- 引越し・配送サービス
- オフィス・店舗向けサービス
- その他








