
蜂の巣を作らせたくない!
そうですよね、家に蜂の巣ができたら怖いものです。
「毎年、蜂の巣ができる」「去年、巣を作られた」「最近、家のまわりでハチをよくみかける」
このような方は、当記事がご紹介する蜂の巣予防方法をぜひ目を通してみてください。
予防って自分でできるの?
大丈夫、ご安心ください。ここでご紹介する方法は、すべてご自身でおこなえる蜂の巣予防対策を、わかりやすく説明しています。
蜂の巣予防で大切なことは、2点。
- 蜂の巣ができる場所を知っておく
- 予防する時期、タイミングを逃さない
殺虫剤スプレーやハッカオイル・金網など、市販で安価で手に入る道具で巣作りを防止するので、タイミングさえ合えば気軽にできます。
効果的な予防方法を解説しているので、気になる対策をぜひ取り入れてみてくださいね。
ただし、すでにもう巣が作られたいる方は、予防方法では間に合いません。
駆除としての対応が必要なので、業者への相談をご検討ください。
- おすすめの蜂の巣予防法は「忌避剤」「場所の封鎖」「蜂の捕獲」
- 効率的な予防法:蜂の活動時期に合わせて春~夏ごろに予防する
- 軒下・玄関・屋根裏に蜂の巣が作られやすい
- 予防対策後も継続することで効果がある
- もしも蜂の巣を発見したら、早めに駆除をする
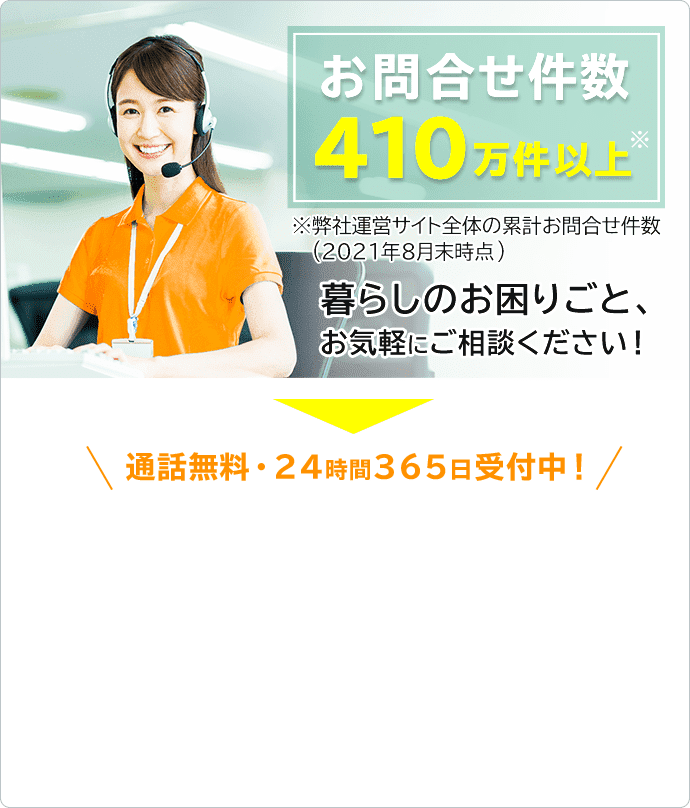
目次
3つの蜂の巣予防法【臭い・封鎖・捕獲】
蜂の巣の予防方法として代表的なのは以下の3つです。
- 蜂が嫌がる臭いを使って、住みづらい環境を作る
- 物理的に巣を作れないように、場所を封鎖する
- 巣を作る女王蜂を捕獲する
それぞれ具体的な対策方法をご説明していきます。
①蜂の嫌いな臭いを利用する
蜂の巣予防する方法の1つめは「蜂が巣を作りたくない環境にする」ことです。
蜂が苦手な香りや成分を使って、蜂にとって嫌な生活場所にしてしまいましょう。
忌避剤として利用できるグッズを3つご紹介します。

蜂はミントの香りが苦手といわれています。
ミントから抽出されたハッカ油を、蜂の巣予防をしたい場所にスプレーしておきましょう。
自然成分なので人にも環境にも優しいため、薬剤が苦手な方にはおすすめです。
蜂駆除用の殺虫スプレーを、巣を作られそうな場所に噴霧しておきましょう。
殺虫スプレーを吹きかける場所については、「巣が作られやすい場所」にて詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
焦げくさいニオイのする木酢液を、蜂は苦手としています。
巣が作られそうな場所に木酢液を散布しましょう。庭木や植え込みなどに巣を作られることを予防したい場合は、木酢液をバケツに入れて設置するだけでも効果があります。※木酢液特有の焦げくさいニオイは人にとっても気になることがあります。洗濯物にニオイがうつってしまったり、窓からニオイが入り込んだりするので、木酢液を使うときは、風向きや使用場所に注意したほうがよさそうです。
以上の3つが、グッズを活用した予防法です。
注意点として、
- エアコンの室外機など、機械類に噴射すると故障してしまうことがある
- 雨が降ると忌避成分が流れ落ちてしまうことがある
このようなことがあるので、次でご紹介する予防方法②と③もチェックしておいてくださいね。
グッズを利用するより効果が薄いですが、簡単でお手軽にできる予防対策です。
②蜂の巣が作れないようにする
2つ目の予防方法は「物理的に巣を作れないようにする」ということです。蜂の習性や特徴を生かして巣が作られそうな箇所を対策しましょう。

蜂は、土中や木の根元のような外敵に見つかりにくい閉鎖的な空間を好む傾向にあります。
家屋でいえば天井裏や床下などは蜂に好まれる場所です。このような場所に通じる隙間や通気口に網をかけ、出入り口を封鎖してしまいましょう。封鎖するときは金網などの「丈夫かつ通気性も保てるモノ」を用いるとよいです。
蜂は雨で羽が濡れてしまうと動きがにぶり、うまく飛ぶことができなくなります。そのため蜂は、「雨」を防げる場所を選んで巣を作る傾向があります。庭木を剪定するなどし、雨風をしのげる場所を徹底的につぶしておくとよいでしょう
③蜂を捕獲する
蜂の巣を作られないようにするためには、蜂をおびき寄せて捕まえてしまうことも有効です。スズメバチとアシナガバチの巣は、女王蜂が1匹で作り始めます。巣作りを始める前に女王蜂を捕獲することができれば、巣を作られる危険性を減らすことができるでしょう。
蜂を捕まえる道具として、捕獲器というものがあります。捕獲器とは、蜂が好む香りを出しておびき寄せ、捕獲する装置のことです。
捕獲器は市販品のほか、ペットボトルを使って手作りすることもできます。

- 6月以降は、攻撃性の高い働き蜂が増えるため、捕獲器で蜂をおびき寄せることは危険!
- 誘引捕獲器と忌避剤の同時活用は、効果を打ち消し合ってしまうので、どちらか1つに絞る
【番外編】新聞紙で作るダミーの巣がアシナガバチ予防になる?
新聞紙を丸めて、蜂の巣サイズにして吊るしておくとアシナガバチが寄り付かないという噂があります。
ただ、残念ながら効果の立証はされていません。ご自身で作製してみるのもよいかもしれませんが、ダミーだけの蜂の巣予防対策はやめておいたほうが無難です。
これら以外にも蜂の予防法はいくつもあります。より徹底した予防をするならぜひこちらもご覧ください。
あわせて読みたい
蜂の巣を作られやすい場所を重点的に予防しよう
冒頭でお話した、蜂の巣予防の重要ポイントのひとつ。
蜂に巣を作られやすい場所の特徴を知っておくと、効率よく予防対策ができます。
【事例で紹介】巣が作られやすい場所とは

一般的に蜂は、つぎのような条件に当てはまる場所を選んで巣作りをおこなうといわれています。
◆雨風がしのげる
◆乾燥している
◆エサに困らない
◆柔軟剤などの甘い香りがする
ここで2019年度、弊社が請け負った約700件以上のデータから抽出した施工場所グラフをご覧ください。

- 軒下・玄関・屋根裏で半分を占めている!
- 植木やベランダも多い!
- 換気口・通気口、窓、駐車場も注意が必要!
さきほどお伝えした巣作りの条件「外敵に襲われにくい」「乾燥している」「雨風がしのげる」に当てはまりますね。
そのほか、件数は少ないですが、以下のような場所のケースもありました。
| 意外な場所 | 目立たない場所 |
| 犬小屋 | 室外機 |
| 鳥の巣箱 | 壁の中 |
| ウッドデッキ | コンセントの中 |
| シャッター | 車の中 |
このように、蜂はさまざまなところに巣を作ります。
さすがにすべての場所を予防対策をすることも難しく、またもし巣を作られても発見が遅れてしまいそうです。
蜂の出入りしている場所から巣を見つけるか、細かく点検するかで発巣を発見するしかありません。
スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチが巣を作る場所

日本の住宅に巣を作る蜂として有名なのは、「スズメバチ」「アシナガバチ」「ミツバチ」の3種類です。
蜂によって、巣を作る場所に違いがあります。もし家のまわりで以下の蜂を何度も見かけたら、好む場所の特徴を確認し、とくに予防に力を入れたほうがよさそうです。
巣の形状
マーブル模様で丸い形をしており、大きさは最大で1メートル近くになることもある。
巣作りの場所
・軒下などの開放的な空間に巣を作る
・屋根裏などの閉鎖的な空間を好む
・土の中に巣を作る
(※種類によって、好む場所が異なる)
巣の形状
巣穴が見え、お椀を逆さまにしたような形。大きさは最大で15センチメートルほどになる。
巣作りの場所
雨風の当たらない開放的な空間を好む傾向がある。
巣の形状
板のように平たい形で、ミツのロウができている。
巣作りの場所
閉鎖的な空間に巣を作る傾向がある。
3種のなかでもとくに、スズメバチは危険度が高く、刺される被害も後をたちません。
スズメバチに狙われないよう、注意してください。
蜂の巣予防に適したタイミングとは
蜂の巣予防に重要なポイント、場所の次が時期です。
蜂の活動時期にあわせて適したタイミングで対策をおこなうことで、安全で効果的な予防ができます。
蜂の活動時期
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズメバチ | |||||||||||||||
| アシナガバチ | |||||||||||||||
| ミツバチ | |||||||||||||||
スズメバチとアシナガバチは女王蜂のみが冬眠して冬を越します。ミツバチは女王蜂だけでなく働き蜂も越冬し、年間をとおして生息しています。
スズメバチとアシナガバチの予防は女王蜂だけの時期に
スズメバチ・アシナガバチの活動サイクル

殺虫スプレーなどを使って蜂が嫌がる環境を作ったり、網などで蜂の巣が作れないようにしたりといった対策は、蜂が巣を作り始める前の3月頃からおこなうとよいでしょう。7月ごろまで継続的におこなうと、より効果的です。
また、女王蜂を駆除する場合は4月~5月ごろが最適といえます。蜂の種類にもよりますが、女王蜂は4月頃から巣を作り始めます。作り始めは働き蜂はおらず、女王蜂のみで巣を作っている段階です。しばらくして巣が大きくなると働き蜂が生まれ、攻撃性も高くなり、危険も伴うようになります。
そのため、女王蜂のみの段階である4月~5月ごろまでに女王蜂を駆除し、蜂の巣を作られないようにしておくとよいでしょう。
蜂を見かけるときには「日没後」に
すでに近所で蜂を見かけているというときは「日没後」に予防作業をおこないましょう。日中は巣の外を飛び回っている蜂も、夜になると幼虫の世話をするため巣の中に戻ります。
また、気温が低い夜は蜂の動きも鈍くなります。そのため、日中よりも日没後のほうが襲われるおそれも低くなるのです。すでに蜂を見かけているときは、日没後に予防作業をおこなうとよいでしょう。
予防後は定期的な見回りで営巣対策!
ご紹介した予防策をいくつか実施したあとは、実施箇所を定期的に見回るようにしましょう。「蜂の巣はできていないか」「木酢液のニオイが消えていないか」「捕獲器の誘引剤は減っていないか」など、おこなった予防対策の効果が継続しているかを確認します。木酢液が減っていたり誘引剤が減っていたりすると予防効果が低くなってしまうので、再度予防策をおこなうようにしてください。
また、見回りにいくときには4つの注意点があります。身につけるだけで蜂を呼びよせてしまうモノがありますので、蜂に刺されてしまわないように注意点はしっかりと覚えておきましょう。
注意点2.ケガをしないように長袖・長ズボンを身につける
注意点3.蜂はニオイに敏感なので、香水・整髪料などはつけない
注意点4.甘いニオイは蜂を引き寄せてしまうので、ジュースを持っていかない
もし蜂の巣を作られてしまったときは弊社へご相談ください
蜂に巣を作られてしまったとき、すでに蜂の巣を発見したときは、早めの駆除をしてください。
蜂の巣駆除を個人で対応するよりも、プロの業者に依頼した方が安全であり、確実です。
また、業者であれば駆除後のアフターケアとして予防対策もしっかりいたします。
弊社がご紹介する業者は、すべて蜂駆除のエキスパートばかりです。専門的な知識やスキルを持っているため、あっというまに駆除完了。お客様は、家の中で待っていてくだされば、後片付けもすべてこちらで処理いたします。
ご相談、現地調査、見積りは無料となっていますので、どなたでもお気軽にご利用できます。
もちろんキャンセル料もかかりません。話を聞いてみてから、ゆっくりご検討ください。
蜂のことで気になること、ご不安なことがあれば、親切丁寧なスタッフが親身になってカウンセリングをし、駆除のお手伝いをさせていただきます。
みなさまからのご連絡いつでもお待ちしております。
\ 完全無料 /
厳選した全国の蜂の巣駆除業者を探せます!
×
関連記事カテゴリ一覧
蜂の巣駆除の記事アクセスランキング
蜂の巣駆除の最新記事
カテゴリ別記事⼀覧
- お庭の手入れ
- 害虫駆除
- 害獣駆除
- 電気工事
- 鍵開け・交換・修理
- 窓ガラス修理・ドアノブ修理
- 家の修理
- バッテリー上がり
- ハウスクリーニング
- ペット火葬・葬儀
- 家電修理
- パソコン修理・ネット回線
- 家具・雑貨の修理
- 外壁・屋根工事
- リフォーム
- 防犯カメラ設置
- 盗聴器・その他調査診断
- 便利屋・代行サービス
- 引越し・配送サービス
- オフィス・店舗向けサービス
- その他










